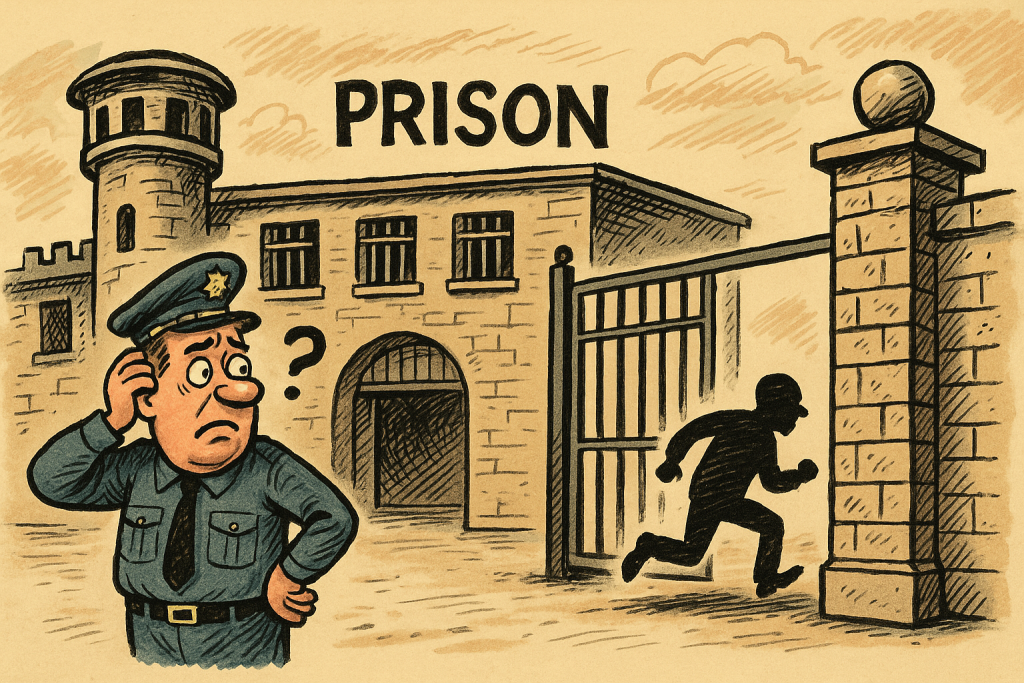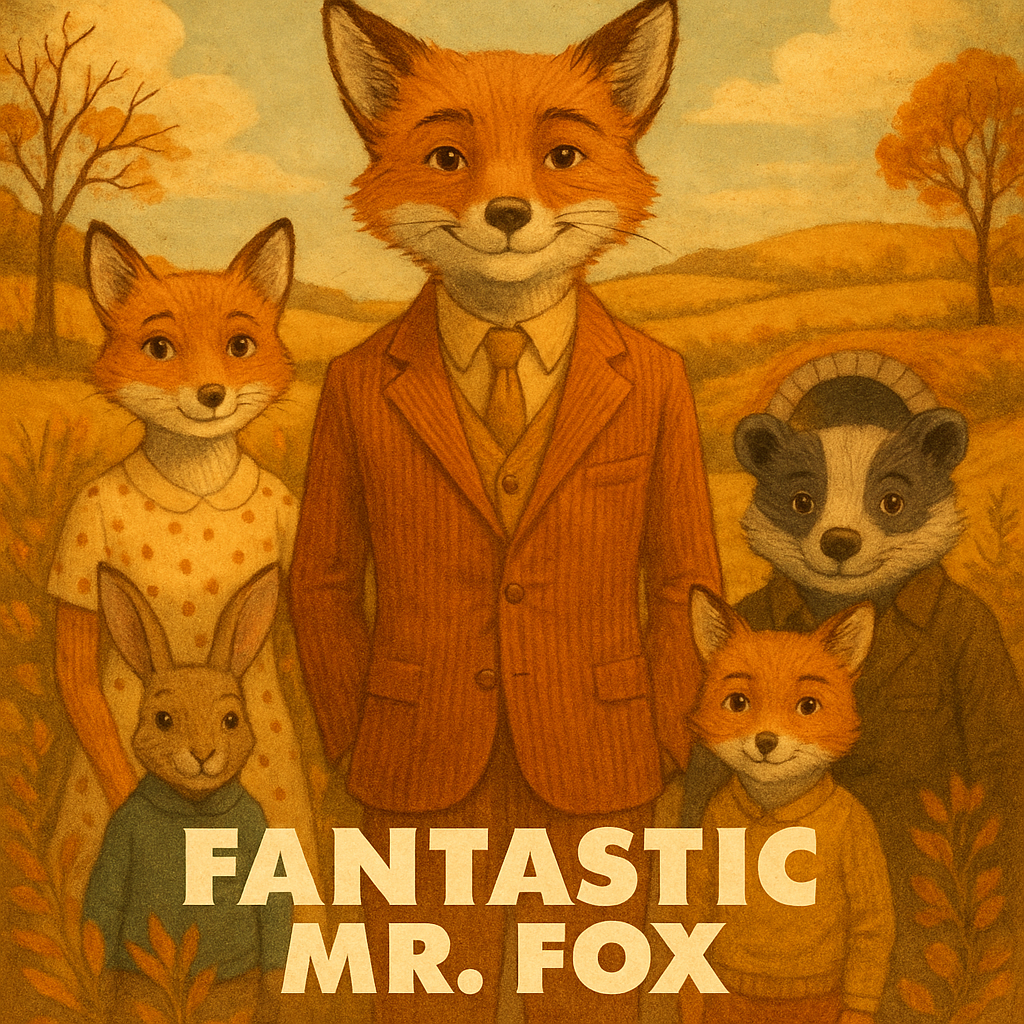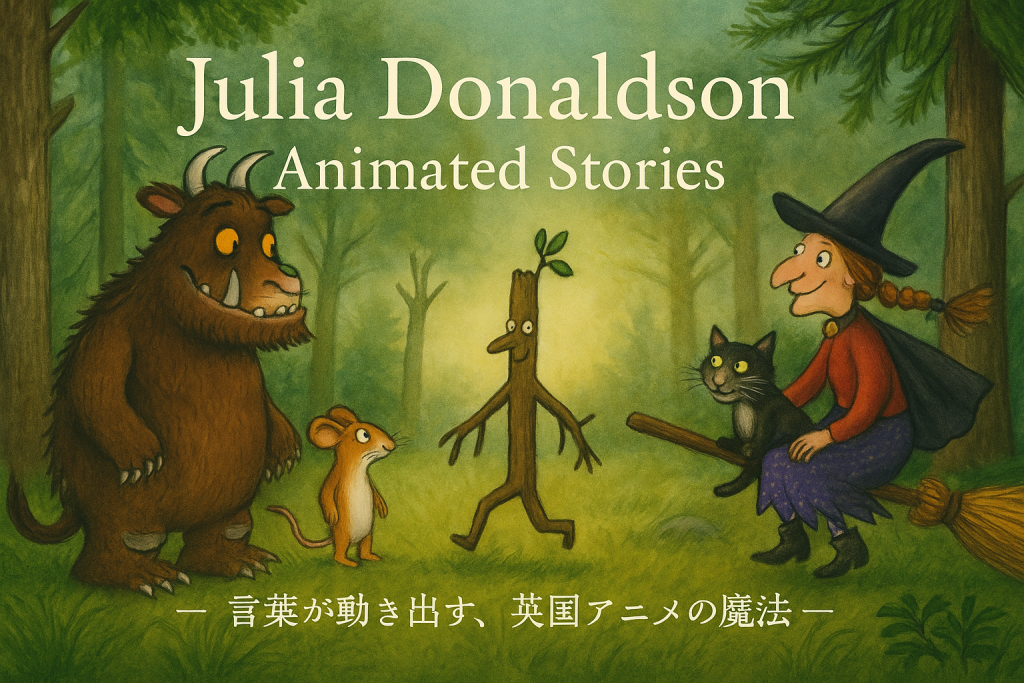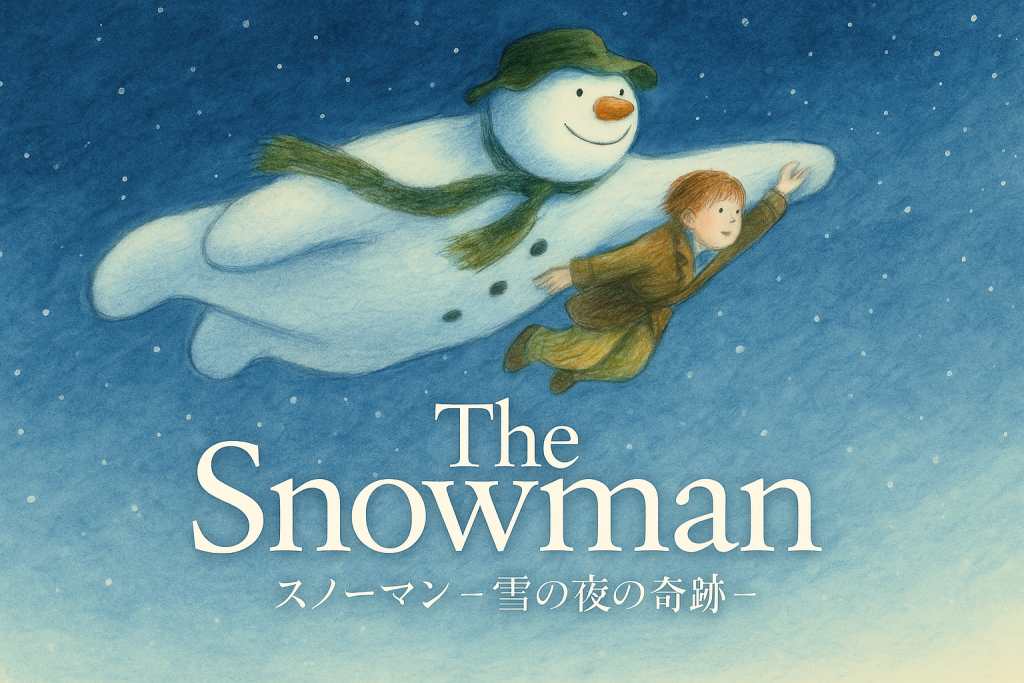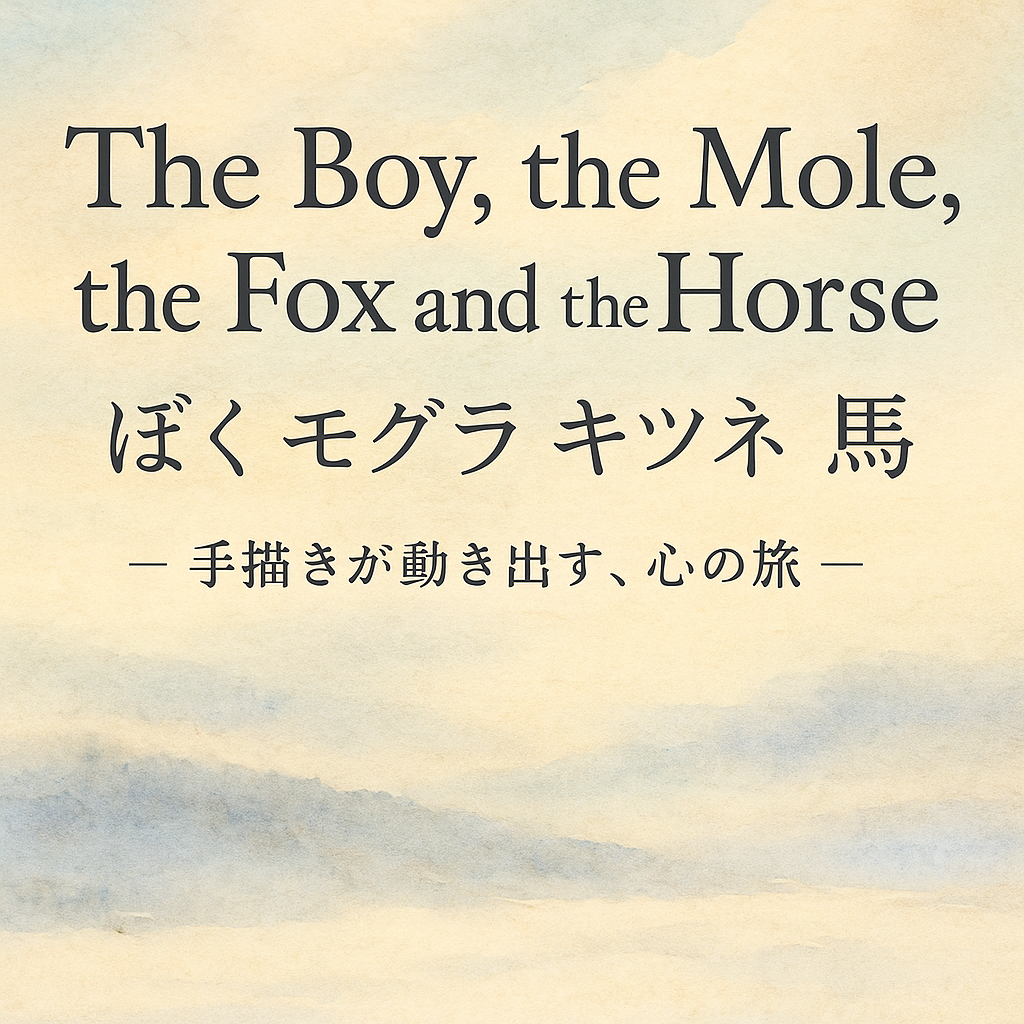…
Author:admin
過密化するイギリス刑務所の現実――そして生じる「誤った釈放」という危機
…
イギリス刑務所、また「うっかり」強姦犯を自由に
…
『Fantastic Mr. Fox』── ウェス・アンダーソンが描く、黄金色のストップモーション世界。
…
『グラファロー』から『スネイルとくじら』まで──ジュリア・ドナルドソンが紡ぐ英国アニメの魔法。
…
『スノーマン』── 雪の夜にだけ訪れる、静かな奇跡。
…
『ぼく モグラ キツネ 馬』── 心がほどける英国発アニメ、優しさが世界を包む34分
…
政治家が言う「生活コストの改善」とは実際になんなのか
…
マンチェスターの悪夢:100人以上を襲った「世界最悪のレイプ犯」
…
ブリストルで燃やされた男と、暴走した“正義”の行方
…