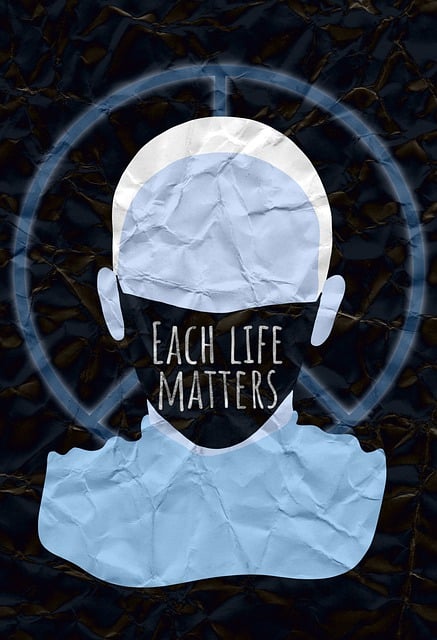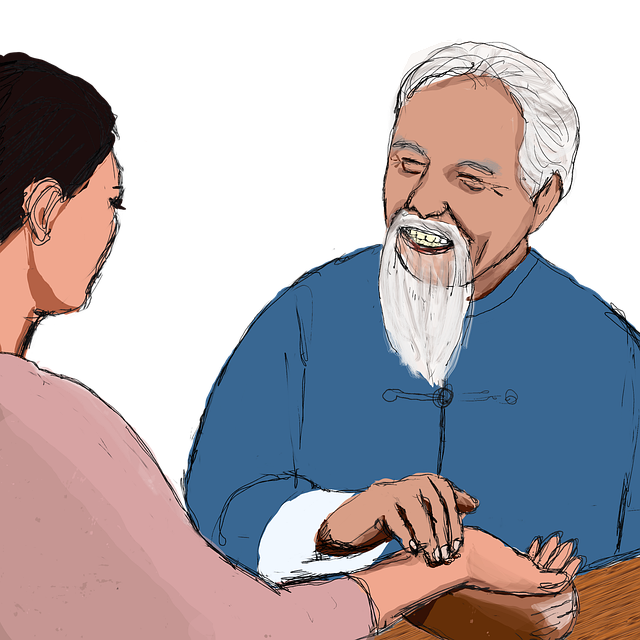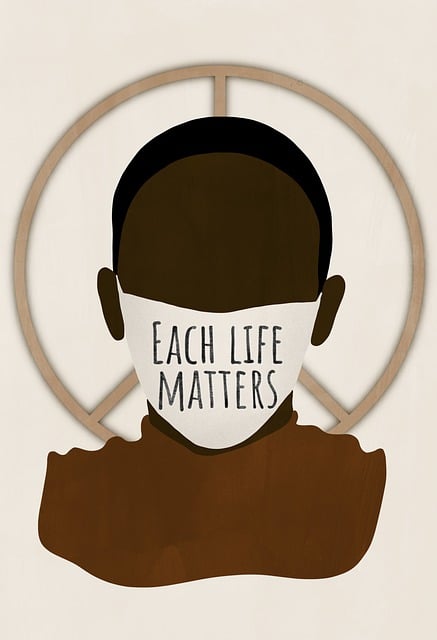…
人種差別
差別用語に敏感すぎるイギリスの空気 ~メディア報道と日常のギャップについて考える
…
イギリス警察と「白人至上主義」の関係を巡る考察
…
イギリスでアジア人アスリートが活躍しはじめたのは本当に最近のこと? -スポーツと「見えない疎外」の歴史
…
排除という本能と、イギリスに根づく人種差別の「現在形」
…
北アイルランド暴動に見る「排外主義」の実像:ルーマニア人容疑者を巡る怒りとその根底にある差別意識
…
イギリスのメディアにおける人種報道の偏り──見落とされる被害者と増幅されるステレオタイプ
…
「全部中国人?」——イギリスにおけるアジア人ステレオタイプの実態とその背景
…
社会の分断が浮き彫りに:イギリスで深まるヘイトと排他主義の連鎖
…
リフォームUKと北東イングランドの政治地形――なぜ極右ポピュリズムがこの地に根を張るのか
…