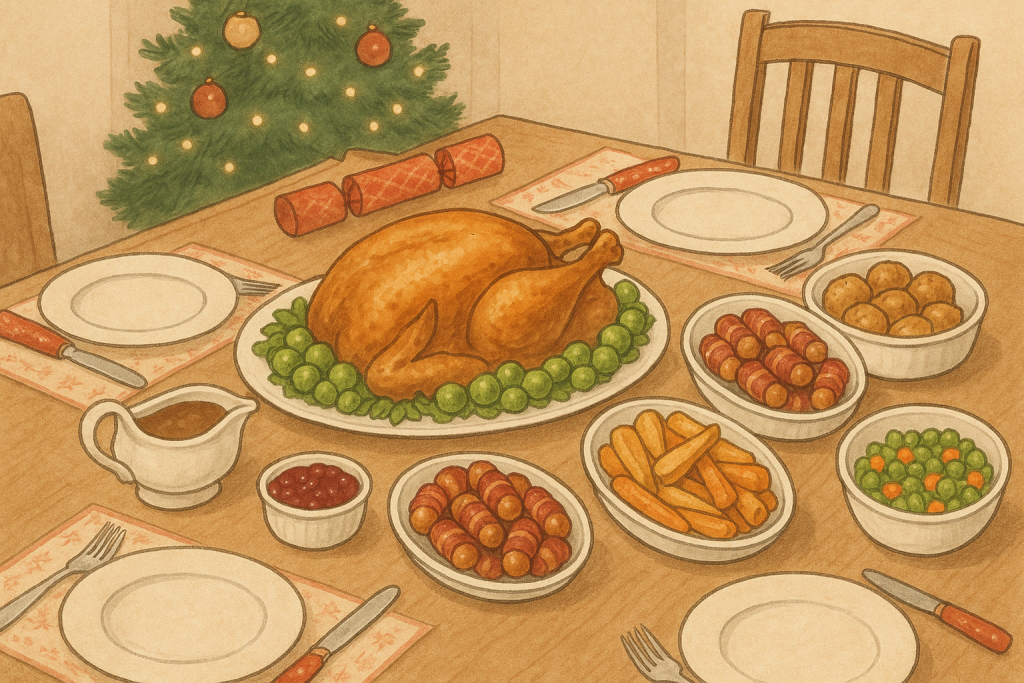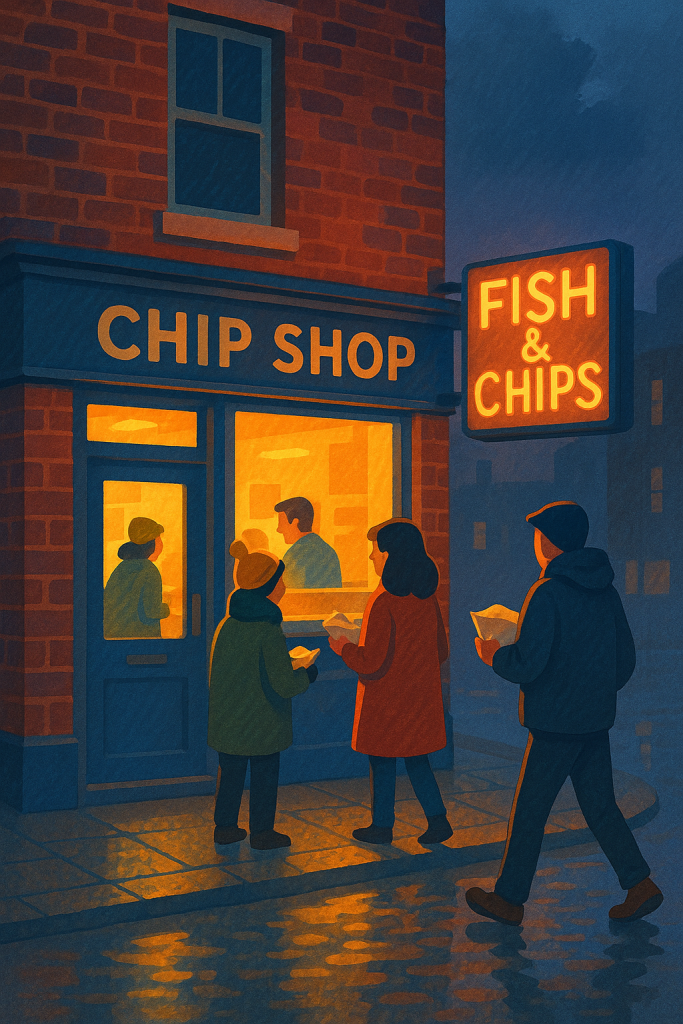…
食文化
イギリス人の夜食はカップラーメンではなくシリアルって本当?
…
なぜイギリス人は毎日ジャガイモを食べられるのに、米は毎日食べたくないのか
…
イギリスのクリスマス定番ドリンクといえばモルドワイン(Mulled Wine)
…
イギリスのクリスマスディナー徹底ガイド|伝統メニュー・食卓マナー・日本での再現アイデア
…
英国チップショップ文化とテイクアウェイの進化|フィッシュアンドチップスが育んだ国民食の物語
…
テイクアウェイの歴史から見る英国フードカルチャー|フィッシュアンドチップスが生んだ国民食文化
…
海辺で冷めにくい持ち帰り術|フィッシュアンドチップスの紙包み折り方と順番を完全解説
…
イギリス各地のベスト衣研究|タラとハドック・揚げ油で変わるフィッシュアンドチップスの味
…
フィッシュアンドチップスに合うビネガー徹底比較|モルト・サイダー・ホワイトの違いと選び方
…