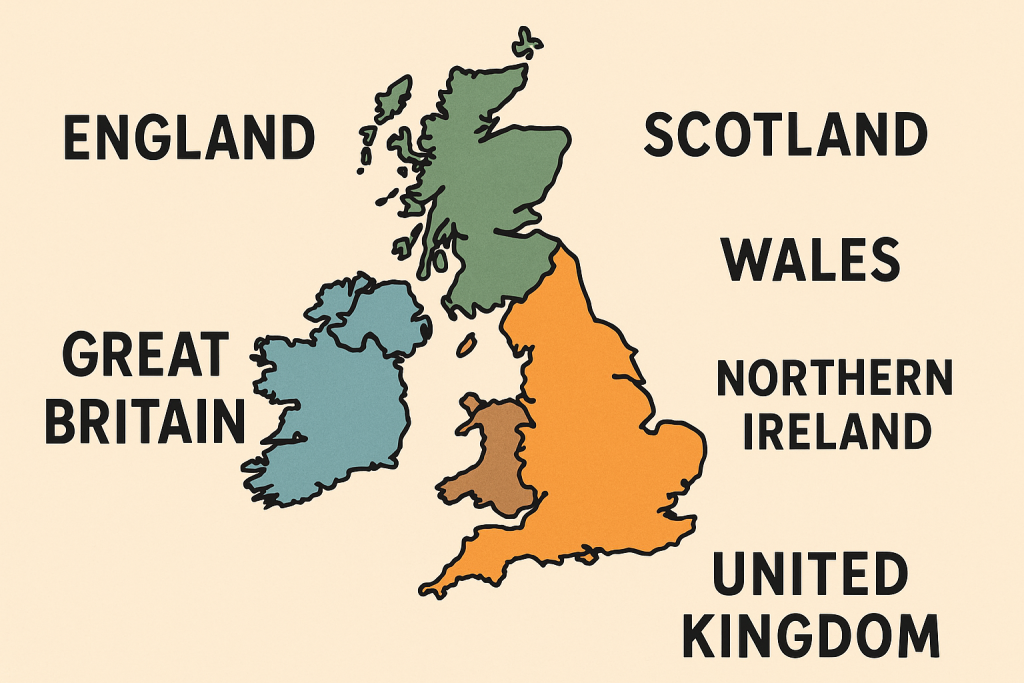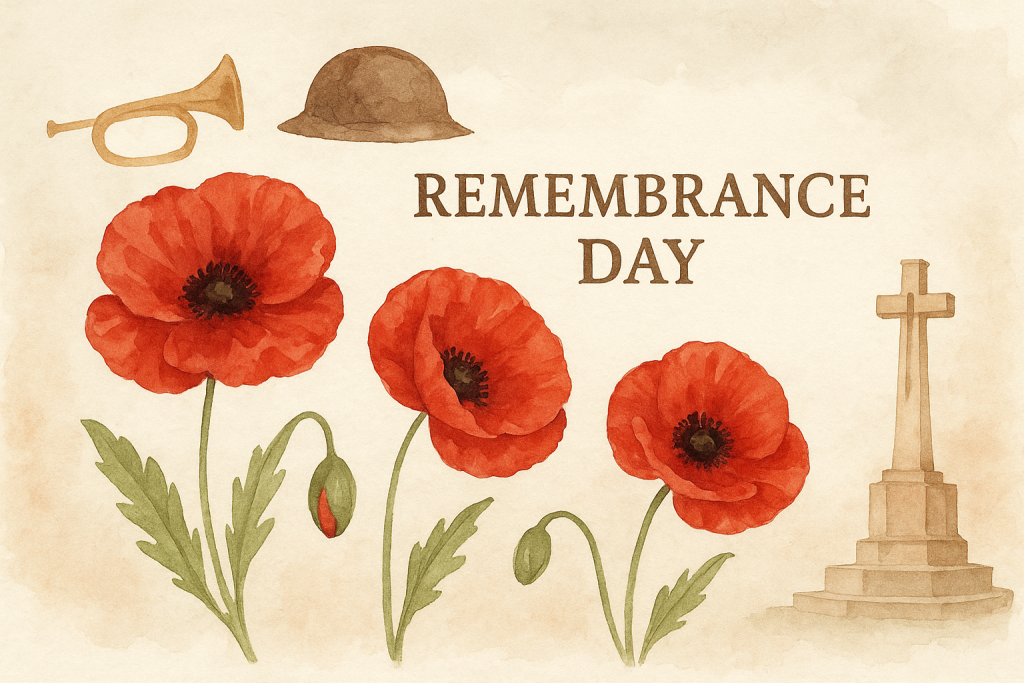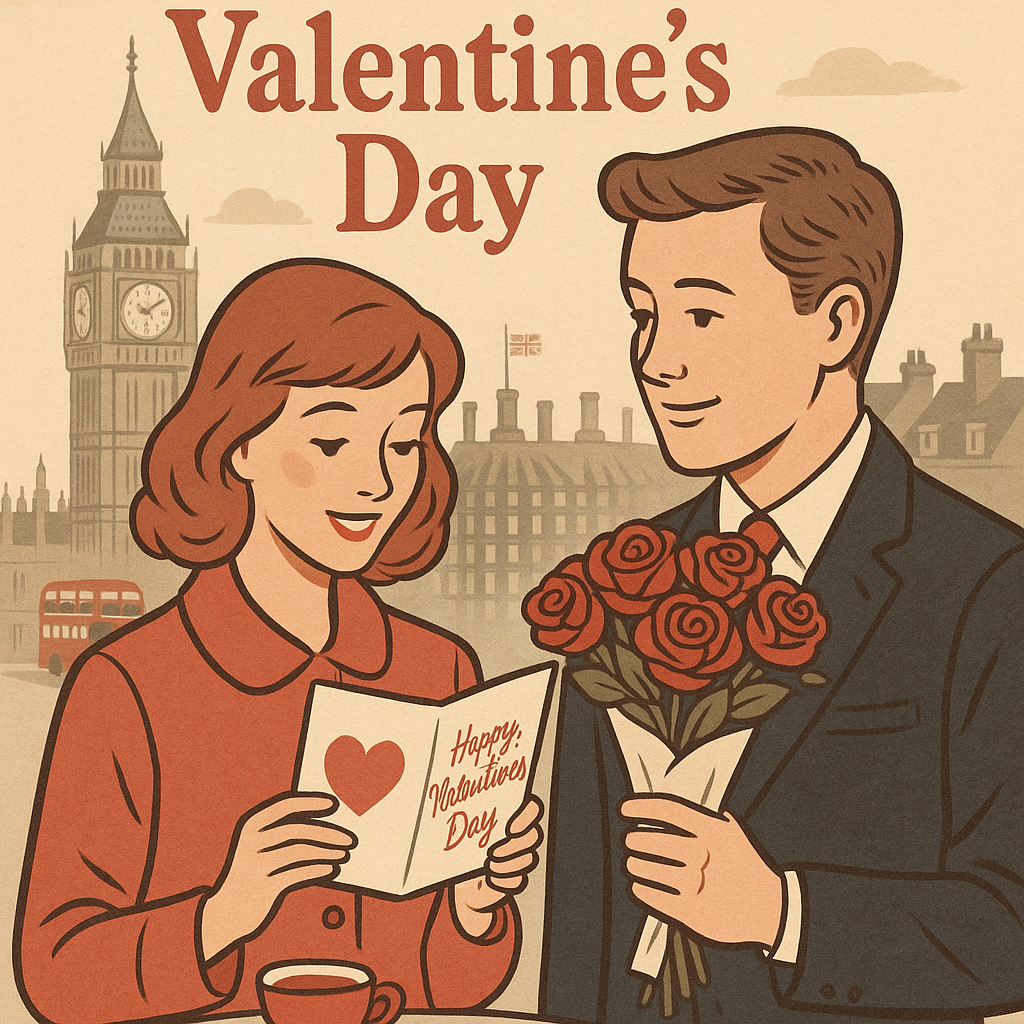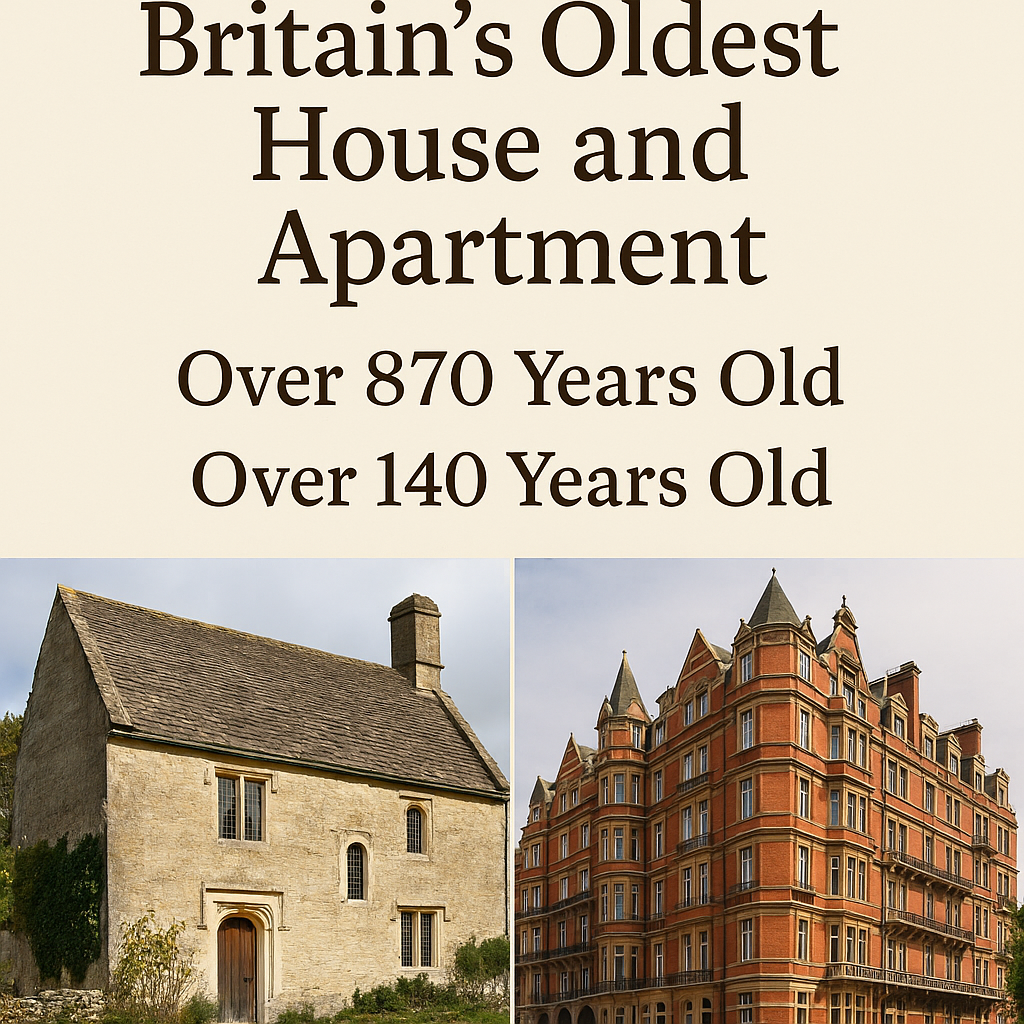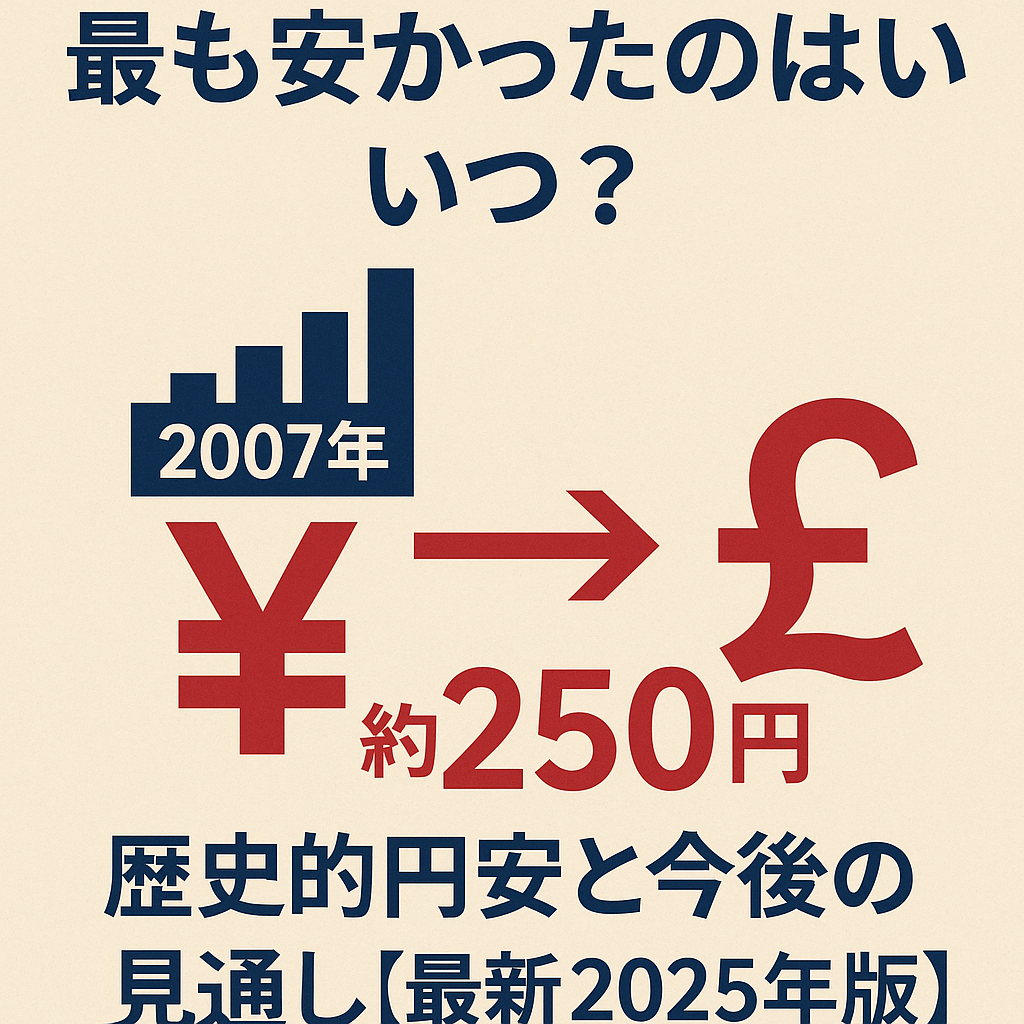…
歴史
わずか100年前に世界をほぼ支配していた大英帝国について
…
イギリスを発見した人は誰?
…
イギリス・イングランド・UK・グレートブリテンは何が違う?意味・境界・歴史まで超初心者向けに解説
…
Remembrance Day(リメンブランス・デー)とは何か
…
バレンタインデーについて
…
イギリスで最も古い住宅とマンションは? ― 870年の時を超える家と、140年前の高級集合住宅
…
マーガレット・サッチャーの思想と政策を徹底解説|右寄りと評された理由とは?
…
冬の海沿いで食べるフィッシュアンドチップスが最高な理由|歴史・誕生の背景と味の科学
…
日本円がポンドに対して最も安かったのはいつ?2007年の歴史的円安と今後の見通し【最新2025年版】
…