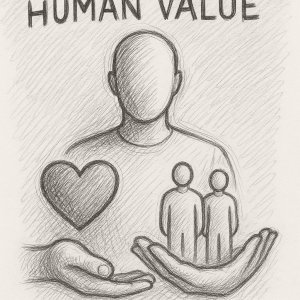
「価値」の物差しとは
私たちは日々、無数の判断をしながら生きている。その中には、目に見えない「人の価値」を無意識に評価している場面が数多く存在する。街を歩いているとき、電車で隣に座る人を見たとき、ニュースで紛争地の映像を見たとき、あるいは物乞いをする人に出会ったとき——私たちの脳裏には「この人はどれくらい価値があるのか」という問いが、知らず知らずのうちに浮かんでいる。
多くの社会では、「価値」が富や学歴、地位、出生地、国籍、外見などによって測られる傾向がある。そしてその価値観は、個人の意識だけでなく、社会構造やメディア、教育制度の中に深く根付いている。特に西欧諸国の一部、たとえばイギリスのような国では、歴史的に階級制度が存在しており、今もなおその名残が人々の無意識の中に残っている。
だが、果たしてそれは正しい「価値」の測り方なのだろうか?
無意識の中の差別と価値判断
私たちは「人間は平等である」と教えられて育つ。しかしその一方で、「成功者はすごい」「貧しい人は努力が足りない」といったメッセージを日々浴びている。その結果、意識の上では平等を信じていても、無意識のうちに他者を序列化し、自分より「下」と見なした人々に対して軽蔑や無関心を抱くことがある。
たとえば、街角で見かける移民労働者やホームレス、あるいはニュースで報じられる難民キャンプの人々。彼らに対して「かわいそうだ」と思うことはあっても、「自分と等しい人間だ」と心の底から感じるのは簡単ではない。それは、社会的に「価値の低い存在」として扱われる人々に対して、自分の中にも差別的な感情があることを示している。
これはイギリスに限ったことではない。むしろ私たち全員が、程度の差こそあれ、そのような感情を内に抱えている。私自身も、ニュースで中東の紛争地やアフリカの貧困の様子を目にしたときに、「ああ、気の毒に」と思うだけで、「もしかしたら自分があそこに生まれていたかもしれない」という想像にまでは至らないことがある。
イギリス社会における階級と価値観
イギリスは長い歴史の中で、明確な階級社会を形成してきた国である。貴族、上流階級、中流階級、労働者階級といった分け方は、現代でも依然として存在しており、教育、職業、言語(アクセント)などによって見分けがつくほどだ。
この階級意識は、日常的な人間関係の中にも浸透している。裕福な家庭に生まれ、名門校に通い、良い職に就いた人は、社会的に「価値が高い」と見なされやすい。逆に、貧困層、移民、難民、ホームレスなどは、「価値の低い存在」とされ、差別や排除の対象となることが多い。
しかし、こうした価値観は果たして本当に正しいのだろうか?人間の価値とは、その人がどれだけお金を持っているか、どこの国に生まれたか、どの学校を卒業したかで決まるのだろうか?そもそも、そんな「価値」なるものは、誰が、何の権利で決めているのか。
生まれる場所を選べないという真実
私たちは、誰一人として「自分がどの国に生まれるか」を選んでいない。日本に生まれた人、イギリスに生まれた人、アフリカの紛争地に生まれた人、パレスチナに生まれた人——それはすべて、偶然の産物に過ぎない。
もし自分が、今ガザで暮らしている子どもとして生まれていたら?もし自分が、水道もないサハラ以南のアフリカに生まれていたら?同じように「愛されたい」「学びたい」「自由に生きたい」と願っても、それが叶わない状況に置かれていたら?そのとき、自分は「価値のある人間だ」と信じ続けることができるだろうか?
それでも私たちは、どこに生まれようと、どんな状況に置かれようと、「一人の人間」としての尊厳と価値を持っている。貧困、紛争、差別に苦しむ人々も、それぞれに物語があり、人生があり、愛する人や夢がある。そのことを忘れてはならない。
移民、難民、そして「見えない人々」
ヨーロッパ諸国では、移民・難民に対する排斥感情が高まりを見せている。特に経済不安やテロの脅威などがあると、政治家やメディアはその矛先を「外から来た者たち」に向けることがある。イギリスのEU離脱(ブレグジット)も、その背景には移民への反感があった。
しかし、そのような人々は「自分の意志で好き勝手に移動している」のではない。多くの場合、彼らは紛争や貧困、政治的弾圧から逃れるために命がけで国を離れている。そして、異国の地でようやくたどり着いた先でも、彼らは「社会の最下層」として生きることを余儀なくされる。
私たちはそんな彼らを「かわいそう」と思うかもしれない。しかしそれでは不十分だ。本当に必要なのは、彼らを「等しい人間」として尊重することだ。同じように、夢を持ち、家族を愛し、笑い、泣く人間として、その人生に価値があることを認めることだ。
「ドラマ」としての人生を尊重する
すべての人間には「物語」がある。それは、その人だけの人生であり、唯一無二の経験であり、たった一つのドラマだ。
貧困に苦しむ家庭に生まれた少年が、家族のために水を汲みに毎日何キロも歩く姿。内戦で親を失い、弟を守るために難民キャンプで生きる少女。差別を受けながらも子どもたちに教育の希望を伝えようとする教師。そこには、映画や小説にも負けないリアルな人間の営みがある。
私たちは、そうした「一人ひとりのドラマ」に対して、敬意を払わなければならない。たとえそれが自分とまったく違う文化や価値観に生きる人であっても、その人の人生が、自分の人生と同じように「かけがえのないもの」であることを認めることが、人間としての最低限の誠実さではないだろうか。
私たちが変わることで社会が変わる
差別や偏見は、制度や構造の中にも存在するが、それ以上に私たち一人ひとりの「心の中」に根を下ろしている。だからこそ、それを乗り越えるためには、まず自分自身の中にある「無意識の序列意識」に気づき、それに疑問を投げかけることが大切だ。
「この人は価値が低い」と思った瞬間、「なぜそう思ったのか?」と問い直してみる。自分が「普通」だと思っていることが、実はどれだけ恵まれているかを振り返ってみる。そして、今この瞬間も、自分と同じように夢や痛みを抱えて生きている無数の人々に思いを馳せてみる。
そうした小さな気づきの積み重ねが、やがて社会を変えていく。人間の価値を、国籍や財産や学歴ではなく、「その人がそこに生きている」という事実そのもので認め合える世界へと。
どんな人間も、たった一つの命であり、たった一つの人生であり、たった一つの物語を持っている。私たちは、そのすべてを尊重する責任があるのだ。


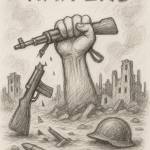
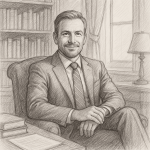


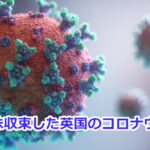



Comments