
イギリスでは近年、キャッシュレス化が進んでいます。コンタクトレス決済、スマホ決済、オンラインバンキングなど、便利なデジタル決済手段が当たり前になりつつあります。しかし、一方で「完全キャッシュレス化」に移行することには、なぜか大きな壁が存在しています。
多くの人は、「高齢者が現金を必要としているから」「地方の小規模店舗がカード手数料負担に耐えられないから」といった理由を挙げます。確かにそれも一因かもしれません。ですが、裏側では、もっと「腹黒い理由」が隠されているという説が囁かれています。以下は、あくまで“推測”ですが、その全貌を憶測的に掘り下げてみましょう。
キャッシュレス化の影の抵抗勢力
まず、一部で囁かれているのは「政治家と業者の癒着問題」です。
現金が存在することで便利なのは、一般市民だけではありません。政治家にとっても現金は「とても都合が良い」のではないか、と一部で疑われています。
例えば、現金での「寄付」や「バックマージン」は、電子決済に比べて追跡されにくい。もし完全にキャッシュレス社会が実現してしまえば、こうした裏金のやりとりは格段に難しくなり、癒着の温床が消えてしまうことになります。
もちろん、これはあくまで推測にすぎませんが、「特定の政治家たちが“高齢者保護”などの名目で現金維持を声高に主張するのは、自らの都合に一部基づいているのでは?」という見方は、時折メディアや庶民の間でも語られます。
キャッシュ・イン・ハンド経済の巨大な存在
もう一つの理由は、いわゆる「キャッシュ・イン・ハンド(Cash in hand)」で働く人たちの存在です。
これは、建設業、清掃、ベビーシッター、ケータリングなど様々な分野で「現金手渡しで支払われる報酬」によって生計を立てている人たちのことです。
ある憶測によれば、イギリスには数十万人規模(場合によっては100万人以上)の「キャッシュ・イン・ハンド」労働者がいると言われています。
この人たちは、現金収入で得た収入を申告しないことによって、所得税・国民保険料の支払いを回避している可能性があります。
さらに、驚くべきことに、こうした人々の中には「生活保護」を受けながら、裏でキャッシュ収入を得て「タンス預金」を貯めている人も存在すると噂されます。つまり、表向きは低所得者として家賃補助や医療補助を享受しつつ、裏では現金収入で豊かな生活をしている、という話です。
これが本当だとすれば、現金の存在は彼らにとって“不可欠”です。そしてキャッシュレス社会が完全に到来したとき、こうした「脱税的ライフスタイル」は立ち行かなくなるでしょう。銀行口座やデジタル決済では、すべての入出金が記録されるからです。
現金維持に“こだわる”政治家たちの不思議
表向きには「高齢者が不便になる」「地方の経済が崩壊する」などと現金維持派の政治家は主張します。
ですが、その裏には「票田を守る意図」や「自身のキャッシュフローを守りたい意図」が潜んでいる可能性は否定できません。
このように考えると、キャッシュレス化への移行にブレーキをかけている“見えない力”は、実は現金経済に依存している人々と、そこから間接的に恩恵を受けている一部の政治家たちなのかもしれません。
本当に困る人は誰か?
一方、完全キャッシュレス化が実現すれば、不正に所得税を回避している人々への打撃は大きいと考えられます。彼らは収入を隠せなくなり、税務署への報告義務が厳格化されることで、多額の追徴課税や罰則に直面するかもしれません。
また、「現金の癒着の温床」が潰されれば、政治の透明性向上にもつながるでしょう。
逆に言えば、これが実現しない現状は「現金経済を守りたい特定層」が強い影響力を持っていることを示しているのかもしれません。
終わりに
イギリス社会がキャッシュレス化に二の足を踏んでいる理由には、もちろん高齢者や地方経済の事情があることは確かです。
しかし、その裏側には、政治家と現金経済に依存する人々の“腹黒い利害”が隠されているという推測も、ある程度は的を射ているのかもしれません。
「現金派」を単なる弱者保護と捉えるだけでなく、時には「現金経済の恩恵を受けている人たちが存在する」という視点からも見てみることが、これからのイギリス社会を考える上で重要なのではないでしょうか。
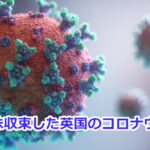







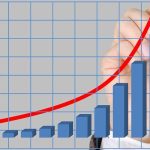

Comments