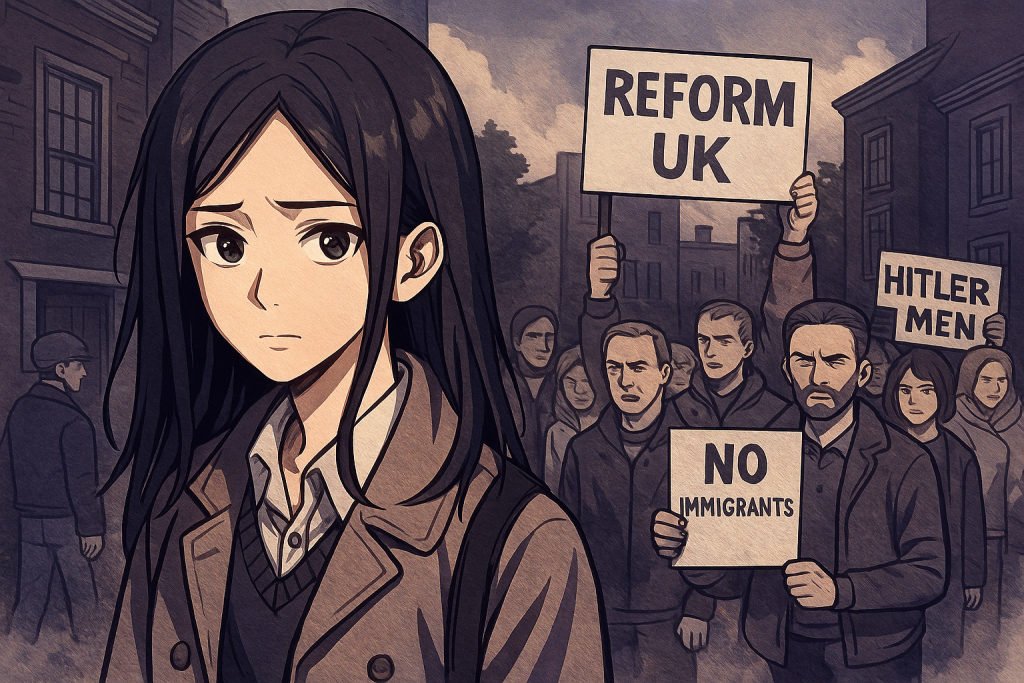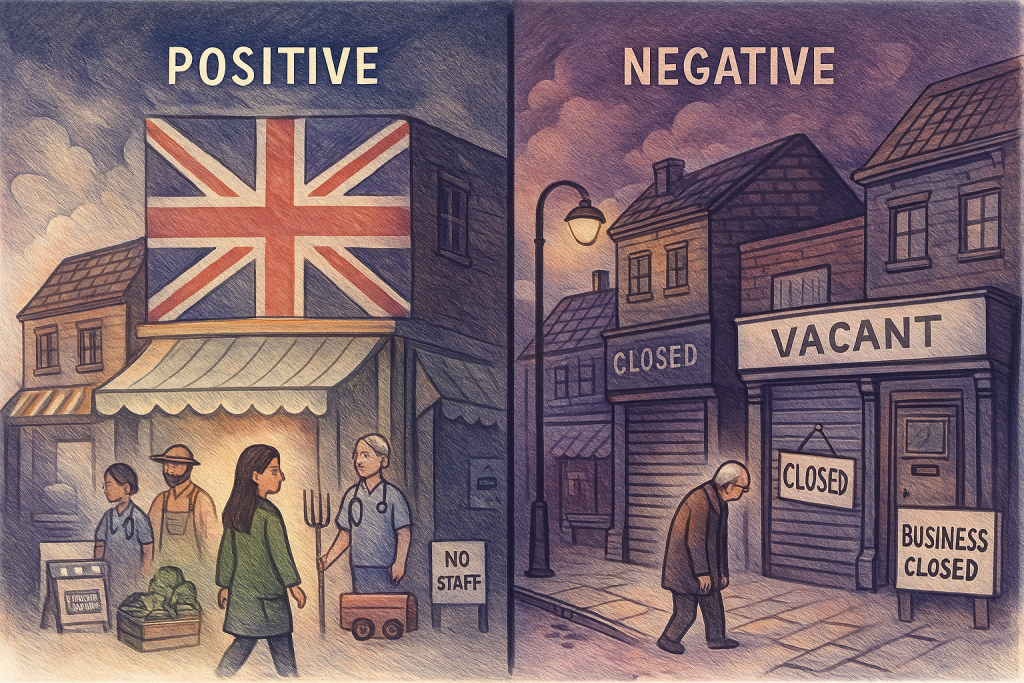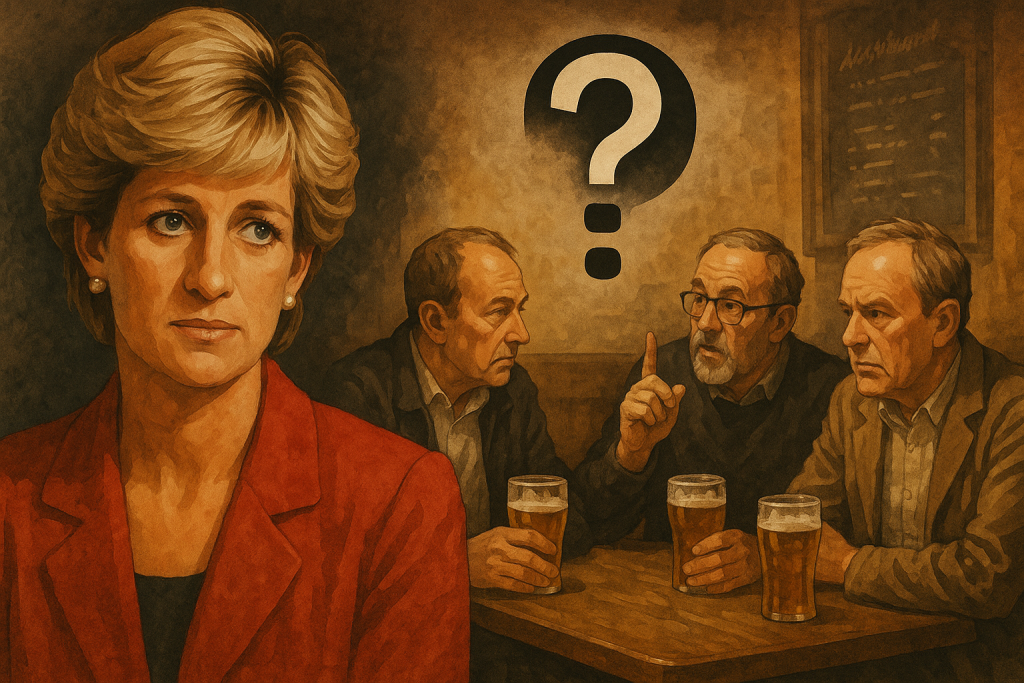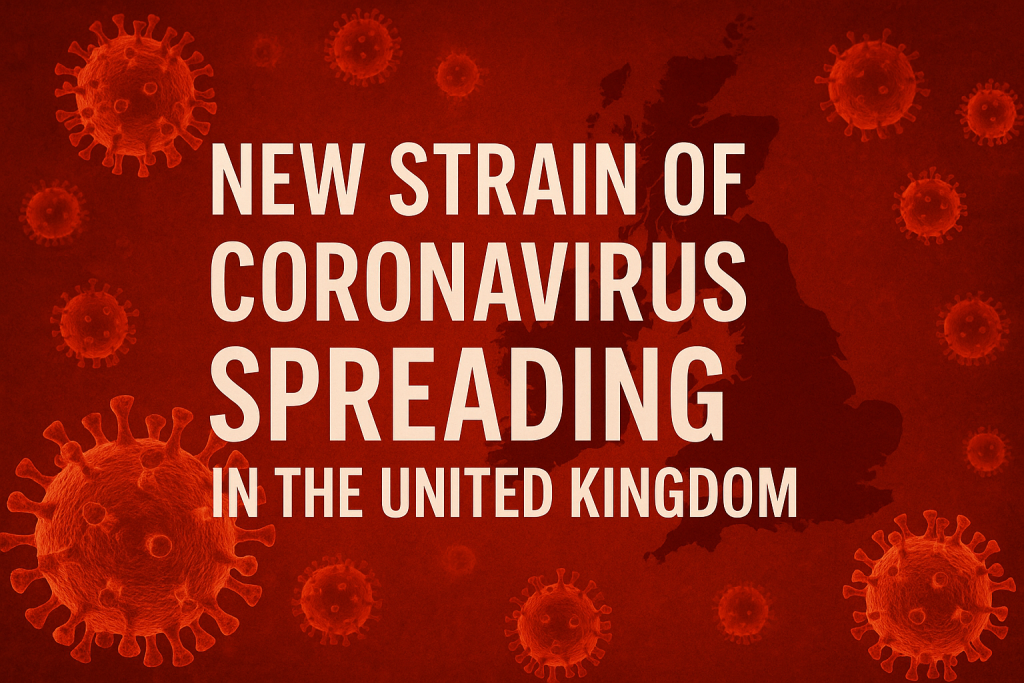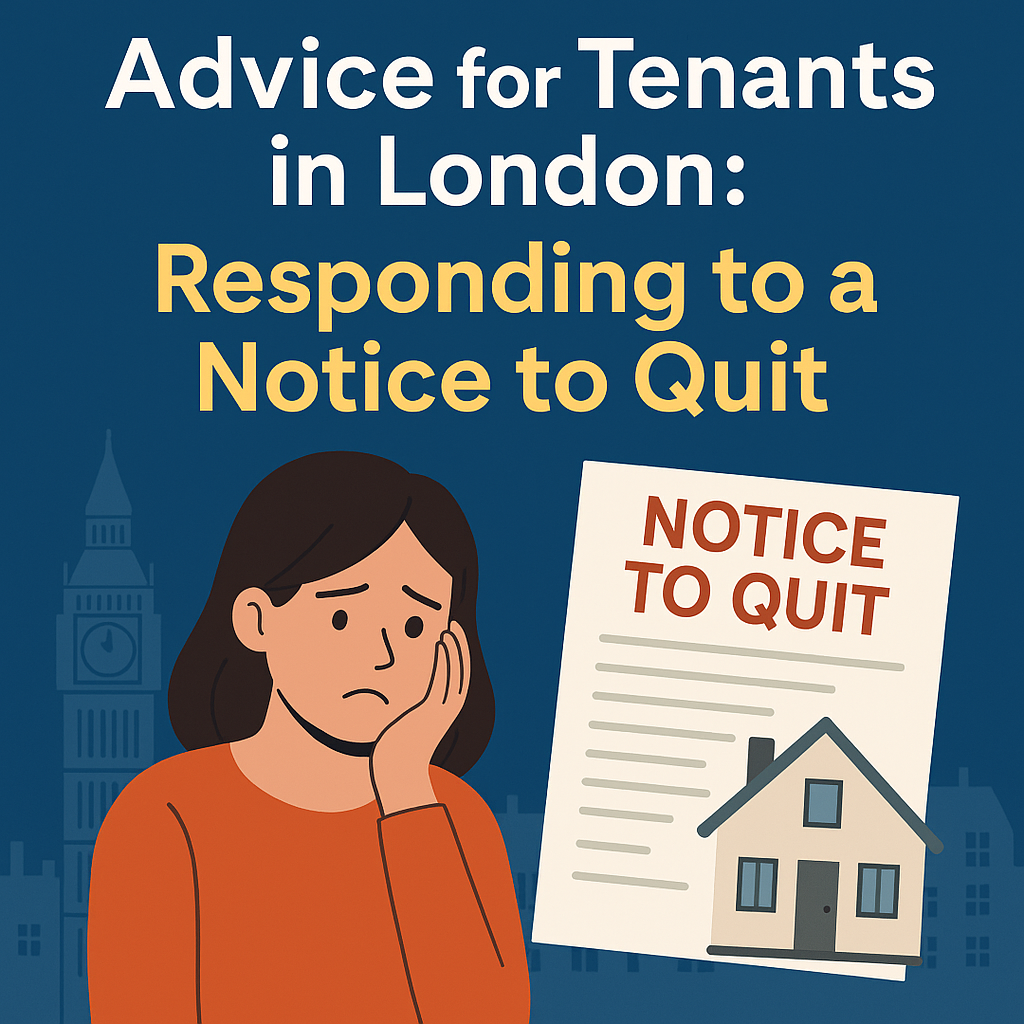…
Author:admin
【イギリス最大の国立公園「ケアンゴームズ国立公園」、キャンプファイヤー禁止の衝撃!】
…
英国を訪れる日本人への注意喚起:地方都市や小さな町でのヘイトクライム事例から学ぶ安全対策
…
イギリスから移民がいなくなった場合に考えられる影響
…
イギリスにおけるゲイ受容の歴史と、その社会的背景
…
イギリス人が未だに語り続けるダイアナ妃の急死——事故か、暗殺か、そして「飲みの席」での語り草となる理由
…
イギリスで “新型変異株” が拡大中:症状が「けっこうしんどい」という報告と最新の知見
…
ロンドンで日本人が安心して参加できる婚活パーティー事情
…
ロンドンで退去通知を受けたときの対応完全ガイド
…
イギリスで大ブームの兆し!日本発スイーツ&カルチャービジネス戦略
…