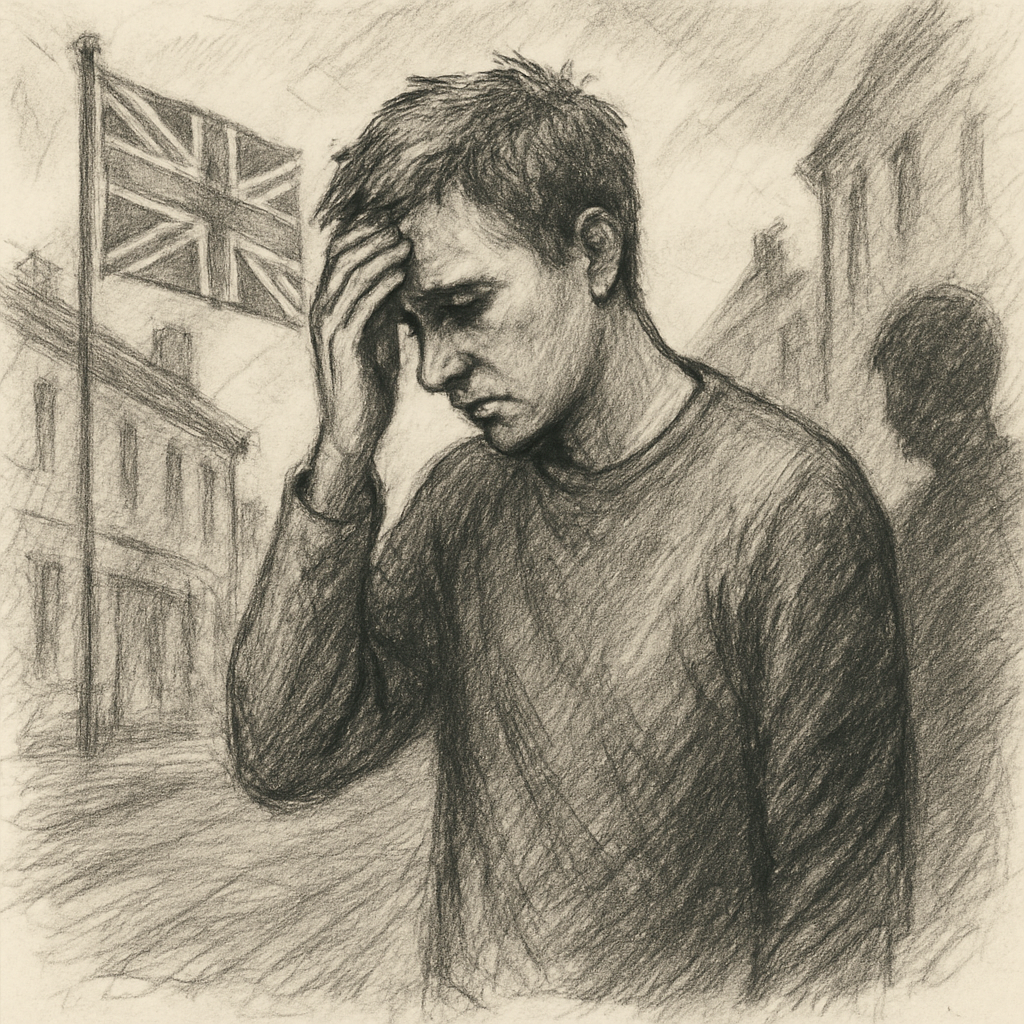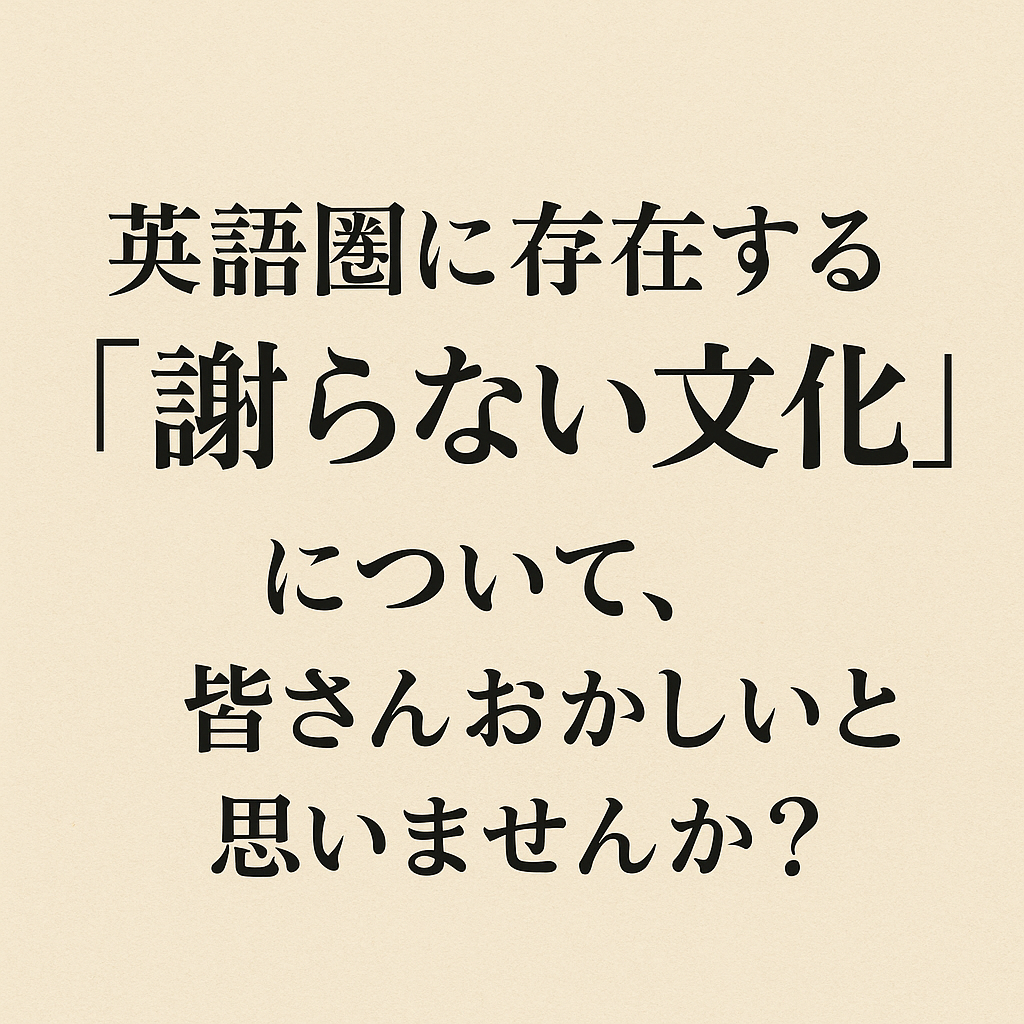…
Author:admin
刑務所の「安全設計」が日常になる社会 ― 便利さと危険性をどう教えるか
…
終わりなき暴力の連鎖を超えて─イスラエル・パレスチナ紛争から人類が学ぶべきこと
…
トランプ大統領と「戦争ビジネス」──イギリスから見た失望の視線
…
イギリスで移民として安全に暮らすには
…
英語圏に存在する「謝らない文化」について、皆さんおかしいと思いませんか?
…
イギリスで強まる反移民感情:地方に広がる国旗掲揚と社会の変化
…
世界で注目されるイギリス出身の有名人たち
…
イギリス経済、雇用環境に再び暗雲 ― 2021年以来の人員削減ペース
…
新浪剛史氏とCBDをめぐる誤解 ― アメリカと日本での規制状況
…