
変貌するハイストリートの風景
かつてイギリスの町の中心には、Marks & Spencer、WHSmith、Boots といった大手小売チェーンが軒を連ね、人々はショッピングバッグを手に賑わっていた。だが2020年代に入ると、その景色は劇的に変貌する。閉店した店舗のシャッターが並び、その空白を埋めるように立ち並ぶのは、なぜか同じような床屋(バーバーショップ)、水パイプを扱うカフェ、そして異国情緒を漂わせるペイストリーやスイーツ店。
表向きは「多文化共生の象徴」とも映るこの現象だが、背後には単純な需要と供給の問題では説明しきれない、不透明な資金の流れと裏社会の影がちらつく。なぜ、利益率の低いとされる業態が、家賃高騰に苦しむはずの商店街に出店できるのか――。
大手企業が撤退した理由
大手小売チェーンが商店街から姿を消した理由は、表面的には明快だ。
- オンライン市場の拡大
Amazonに代表されるEコマースの成長により、日用品や書籍、衣類といった商品をわざわざ街で買う必然性が薄れた。 - 高騰する賃料と固定費
ロンドンをはじめ都市部の商店街は地価上昇に伴い家賃が高騰。利益率の低下と固定費負担により撤退を余儀なくされた。 - ビジネスレート(事業税)の圧迫
イギリス特有の「Business Rates」は実店舗の運営に重くのしかかる。とりわけ中堅チェーンにとっては死活問題であった。
これらの要因が重なり、かつて活気にあふれたハイストリートは空き店舗だらけとなった。
床屋の急増という謎
ところが、その空白を埋めたのは、驚くほど大量の床屋だった。街を歩けば100メートルごとにバーバーの赤と白のポールが回転している。需要と供給のバランスを考えれば、明らかに過剰出店である。
床屋は低コストで開業できる。必要な設備は椅子と鏡、シェーバー程度。だが、その利益率は高くない。1人の顧客から得られる売上は数ポンドから十数ポンド。よほどの集客がなければ、月数千ポンドに及ぶ家賃を払い続けることは困難だ。
それでもなぜ生き残れるのか――。
表の顔と裏の顔
調査を進めると、床屋やスイーツ店が持つ「二つの顔」が浮かび上がる。
- 表の顔:地域住民にサービスを提供する小規模ビジネス。
- 裏の顔:資金洗浄(マネーロンダリング)の拠点。
床屋は現金決済が中心で、売上をごまかしやすい。例えば、実際には一日20人しか客が来ていなくても、帳簿上は50人来店したことにできる。その差額を「合法的な売上」として記録することで、裏資金を表の経済に混ぜ込むことが可能になる。
同様に、スイーツショップやペイストリー店もまた、製造原価が不透明で、仕入れ価格や販売数をごまかしやすい。菓子を10個売ったのか100個売ったのか、外部からは分からない。こうして裏資金を「甘い匂い」に紛れさせるのだ。
移民コミュニティと闇経済の結びつき
トルコ系やイラン系の店舗が目立つのは偶然ではない。イギリスにおける移民コミュニティは強い相互扶助ネットワークを持ち、同郷出身者同士で店舗の貸し借り、資金調達、人材派遣を行う。このネットワークの一部が、裏社会と密接につながっているとされる。
資金源は必ずしも違法薬物や武器取引に限らない。中東やバルカン半島を経由する送金システム(いわゆる「ハワラ」)や、不透明な輸入取引を通じて資金が流入する。こうした資金を浄化する装置として、商店街の床屋や菓子店が機能している。
行政と警察の限界
では、なぜ当局はこれを取り締まらないのか。理由は複数ある。
- 証拠の困難性
売上や仕入れを水増ししているかどうかを立証するのは容易ではない。 - 多文化共生政策との衝突
当局が特定の民族系コミュニティを狙い撃ちすると「人種差別」と批判されるリスクがある。 - 人手不足と優先順位
警察は暴力犯罪やテロ対策に追われ、経済犯罪の取り締まりにはリソースを割けない。
結果として、商店街は「法の網目」をかいくぐった裏資金の温床となっている。
地域経済への影響
この現象は単なる都市の景観変化にとどまらない。
- 健全な中小企業の排除
正当に商売するカフェや雑貨店は高額な家賃に耐えられず撤退。一方、裏資金に支えられた店舗は家賃を払い続けられるため、街全体の健全な競争環境が崩れる。 - 地域社会の空洞化
床屋が乱立しても地域の需要は満たされず、実質的には「客が入らない店」が増えるだけ。商店街は活気を失い、夜にはシャッター街と化す。 - 犯罪ネットワークの拡大
マネーロンダリングを通じて裏資金が正当化されることで、より大規模な犯罪活動が資金面で強化される。
暴露された実例
ある北ロンドンの商店街を取材したジャーナリストによれば、同じ通りに7軒の床屋が並び、どの店も閑古鳥が鳴いていたという。だが、店主は口を揃えて「順調だ」と語る。売上が見合わないはずの家賃をどうやって賄っているのか、明確な説明は一切ない。
さらに、イラン系ペイストリーショップでは、数十種類の菓子が常に山積みされているが、買い物客の姿はまばら。にもかかわらず、翌日も商品は新しく入れ替わっている。廃棄コストを考えれば、通常のビジネスとして成立するはずがない。
こうした矛盾は、「表の売上」と「裏の資金流入」の二重構造を示唆している。
闇に覆われた未来の商店街
イギリス政府は「Levelling Up(地域格差是正)」政策の一環として商店街再生を掲げているが、実態は裏資金の流入により歪められている。商店街は地域社会の象徴であり、人々が集い交流する場であるはずだ。だが現状では、赤と白のバーバーポールが立ち並び、甘い香りが漂う裏側に、資金洗浄と犯罪ネットワークの影が潜んでいる。
我々が目にする光景は、ただの床屋や菓子店の繁栄ではない。そこには「消費」という仮面を被った裏社会の経済活動が息づいている。
ハイストリートの未来を取り戻すには、行政と市民が共に現実を直視し、透明性のある仕組みを構築するしかないだろう。そうでなければ、商店街はますます「合法を装う非合法」の舞台と化し、地域の営みは静かに蝕まれていく――。
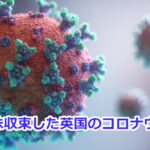







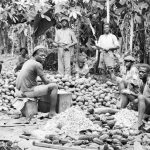

Comments