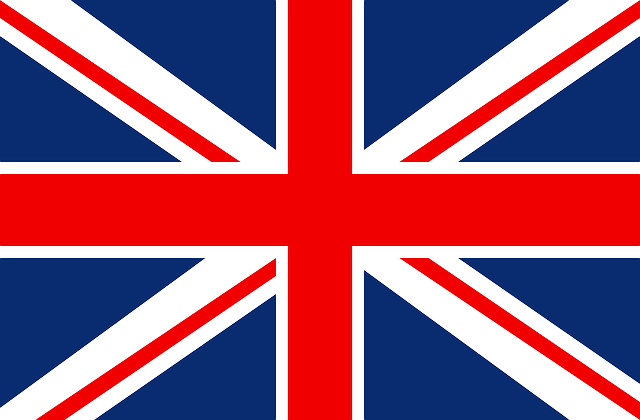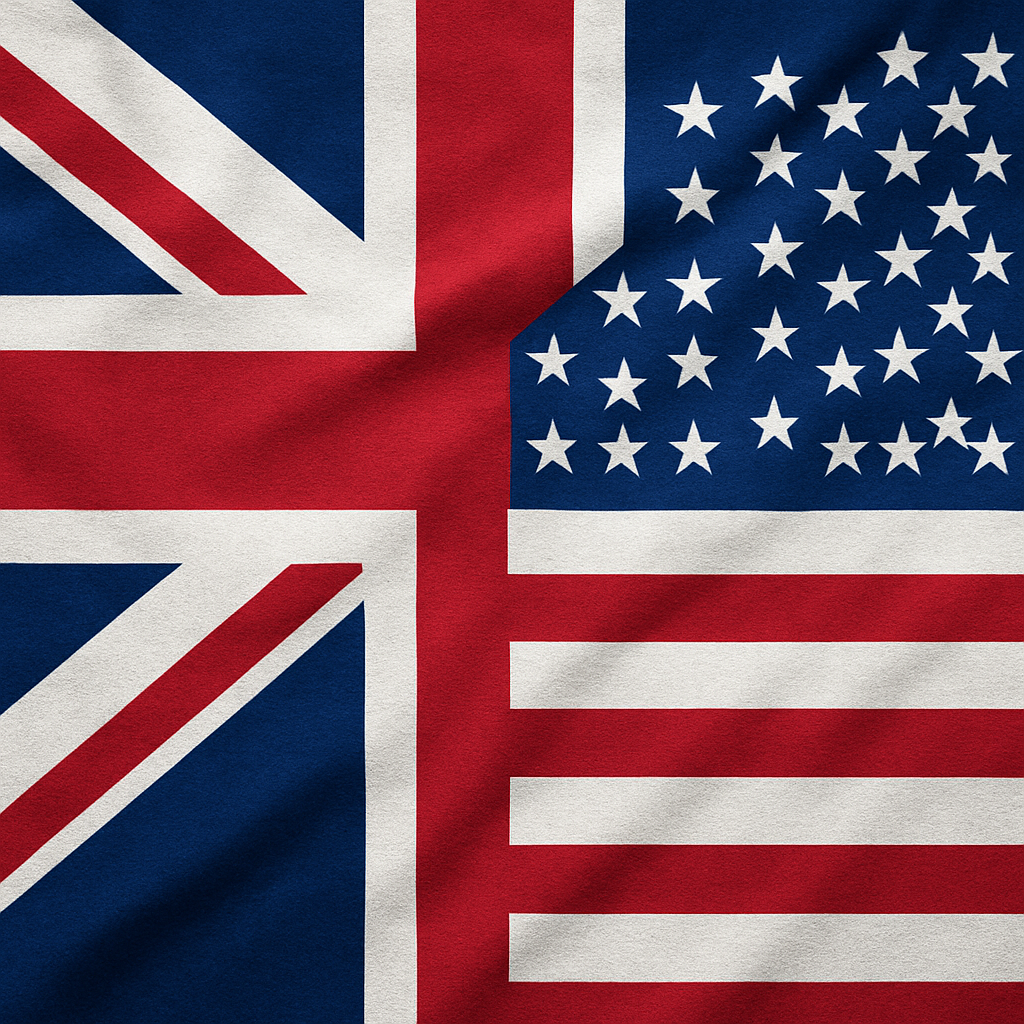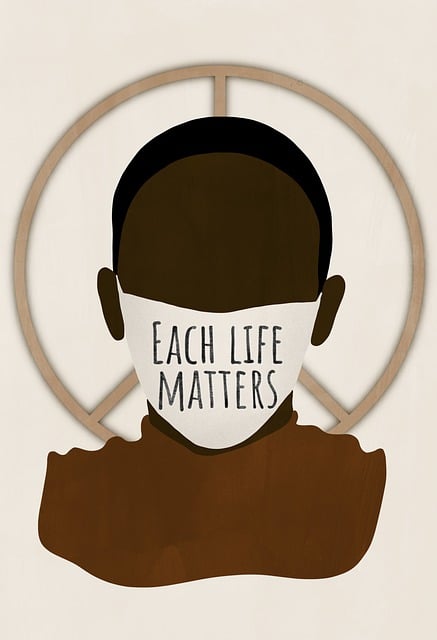…
政治
イギリス政府、またしても愚策?核兵器運搬機購入の裏に潜む「税金の無駄遣い」
…
加担か、中立か?
…
英国で承認された「余命6か月以内」の安楽死制度――医師の責任と植物状態患者の未来
…
HS2計画――未着工16年、誰のための超高速鉄道なのか
…
「歴史的」米英貿易協定の実態──華やかな発表の裏に潜む英国の課題と展望
…
なぜイギリスはEUに戻らないのか――移民問題と国家としての選択
…
イギリスの交通ルール大改革:巧妙な「罰金経済」が国民を締め上げる構造とは
…
リフォームUKと北東イングランドの政治地形――なぜ極右ポピュリズムがこの地に根を張るのか
…
アメリカを操る影の手?「イギリス支配説」の真相に迫る
…