
イギリスにおいて、健康意識の高まりとともにジムやフィットネスクラブへの関心は年々強まっています。2024年の統計によると、イギリス国内のジム会員数は約1,150万人に達しており、これは成人人口のおよそ16.9%を占める高水準となっています。ヨーロッパ諸国と比較してもこの数字は際立っており、イギリス国民の健康志向が高まっていることがうかがえます。
しかし、これだけ多くの人々がジムに入会しているにもかかわらず、実際にジムを定期的に利用している人は限られているのが現実です。Statistaの調査によれば、ジム会員の約18%は一度もジムを利用しておらず、約21%がほぼ毎日のようにジムに通っている一方で、残りの多数は週に数回程度の利用にとどまっているとされています。さらに、Smart Health Clubsの報告では、ジム会員の約50%が入会から6か月以内に退会しているという驚くべきデータもあります。
このギャップはなぜ生じるのでしょうか。その背景には、「参加すること自体が目的化している」現代社会の特異な価値観があるようです。
1. 健康志向の高まりと社会的プレッシャー
イギリスでは、国民の76%が「健康でありたい」と考えており、これはThe TimesやThe Guardianといった主要メディアでも頻繁に取り上げられるテーマです。健康を意識すること自体は非常に前向きな傾向ですが、その一方で、周囲からの無言のプレッシャーやSNSでの情報拡散により、「ジムに通っていることがステータス」となる現象が起きています。その結果として、実際に運動を続けるというよりも、「ジムに入会した」という事実だけで満足してしまう人が増えているのです。
2. モチベーションの維持の難しさ
ジム通いを続けるためには、継続的なモチベーションと日常生活とのバランスが不可欠です。しかしながら、仕事の多忙さ、家庭の事情、さらには予期せぬ体調不良など、通うことを妨げる要因は数多く存在します。加えて、ジム自体が初心者にとって敷居が高く、十分なサポート体制が整っていないケースもあり、「通わない理由」は数え切れないほど存在しています。
3. 「所有」や「所属」が満足感を生む現代的心理構造
現代人の心理構造には、「何かを所有している」あるいは「どこかに所属している」という事実だけで一定の満足感を得る傾向があります。これはジムだけでなく、他の会員制サービスにも共通して見られる現象です。
a. オンライン学習プラットフォーム
SkillshareやUdemy、Courseraなど、オンライン学習サービスに登録する人は年々増加しています。しかしながら、実際にコースを完了する人は少なく、多くは「登録しただけ」で満足してしまう傾向にあります。これは「学びたい」という意欲があっても、それを日常生活に組み込むのが難しいという現実を示しています。
b. サブスクリプション型サービス
SpotifyやNetflix、各種電子書籍サービスなど、月額料金を支払うことで利用できるサブスクリプション型のサービスもまた、「実際にはほとんど使っていない」現象がしばしば見られます。これは、自分が「文化的で洗練された生活を送っている」という錯覚に満足しているケースが多く、本来の利用目的とはかけ離れてしまっています。
4. 「参加することに意義がある」文化的背景
イギリスには、スポーツや教育、地域活動において「参加すること自体が意義を持つ」という文化的価値観が根付いています。これはポジティブな側面もある一方で、行動の実効性よりも形式的な参加に重きを置く傾向を助長しています。ジムへの入会も、「実際に成果を出す」より「健康的である自分を演出する」ことが目的化している場合が少なくありません。
5. 利用継続のための施策と今後の展望
このような現状を受けて、フィットネスクラブやジム業界は、入会者の定着率を高めるための施策を模索しています。例えば、以下のような取り組みが注目されています:
- 個別トレーニングプログラムの提供:会員の目標や体力レベルに応じたメニューの作成。
- モバイルアプリによる進捗管理:日々のトレーニング状況や成果を可視化し、達成感を促進。
- コミュニティ形成:会員同士の交流イベントやグループレッスンを通じた帰属意識の醸成。
- 心理的支援プログラム:継続的なモチベーションをサポートするメンタルトレーニングやカウンセリング。
また、業界全体としても、入会時のマーケティングに偏重するのではなく、「継続して通う価値」をどのように伝え、提供していくかが重要な課題となっています。
結論
イギリスにおけるジム会員の実態は、「入会して満足する人」と「継続的に通う人」の間に大きなギャップが存在することを浮き彫りにしています。これはジムに限らず、現代社会に広がる「形式的な参加」と「実質的な利用」との間の乖離を象徴しています。今後は、個々のライフスタイルに合った柔軟なサービス提供や、心理的支援を含む包括的なサポート体制の構築が求められるでしょう。
真に健康な社会を目指すためには、「参加すること」そのものから一歩進んで、「成果を実感し続けられる仕組み」への転換が不可欠です。






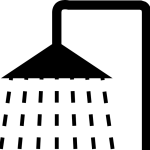



Comments