
2025年3月下旬、ミャンマーを襲った大規模な地震は、瞬く間に多くの命を奪い、数えきれないほどの人々の生活を一変させた。公式には少なくとも1700人が亡くなったとされているが、報道の自由が制限されたこの国において、正確な被害状況の全貌は見えてこない。通信インフラの崩壊や取材規制により、現地の声がなかなか外へと届かない中、世界各国のメディアは断片的な情報をもとに報道を行っている。
その中でも注目を集めたのが、イギリスの公共放送BBCによる報道である。BBCは、ミャンマー政府の情報統制と、それによる正確な死傷者数の不透明さを厳しく批判した。この姿勢は一見、報道機関として当然の態度にも思える。しかし、その語り口には「遠くの国の出来事を観察するだけ」といった冷淡さ、いわば“他人事”としての距離感がにじんでいた。
災害報道において、果たしてそれで良いのだろうか。問題は単に「被害者の正確な数がわからない」という点にとどまらない。本当に報道が果たすべき役割は、別のところにあるのではないか。
■ 本当に伝えるべきは「今、何が必要か」
被災地で最も必要とされているのは、数字ではなく支援だ。死者の数を正確に報じることも重要ではあるが、それ以上に必要なのは「今、現地で何が足りていないのか」「どうすれば次の命を救えるのか」といった実用的かつ緊急性の高い情報である。
災害が発生した直後には、初動対応として食料や水、医療品の確保と供給が急務となる。避難所の設営や衛生環境の整備、感染症の予防といった二次的な課題も同時に進行する。また、地震によるインフラの損傷は、救援活動そのものを困難にするため、道路や通信網の復旧支援も急がれる。
こうした一つひとつのニーズに即した支援を呼びかけ、あるいは具体的な支援方法を提示することこそ、報道機関の社会的責任のひとつであるはずだ。
■ 二次災害の危険性と報道の役割
地震直後には、多くの場合、余震や土砂崩れ、火災、ダムの決壊といった二次災害が発生する可能性が高い。これらは一次災害よりも人的・物的被害を拡大させるリスクを持っており、予測と対策が急務である。
報道機関は、政府や救援機関からの情報だけでなく、専門家の分析や現地の状況をふまえたリスク評価を行い、それを視聴者に伝える義務がある。情報の受け手は報道を通じて、現在起きていることだけでなく、今後起こり得ることへの備えを学ぶことができる。
それゆえに、単に被害の規模や死者数を伝えるだけでなく、今後の展開とそれに対する具体的な対応策を併せて報じることが必要だ。未来を見据えた報道は、人々の行動を変え、命を守る力を持っている。
■ 「安全地帯」からの視点がもたらす冷酷さ
私たちが気をつけなければならないのは、被災地から物理的・心理的に離れた場所にいることで、無意識のうちに“冷たい目線”を持ってしまうことである。数字を並べ、政府の対応を批評する。それ自体が悪いのではないが、それだけに終始してしまえば、報道はただの評論に過ぎなくなってしまう。
「1700人死亡」という数字の背後には、1700の人生と家族、希望と挫折、夢と絶望がある。一人ひとりの存在があったはずだ。それを忘れた報道は、無機質で人間味のない情報の羅列に過ぎず、視聴者の心には届かない。
記者たちには、数字の背後にある「顔」を描き出す努力が求められる。被災者の声に耳を傾け、写真や映像でその表情を届け、なぜその人がそこにいたのか、何を失ったのか、そして何を必要としているのかを伝えること。それが真の報道と言えるのではないだろうか。
■ ジャーナリズムが果たすべき役割とは
報道の目的は単なる情報の伝達ではなく、「社会に行動を促すこと」にある。人々に現状を理解させ、共感を喚起し、何かしらのアクションへとつなげること。ときには募金やボランティア参加、ときにはSNSでの情報拡散。そうした一人ひとりの小さな行動が、大きな支援の流れとなり、被災地の再建につながっていく。
そのためには、報道に共感の力が必要だ。「これは自分にも起こりうることだ」と感じさせるような伝え方、「他人事ではない」と思わせる構成と語り口。それこそが、報道が持つ本質的な力である。
■ 報道は変われるか──未来のジャーナリズムへ
現代のメディアは、かつてないほどのスピードで情報を伝えることができるようになった。同時に、情報過多とフェイクニュースの問題に直面してもいる。その中で、信頼できる報道機関としての在り方が問われている。
災害報道においても、単に「起きたことを正確に伝える」だけではなく、「何のために伝えるのか」を常に自問し続ける必要がある。被災地に寄り添い、未来を見据え、人々を行動へと導く。そんな報道が、今こそ求められている。
「いかに報じるか」ではなく、「なぜ報じるのか」。ジャーナリズムの原点に立ち返り、遠くの国の悲劇を“誰かの痛み”として感じ取る力。それこそが、メディアにとっての新たな使命なのではないだろうか。

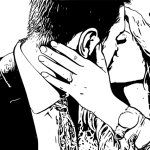







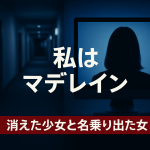
Comments