
2025年現在、イギリスでは物価上昇の勢いが止まらず、生活コストの高騰が長期化しています。 食料品やエネルギー、住宅費など、生活のあらゆる場面で値上がりが続き、 国民の間では「もう普通の暮らしが贅沢になった」との声も上がっています。 特に注目すべきは、イギリスのインフレ率がG7諸国の中で最も高い水準を維持している点です。 この記事では、なぜイギリスの物価上昇が鈍化しないのかを、経済構造・社会背景の両面から詳しく解説します。
G7で最も高いイギリスのインフレ率
英国国家統計局(ONS)の発表によると、2025年9月時点の消費者物価指数(CPI)は前年比6.8%上昇。 フランスやアメリカ、ドイツが3〜4%台に落ち着いている中で、 イギリスの物価上昇は依然として高止まりしています。 政府とイングランド銀行(BOE)は目標インフレ率を2%としていますが、その実現は依然として遠い状況です。
なぜイギリスだけ物価が下がらないのか?
イギリスの物価上昇が鈍化しない理由は、短期的な価格変動ではなく、経済構造そのものに根ざしています。 以下の3つの要因が、長期的なインフレ圧力を支えていると考えられます。
-
① エネルギーコストの高さと輸入依存
イギリスはエネルギー資源の多くを海外に依存しており、国際市場の価格変動が即座に国内物価へ反映されます。 ウクライナ情勢の影響でガス価格が上昇して以降、光熱費は一時より下がったものの依然高水準にあります。 エネルギー価格が安定しない限り、物価全体の抑制は難しいとみられています。 -
② 労働力不足による賃金上昇
ブレグジット以降、EU域内からの労働者が減少し、人手不足が常態化しています。 物流、医療、サービス業を中心に賃金が上昇し、これが企業のコスト増につながっています。 結果として、企業は価格転嫁を余儀なくされ、物価上昇を加速させているのです。 -
③ ポンド安と輸入コストの増加
為替市場でポンドが弱含む状態が続いており、輸入品の価格が上昇。 食料品や原材料、燃料といった生活・生産の基礎を支える品目が高止まりしています。 イギリスは輸入依存度が高いため、為替の影響を他国より強く受けやすい構造です。
金融政策だけでは抑えきれないインフレ
イングランド銀行はインフレを抑えるために利上げを続けていますが、 住宅ローン金利の上昇や企業投資の停滞など副作用も大きく、景気の減速を招いています。 金利政策は「需要の冷却」には効果があるものの、 イギリス経済が抱える供給面の問題、つまりコスト構造の歪みには十分な効果を発揮できていません。
生活コスト危機の深刻化
高インフレによって実質賃金は減少し、国民の多くが生活の質を下げざるを得ない状況です。 スーパーマーケットでは自社ブランド品やディスカウント商品の人気が高まり、 外食産業も価格高騰を受けて利用客が減少。 「生活コスト危機(Cost of Living Crisis)」は今もイギリス社会を覆う深刻な課題となっています。
今後の展望:構造改革がカギ
多くのエコノミストは、2026年以降にインフレ率が緩やかに低下すると予測しています。 しかし、賃金上昇圧力やエネルギーコストの高止まりを考慮すると、 物価の安定には構造的な経済改革が不可欠です。 労働市場の再設計、再生可能エネルギー投資、物流効率化など、 長期的な取り組みが問われています。
イギリスのインフレ問題は、単なる経済現象ではなく、社会構造の課題そのものを映し出しています。 G7で最も高いインフレ率という現実を前に、政府と国民がどのような選択をするかが、今後の安定を左右するでしょう。
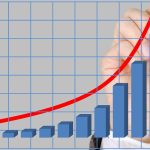





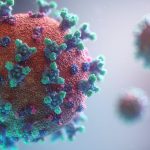



Comments