
「実家に帰省する」「実家暮らし」「実家の味」……日本では「実家」という言葉が日常的に使われ、特別な意味を持つ。家族が住み、思い出が蓄積されている場所。そこは人生の出発点であり、心の拠り所でもある。だが、イギリス人と話をしていると、こうした「実家」という概念が驚くほど薄いことに気づく。
なぜ、イギリス人には「実家」という感覚が乏しいのか?それは「引っ越し」という文化的・経済的な背景に大きく関係している。本稿では、イギリスにおける住宅事情、家族観、ライフスタイルの変化などを通して、「実家」という概念が根付きにくい理由を探っていく。
1. 「実家」という日本独特の概念
まず、「実家」という言葉を英語に訳すとしたら何になるのだろうか?辞書的には「parents’ house」や「family home」などが使われることが多いが、どれもニュアンスとしては「一時的に帰省する場所」や「両親が現在住んでいる家」を意味するにすぎない。「代々続く家」「帰る場所としての心の拠り所」という意味合いまでは含まれていない。
日本では、親から子へ、家と土地が受け継がれていく文化が強く、特に地方に行けば「○○家の本家」というような言い方も残っている。家系や地域との結びつきが強い社会構造が、「実家」という概念を根付かせている。だが、イギリスではこのような「家系としての家」という感覚が希薄である。
2. イギリス人はとにかくよく引っ越す
イギリス人のライフスタイルを語るうえで欠かせないのが、「頻繁な引っ越し」である。調査によれば、イギリス人は生涯で平均8回以上、引っ越しを経験すると言われている。子ども時代から大学進学、就職、結婚、転職、離婚、老後と、ライフステージごとに住む場所を変えるのが一般的なのだ。
特に顕著なのが大学進学のタイミングでの「家を出る」文化。日本では自宅から通える大学を選ぶ人も多いが、イギリスでは地方の大学へ進学し、親元を離れるのが普通。大学卒業後はさらに別の都市に就職し、友人や恋人とシェアハウスをしながら独立した生活を始める。
こうして、一度親元を離れたイギリス人が、再び「元の家に戻る」ことは稀であり、「帰省する場所」というより、「かつて住んでいた家の一つ」として認識されることが多い。
3. 不動産文化:買っては売る、資産としての家
イギリスでは不動産の売買が非常に活発で、人生の節目に家を「買い替える」文化が根付いている。例えば、若い夫婦がまず手頃な価格の「スターター・ホーム」を購入し、家族が増えるにしたがってより広い家に「ステップアップ」していく。その後、子どもが巣立てば、今度は管理が楽な「ダウンサイジング」をするという流れが一般的だ。
つまり、「親がずっと同じ家に住み続ける」というケースが非常に少ない。家は「資産」として捉えられ、タイミングを見て売買することが当たり前になっている。これでは「ずっと変わらない実家」という存在ができにくく、「帰省」という文化も根付きにくいのだ。
4. 家族の関係性とプライバシーの重視
イギリスでは家族同士であっても「個人の領域」を大切にする文化があり、それが住まい方にも影響を与えている。成人した子どもが親と同居するケースは稀で、「早く独立すること」が一種の美徳とされている。
親子関係は良好であっても、頻繁に会ったり、毎週電話をしたりする習慣はあまりない。家族との距離感が、物理的にも心理的にも日本より遠いことが多い。したがって、親が引っ越してしまえば「前の家=実家」という意識は希薄になり、新しい家も「両親の今の家」としてあくまで他人の家のように扱われる。
5. 地域共同体よりも個のライフスタイル
日本では、地域社会や近隣とのつながりが今なお重要視される傾向がある。特に地方では、近所付き合い、町内会、地元イベントなどが生活に根付いており、「帰省」はそれらの関係性を一時的に取り戻す行為でもある。
一方、イギリスでは個人主義が浸透しており、地域よりも「自分のキャリアやライフスタイル」に重きを置く。新しい仕事、新しい人間関係、新しい住環境を積極的に求めるため、「地元に帰る」という発想自体があまり存在しないのだ。
6. 例外としての貴族階級と伝統的邸宅
もっとも、イギリスにも「代々受け継がれる家」が存在しないわけではない。例えば、貴族や上流階級が所有する「マナーハウス(荘園)」や「エステート」はその典型だ。こうした邸宅は家名と密接に結びついており、家族の歴史や格式を象徴する存在でもある。
しかし、これらはごく一部の特権階級の話であり、一般市民にとっては現実離れした世界。イギリス社会全体としては、こうした「一つの家に長く住み続ける」文化は一般的ではない。
7. 「家」は物理的な場所から、心のつながりへ
イギリスでは、家族や大切な人と過ごす時間そのものに価値が置かれ、「どこにいるか」よりも「誰といるか」が重要視される傾向がある。たとえば、クリスマスやイースターに「家族と過ごす」ことは重視されるが、それがどこの家かはさほど問題ではない。親が住んでいる今の家でも、子どもの家でも、あるいはレンタルしたコテージでも構わないのだ。
この考え方は、「家=心のつながり」であり、「実家=建物」ではない、という価値観の反映でもある。
結論:イギリスにおける「実家」とは
以上のように、イギリス人にとって「実家」という言葉は、少なくとも日本人が持つような意味では存在しない。頻繁な引っ越し、資産としての住宅観、家族の独立性、個人主義的なライフスタイルなどが複合的に影響し、「帰るべき場所」としての家が形成されにくいのである。
とはいえ、それは「家族を大切にしていない」ことを意味するわけではない。むしろ、場所に縛られず、関係性を重視する柔軟な価値観がそこにはある。イギリス人の暮らし方を知ることは、日本人にとって「実家とは何か」を改めて問い直すきっかけにもなるのではないだろうか。








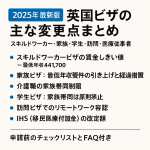

Comments