
新型コロナウイルス感染症が発生してから約4年が経過した今、パンデミックの急性期は多くの国で終息を迎えつつあります。しかし、その“後遺症”とも言える「Long COVID(ロング・コビッド、長期持続型COVID-19)」の問題は、いまだに深刻な形で多くの人々の生活と社会に影を落としています。
イングランドとスコットランドにおいては、2024年4月時点で約200万人がLong COVIDの症状を報告しています。そのうち、約150万人は日常生活に支障をきたすレベルの症状に悩まされており、慢性的な健康問題としての認識が社会的にも広がりつつあります。さらに驚くべきは、約71%の患者が1年以上、51%が2年以上、30%が3年以上も症状を抱え続けているという実態です(出典:Office for National Statistics)。
見えづらい「長期の苦しみ」
Long COVIDの症状は多岐にわたります。倦怠感、呼吸困難、脳の霧(ブレインフォグ)、記憶力や集中力の低下、睡眠障害、心拍数の異常、筋肉痛や関節痛など、多様な症状が組み合わさって現れます。中には、日常的な家事すら困難になり、社会活動から完全に離脱せざるを得ない人も少なくありません。
このような多様かつ個別的な症状のため、診断や支援の枠組みが曖昧であり、医療機関で「異常なし」とされるケースも多発しています。見た目には健康に見えることから、家族や職場からの理解を得ることができず、精神的な孤立感を深める人もいます。
貧困層に重くのしかかる負担
University of Oxfordによる研究では、社会経済的に恵まれない地域ほど、Long COVIDの発症率が高いことが明らかになっています。具体的には、最も貧困な層での発症率は3.2%、最も裕福な層では1.5%と、およそ2倍の開きがあります。
この数字は、医療へのアクセス、生活環境、栄養状態、基礎疾患の有無、そして職業的な感染リスク(サービス業やケアワーカーなど)といった複合的要因を反映しています。また、ジェンダーの観点では女性の方がやや高い割合で影響を受けているというデータも出ています。
つまり、Long COVIDは「平等に広がる病気」ではなく、すでに不利な立場にいる人々をさらに追い込む性質を持っています。これは、単なる医療問題ではなく、社会的公正の問題でもあるのです。
雇用と経済への重大なインパクト
健康問題が日常生活だけでなく、経済的な側面にも大きな影響を及ぼしている点は見逃せません。イギリスでは、Long COVIDを理由に約11万人の労働者が労働市場から離脱していると報告されています。これにより、年間約15億ポンド(約2,850億円)の経済損失が発生していると試算されています(出典:Institute for Fiscal Studies)。
さらに、労働組合会議(TUC)とLong Covid Supportによる調査では、Long COVIDを抱える労働者の7人に1人(14%)が職を失ったと回答しており、3分の2以上が職場で差別的扱いを受けたと述べています(出典:HR Magazine)。これは、企業側が症状の理解不足や柔軟な勤務体制への対応ができていないことを示唆しています。
職場での不当解雇、昇進停止、配置転換など、表立った差別ではなくても、見えにくい「サイレントな排除」が横行している状況に、多くの患者が苦しんでいます。
政府の対応と課題
イギリス政府はLong COVID問題に対して一定の対策を打ち出しています。2024年3月には、Long COVIDの治療・支援のために3億1400万ポンドの予算を投じ、100以上の専門クリニックをイングランド全土に設置することを決定しました(出典:House of Commons Library)。
このような体制整備は一定の前進ではありますが、患者団体や専門家は、さらなる対策の必要性を訴えています。特に以下のような点が課題として指摘されています:
- Long COVIDを正式に「障害」として認定すること
- 職場における合理的配慮の義務化
- 在宅勤務や時短勤務など、柔軟な働き方の法的保証
- 再感染防止のための職場での感染対策強化
- 慢性的な症状に対応できる医療人材の育成と配置
政府による政策はまだ「治療と診断」に焦点が当たっており、「雇用」「福祉」「教育」といった社会全体の構造にまで踏み込めていないという声も多くあります。
Long COVIDが突きつける“社会の健康”
パンデミックは単なる感染症の拡大ではありません。それは医療体制の弱さ、格差社会の現実、職場の柔軟性の欠如、そして社会的弱者の置き去りといった“既存の問題”を一気に顕在化させる出来事でした。
Long COVIDの影響を受けている人々は、単に「治らない症状」に苦しむだけでなく、社会からの理解と支援が乏しいという「二重の苦しみ」にさらされています。その一方で、彼らの声がようやくメディアや議会でも取り上げられはじめ、制度の変革を促す原動力にもなりつつあります。
今後に向けた提言
Long COVIDの問題に対して、今後求められる対応は以下のようにまとめられます:
- 包括的な医療・福祉連携体制の構築:プライマリケア、リハビリ、精神保健サービスなどを横断的に統合した支援が必要です。
- 雇用における差別防止と支援制度の充実:障害者雇用の制度を応用するなど、労働者としての権利を保障する仕組みが求められます。
- 教育機関や家庭への支援拡充:若年層のLong COVIDも増加しており、学校や家庭でのサポート体制も整備が急務です。
- エビデンスに基づく研究推進と情報発信:疫学的調査や治療法の研究に継続的な資金投入が必要です。
結論:見えない「第2のパンデミック」にどう立ち向かうか
Long COVIDは、感染症が収束してもなお続く“もうひとつのパンデミック”です。それは個人の健康だけでなく、家族の生活、社会の福祉、国家の経済に至るまで、あらゆる面にじわじわと影響を及ぼしています。
この問題を軽視せず、個々の患者の声に耳を傾け、制度と意識の両面から「持続可能な共生社会」を築いていくことが、私たちに課せられた次なる課題です。






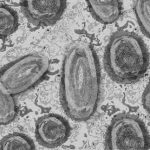



Comments