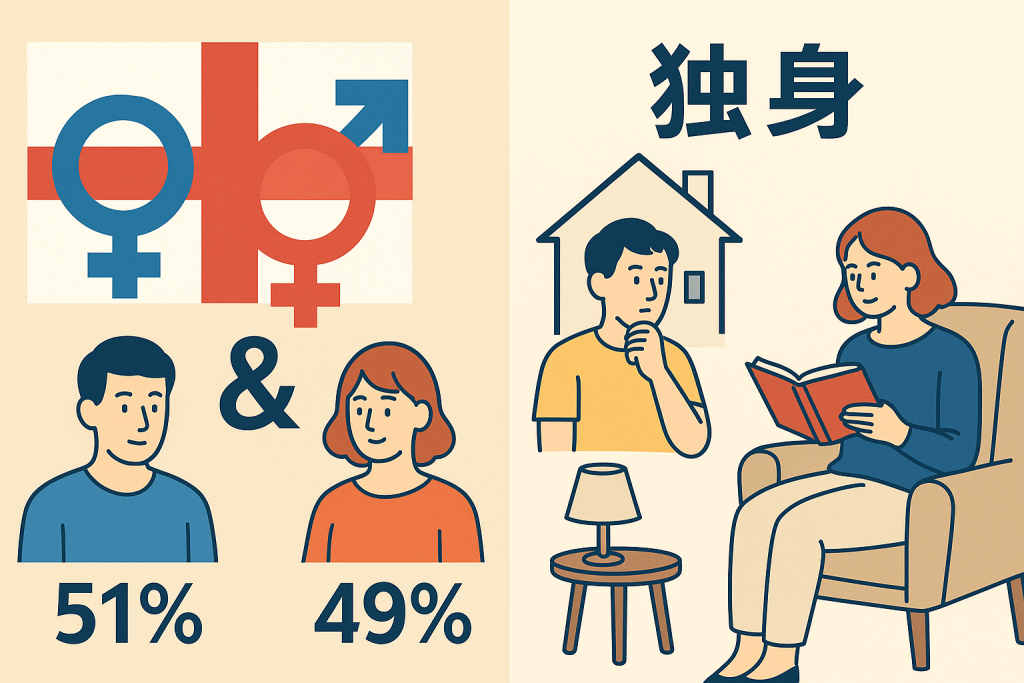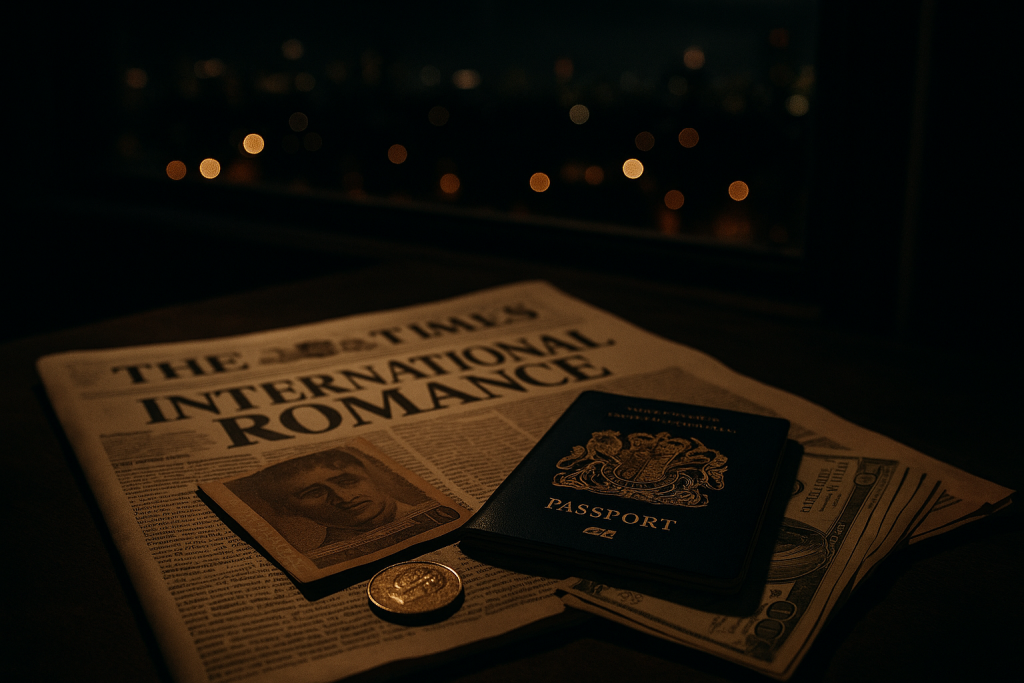…
結婚
イギリスでは男性と女性どちらが多い?
…
イギリス人でも離婚は多い?──「生まれ変わっても同じ相手を選ぶ」カップルの意外な回答と日本との違い
…
イギリス人男性とアジア人女性、そして日本人男性と南アジア婚──“愛と経済”が交差する国際結婚の現実
…
イギリスの婚姻率・出生率・結婚する平均年齢【2025年最新】ONS統計で見るイギリスの結婚事情
…
ロンドンで日本人が安心して参加できる婚活パーティー事情
…
イギリス配偶者ビザ取得の手順ガイド 2025年版
…
「慰謝料クイーン」は現代の魔女か、それとも制度の申し子か──イギリス離婚制度の裏側に迫る
…
イギリス人と結婚したら生活はこう変わる 〜紅茶とユーモアに満ちた日々〜
…
イギリスの祝い事文化に見る「主役が損をする」システム:誕生日と結婚式の舞台裏
…