
はじめに
現代社会において「学歴」はいまだに大きな影響力を持つ要素のひとつである。特に高等教育への進学は、キャリア形成や所得、社会的地位に直結することが多い。しかし、すべての人が大学に進学するわけではないし、大学に行かない人生にも多様な選択肢が存在する。本稿では、イギリスの大学進学率、大学に行かない人々の進路、そして学歴が将来に与える影響について検討する。
イギリスの大学進学率
イギリスでは、高等教育への進学率は年々上昇傾向にある。政府統計(UCASなど)によれば、2023年時点での大学進学率(18歳人口に対する高等教育機関への進学者の割合)は約38〜40%である。ただし、地域、性別、社会経済的背景によってばらつきがある。例えば、ロンドンなどの都市部では進学率が高く、北部地方やスコットランドの一部ではやや低めである。
また、大学進学者の多くはAレベル(日本で言う高校卒業資格)を取得しており、進学先は大学(University)やカレッジ(College)など多岐にわたる。オックスフォード大学やケンブリッジ大学に代表されるトップ校への進学は依然として高い競争率を誇る。
大学に行かない人の選択肢
職業訓練(Apprenticeships)
イギリスでは大学以外にも多様な進路が存在する。最も代表的なのが「アプレンティスシップ(Apprenticeship)」と呼ばれる職業訓練制度である。これは企業に勤めながらスキルを学び、一定の認定資格を取得できる制度であり、大学に行かずに実務的なキャリアをスタートできる道として注目されている。
近年では、IT、会計、エンジニアリング、ヘルスケアなど多様な業界で高レベルのアプレンティスシップが用意されており、大学卒業と同等、あるいはそれ以上の給与水準を得るケースもある。
専門学校や短期教育機関
さらに、専門分野に特化した教育機関(Further Education Colleges)も大学以外の選択肢となる。例えば、美容、料理、建築、デザイン、映像制作などの分野で、即戦力としての技能を習得するためのコースが充実している。
就労とキャリア形成
一部の若者は、18歳で学校を卒業した後すぐに就職し、現場経験を積みながらキャリアを形成する道を選ぶ。販売職、接客業、運輸、建設業、介護など、エントリーレベルの職種が多く存在する。また、働きながら夜間や通信で資格取得を目指す人も多い。
肉体労働=大学に行かない人の道か?
しばしば誤解されがちだが、大学に行かない=肉体労働という構図は必ずしも正しくない。確かに建設業や製造業など、体力を要する仕事もあるが、これらも高度なスキルや資格を必要とする場合が多い。
また、IT業界やデジタルマーケティングなど、一見すると文系的な職業でも、大学を経由せずに独学やブートキャンプなどでスキルを身につけて活躍する人も増えている。YouTuber、ゲーム開発者、デザイナーなど、新しい産業構造の中で生まれた職業は、学歴よりも成果物や実力が重視される。
学歴が将来に与える影響
所得と雇用の安定性
統計的には、大学卒業者の平均所得は高卒者やそれ以下の学歴の人よりも高い傾向がある。イギリスのONS(国家統計局)のデータによれば、大学卒業者の平均年収は約30,000〜35,000ポンドであるのに対し、大学に行かなかった人の平均年収は20,000〜25,000ポンド程度である。
また、大学卒業者の失業率は低く、景気の悪化時にも比較的職を失いにくいという傾向が見られる。これらの要素は、住宅ローンの審査、家庭形成、将来の老後資金など、人生全般にわたる安定性に影響する。
キャリアの選択肢
大学進学は、医師、弁護士、研究者、公務員など、学歴が求められる職業への道を開く。また、多くの企業では、昇進や専門職への異動にあたり学士号や修士号が要件となることもある。
とはいえ、近年ではGoogleやAppleといった大企業が「学位不要」の方針を示すなど、実力主義へのシフトも進んでいる。特にテック系やスタートアップ界隈では、学歴よりも実績やスキルが評価されやすい。
社会的ネットワーク
大学進学には、知識の習得や資格の取得だけでなく、同世代との人脈形成という側面もある。これは将来的なキャリア支援、起業の仲間、情報交換の基盤となる。
一方で、大学に行かずに業界内での人脈を築き、現場での信頼を積み重ねることでキャリアを発展させるケースもあり、どちらが優れているかは一概には言えない。
おわりに
イギリスにおける大学進学率はおよそ40%程度であり、多くの若者が高等教育を通じて将来の可能性を広げようとしている。しかし、大学に行かない選択も決して劣った道ではなく、多様なキャリアが用意されている。
学歴は確かに一定の影響力を持つが、それがすべてを決定づけるわけではない。むしろ、個々の適性や目標に応じた進路選択こそが、充実した人生を築く鍵となる。社会全体が「学歴以外の価値」に目を向け、多様な成功のかたちを認め合うことが、これからの教育と雇用のあり方にとって重要である。






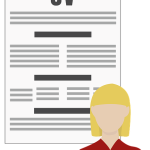



Comments