
はじめに
YouTubeの普及により、誰もが簡単に動画を投稿し、世界中に発信できる時代となった。クリエイティブなコンテンツで人々を魅了するユーチューバーがいる一方で、視聴回数と注目を求めて常軌を逸した行動をとる「迷惑系ユーチューバー」も目立つようになってきた。この現象は日本に限った話ではない。実はイギリスでも同様の問題が深刻化しており、若者たちによる公共の場での違法行為や社会的ルールの逸脱が波紋を広げている。
イギリスにおける迷惑系ユーチューバーの実態
イギリスでは、都市部を中心に迷惑系ユーチューバーが問題視されている。彼らの多くは10代後半から20代前半の若者で、再生回数やSNSでのフォロワー数を稼ぐことを目的として、過激で違法な行動に出る傾向がある。
たとえば、ロンドンを拠点に活動するあるユーチューバーは、電車の屋根に無断で登って移動するというスタントを繰り返し、交通機関を混乱させた。また、別の若者グループは、スーパーや飲食店で店員にいたずらを仕掛けたり、商品を勝手に使用したりする動画をアップロードして炎上した。
こうした迷惑行為は、時に命の危険すら伴う。高層ビルの縁を歩いたり、走行中のバスの屋根に飛び乗ったりといった「パルクール」や「アーバン・エクスプロレーション(都市探検)」を模倣する動画も多く見られ、若者の模倣被害も報告されている。
事例紹介:バカげた行為が招く法的措置
イギリスの有名な迷惑系ユーチューバーの一人に、”Mizzy”ことバカリ・ブロンツィ(Bacari-Bronze O’Garro)がいる。彼はロンドン北部で、他人の家に無断で侵入する、通行人の自転車を勝手に乗り回すといった動画を投稿し、大きな非難を浴びた。最終的には複数の罪で逮捕され、SNS活動に関する禁止命令が出された。
このような事例は、法的な対応を強化する一因となっている。2023年には、公共秩序法の下での刑罰が強化され、SNSを通じた迷惑行為にも罰則が及ぶようになった。ロンドン警視庁も「オンラインとオフラインの境界はない」として、インターネット上の行為も現実社会と同様に取り締まる方針を明確にした。
なぜ迷惑系ユーチューバーが増えるのか?
このような迷惑行為の背景には、いくつかの社会的要因がある。まず第一に、アルゴリズムによって「過激なコンテンツほどバズりやすい」という現実がある。YouTubeやTikTokのようなプラットフォームでは、センセーショナルな映像がアルゴリズムによって拡散されやすく、刺激的な内容ほど視聴回数を稼げる傾向にある。
また、若者たちが自己表現の場を求める中で、手っ取り早く「有名になる」手段として迷惑行為を選ぶケースも多い。教育や家庭でのモラル教育の不十分さ、経済的な格差、社会的な孤立感といった複合的な問題も彼らの行動に影響している。
社会とプラットフォームの対応
このような問題に対し、社会全体としてどのように対応すべきかが問われている。まず、プラットフォーム側の責任が大きい。YouTubeやTikTokでは、違反行為に対する規約を強化し、問題のある動画を削除する体制を整えてはいるが、イタチごっこの様相を呈している。
さらに、広告収入によってこうしたユーチューバーが利益を得ている現状にも批判が集まっている。広告主やスポンサー企業が、コンテンツの健全性をより厳格に審査し、迷惑系ユーチューバーへの支援を打ち切る動きも出てきている。
一方で、教育現場でのメディアリテラシー教育の重要性も増している。子どもたちがインターネットの世界でどのような情報に触れているかを正しく理解し、自らの行動が他者や社会に与える影響を考える力を養うことが求められている。
結論:自由と責任のバランスをどう取るか
迷惑系ユーチューバーの問題は、単なる「若気の至り」では済まされない社会的課題である。表現の自由は重要だが、それには責任が伴う。注目を集めるために他者を傷つけたり、公共の安全を脅かす行為は決して容認されるべきではない。
イギリスでも、日本と同様に、社会全体での意識改革と法整備、そして教育の強化が急務である。私たちは今、ネット時代にふさわしい新たな倫理観と法の在り方を模索する転換点に立たされているのかもしれない。



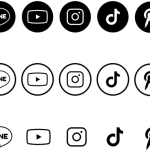

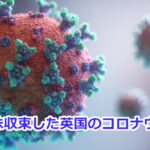




Comments