
はじめに:病名が氾濫する社会
近年、イギリスでは子どもたちや若者に対する発達障害の診断が急増している。ADHD(注意欠如・多動症)、OCD(強迫性障害)、ASD(自閉スペクトラム症)といった名称は、もはや医療専門家の間だけでなく、家庭、学校、SNS上にまで広く浸透している。「うちの子、ADHDなのよ」と親が語り、「僕、OCDっぽいから」と学生が言う――こうした表現は今や日常的なものとなった。
だが、本当にこの社会的現象は歓迎されるべきものなのだろうか?
あるいは、それは“理解”という仮面を被った、もうひとつの“抑圧”なのではないか?
ラベリングという文化:イギリスの特異性
イギリス社会には、何事にも明確な「枠組み」や「カテゴリー」を与えようとする傾向が強い。階級制度が根強く残っている点からも明らかなように、この国は人々を何らかのラベルで分類することに安心感を覚える文化を持っている。そこにおいて、「診断名」は一種の文化的記号となり、本人の内面を語る前に、そのラベルが人間像を先取りしてしまう。
たとえば学校で問題行動が見られる子どもがいた場合、教師や親はすぐに「ADHDかもしれない」と疑う。以前なら「落ち着きがない」「いたずら好き」などと表現されていた性質も、今では医学的な診断名に置き換えられる。そしてその瞬間から、その子どもは「ADHDの子」として、特別な視線にさらされることになる。
このような過程は、一見すると支援の第一歩にも思える。しかし実際には、診断が社会的ラベリングの一種として機能し、本人の可能性や多様な性格のあり方を狭めてしまう危険性を孕んでいる。
親の“都合”とラベル
とりわけ注目したいのは、ADHDの診断がなされるプロセスにおいて、親の姿勢がどれだけ影響を及ぼしているかという点である。
例えば、子どもが学校で集中力を欠いている、忘れ物が多い、騒がしい――そうした行動に悩む親が、「なぜうちの子は普通じゃないのか」と感じ始める。そして、その疑問への“納得の答え”としてADHDという診断名が浮上する。親は「うちの子はADHDだから仕方ない」と考えることで、ある意味で自らの育児の不全感から解放される。
だが、そのとき考慮されているのは「親自身の安心」であって、「子どもがその後どう扱われるか」という視点ではないことが多い。ADHDの診断を受けたことで、子どもは支援が受けられるかもしれないが、同時に「病気を持つ者」「特別な配慮が必要な存在」として見なされるようになる。
これは、子どもの自己認識に大きな影響を与える可能性がある。とくに幼少期において、「自分は他の子とは違う」「問題がある」と認識してしまうことは、その後の自信形成や社会性の発達に暗い影を落とす。親が「理解者」として振る舞っているつもりでも、無意識のうちに“障害者としての子ども”というイメージを固定化してしまっている場合もあるのだ。
診断=免罪符?
もう一つの問題は、「診断」が行動の正当化に使われることがある点だ。
「ADHDだから宿題ができない」「OCDだから手を洗いすぎる」――このような言い訳が通用する状況では、本人の努力や工夫が軽視される。むしろ診断名があることで、「頑張らなくてもいい」という空気が形成され、本人の成長機会が奪われてしまう。
また、学校や家庭においても、「この子はADHDだから仕方ない」と諦めのような態度が生まれやすい。これは支援とは真逆の態度である。むしろ、診断を通して子どもを“定義”し、“制限”してしまっている。
では、診断は不要なのか?
もちろん、すべての診断が悪であるとは言わない。実際、ADHDやOCDに苦しむ子どもたちが適切な診断を受け、薬物療法やカウンセリングなどの支援を得ることで生活の質が向上する例も数多い。
問題なのは、診断の乱用と、それを支える社会の態度である。少しでも“普通”から外れた行動があると、「病気」や「障害」のラベルを貼って安心しようとする文化。これは、子どもの個性を尊重するのではなく、むしろ規格化・統制しようとする動きである。
「わからなさ」に耐える力
イギリス社会が抱える根本的な問題は、「わからなさ」に耐えられないことだと筆者は感じる。
落ち着きがない子がいたとき、「なぜなのか」「どうしてこの子だけこうなのか」と即座に原因を探りたがる。そして、その“わからなさ”を埋める答えとして、「ADHDです」という医学的な言葉が提示される。
しかし、子どもの成長や行動というものは、必ずしも因果関係だけで割り切れるものではない。時に“説明できないもの”として、ただ静かに見守るという態度が必要ではないか。ラベルを貼ることで安心するよりも、「わからないまま」関わり続ける勇気こそ、真の理解に繋がるのではないか。
終わりに:ラベルの向こうにいる「ひとりの人間」を見る
診断名があることで救われる人がいるのも事実。だが、その反面で、ラベルが人間性を覆い隠し、無意識の差別や分断を生み出している場面も多い。
イギリスの教育現場、家庭、メディア、SNS――どこもが「診断」に飛びつきすぎてはいないか?
ADHDであることよりも、「いま、この子が何に困っていて、どんな風に過ごしているのか」にこそ、もっと目を向けるべきではないだろうか。
ラベルを貼ることは簡単だ。しかし、そのラベルの向こうにいる「ひとりの子ども」と真摯に向き合うことの方が、ずっと難しく、そして尊い。






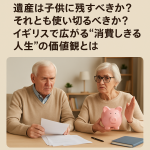



Comments