
もし、あなたがイギリスの街角を歩いていたとしましょう。
スーパーマーケットの中で、子どもが走り回って棚にぶつかりそうになっても、誰も注意しません。レストランで子どもが大声を上げても、親は笑って見守るばかり──そんな光景に戸惑いを覚える日本人は少なくありません。
「この子、ちゃんと叱らなくて大丈夫なの…?」
そう思ったことのある方も、きっといるはずです。
自由を重んじるイギリスの子育て文化
イギリスでは、子どもは生まれた瞬間から「ひとりの人格」として尊重されます。泣きたいときに泣き、怒りたいときに怒る。それは「感情の自由な表現」として、大人が守るべき権利でもあるのです。
一方で、日本では公共の場で子どもがはしゃいだり大きな声を出したりすれば、すかさず親が「静かにしなさい」と声をかけるのが一般的です。これは、「周囲に迷惑をかけないように」という、社会との調和を大切にする文化からくる自然な反応でもあります。
文化的な背景の違い──それは否定すべきものではありません。けれども、この“自由”が“放任”にすり替わってしまったとき、何が起きるのでしょうか?
少年犯罪が問いかける「子どもの自由」の行き先
イギリスでは、年齢が一桁台の子どもたちによる重大犯罪が時折報じられ、社会を揺るがします。最も象徴的な事件として記憶に刻まれているのが、1993年の「ジェームズ・バルジャー事件」です。当時10歳の少年2人が、2歳の男の子を誘拐し、残虐な方法で命を奪ったこの事件は、世界中に衝撃を与えました。
あれから30年以上が経ちましたが、依然として11〜13歳の少年によるナイフ犯罪や暴力事件は後を絶ちません。もちろん、すべての原因が“叱らない育児”にあるわけではありません。家庭の貧困、教育機会の格差、親子関係の希薄さ──社会的要因が複雑に絡み合っています。
けれど、根底にはやはり「子どもに制御のきかない“自由”を与えすぎてしまった」という社会全体の葛藤が見え隠れしているのです。
子どもは「自由」によって伸びる。でも、「しつけ」によって守られる。
自由は、確かに子どもの個性や創造力を伸ばします。しかし同時に、それを支える「しつけ」や「境界線」がなければ、子どもは社会という大海の中で舵を失い、漂ってしまうことがあります。
親が「これはいけない」と示すことは、決して子どもの心を傷つけることではありません。むしろ、「ルールがあること」「人に優しくすること」「誰かの気持ちを考えること」は、子どもが安心して世界と関われる“支え”になるのです。
そしてそれは、親だけが背負うべき責任ではありません。家庭、学校、地域社会、行政、そして国家──「子どもを育てる」という営みは、社会全体で支え合ってこそ、健全に機能するものです。
いま、親として私たちができること
子どもが「自由に育つ」ことと、「他者を思いやれる人間に育つ」ことは、決して矛盾するものではありません。むしろその両方をバランスよく教えることこそ、現代の親に求められている最大の使命ではないでしょうか。
叱ることにためらいを感じたとき、どうか思い出してください。
それは「自由を奪うこと」ではなく、
「子どもがこの世界で幸せに生きていくための道しるべ」を示す行為なのだということを。
イギリスの子育て文化に学びつつも、日本の良さも見失わずに。
「自由」と「しつけ」を両立させる子育てを、私たちは模索し続けていいのです。

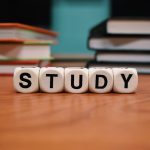








Comments