
はじめに
お小遣いという言葉を聞いて、日本の多くの人が思い浮かべるのは、親から毎月または毎週決まった金額を手渡される「現金」のイメージではないだろうか。小学生になったら月に500円、中学生で1000円から3000円、高校生でアルバイトを始めるまで段階的に増えていくのが一般的な日本のスタイルである。
では、イギリスではどうなのだろうか。子どもたちはそもそも「お小遣い」という概念を持っているのか?また、どのように金銭感覚を学んでいくのだろうか?
本記事では、イギリスの子どもたちがもらうお小遣いの実態、その文化的背景、家庭内での教育的な役割、さらには近年のデジタル化の影響にまで踏み込み、日本との違いを考察しながら紹介する。
1. イギリスにおける「お小遣い」という概念
お小遣いは「ポケットマネー (pocket money)」
イギリスでは、お小遣いのことを「pocket money(ポケットマネー)」と呼ぶ。これは日本のお小遣いに非常に近い概念であり、子どもが自分の裁量で使うことのできるお金のことを指す。親が定期的に渡すこともあれば、不定期に何かのお手伝いや好成績へのご褒美として渡されることもある。
概念としての位置づけ
イギリスでは、子どもにポケットマネーを与えることは「金銭教育」の一環として一般的に受け入れられている。使い道を自分で考えさせることで、金銭感覚、自己管理、将来の経済的自立に向けた準備が進められると考えられている。
家庭の方針による差異
家庭によって「定額で毎週渡す」「家の仕事をしたときだけ渡す」「特別なときのみ渡す」と方法は異なるが、「子どもが自分の意思でお金を使う練習をさせる」という目的は共通している。
2. 子どもがもらう金額の実態
年齢別の平均お小遣い額
イギリスの金融教育団体や銀行が定期的に実施している調査によると、年齢別のお小遣い額は以下のようになっている(2023年のGoHenry社の調査データを参照):
- 6歳:週に約2.50ポンド(約500円)
- 8歳:週に約3.00ポンド(約600円)
- 10歳:週に約4.50ポンド(約900円)
- 12歳:週に約6.00ポンド(約1200円)
- 14歳:週に約8.00ポンド(約1600円)
- 16歳:週に約10.00ポンド(約2000円)
月額換算すると、16歳の子どもで約40ポンド(約8000円)程度となる。
地域差と社会階層
ロンドンなどの都市部では生活費が高いため、ポケットマネーの金額も高めに設定される傾向がある。一方で、地方の家庭ではもう少し控えめな額が主流である。また、所得の高い家庭ではお小遣いの額が多めに設定される傾向があるものの、「金額の大小」よりも「教育的な使い方」を重視する家庭が多いのも特徴だ。
3. お小遣いの与え方と教育的視点
お金は「報酬」か「基本権利」か?
イギリスの親の間で議論されがちなのが、「お小遣いは労働に対する報酬として与えるべきか、それとも一定の年齢に達したら当然与えるべきか」という点である。
- 報酬型(Task-based):ベッドを整える、皿洗いをする、芝生を刈るなどの家事をこなした報酬としてポケットマネーを与える。
- 固定型(Fixed allowance):週に一定額を与え、使い方について自由を与える。節約や計画性を学ぶ機会となる。
この選択は、親の育児方針や教育観に強く影響される。調査によると、およそ6割の家庭が何らかの「報酬制」を取り入れており、子どもに「お金は働いて得るもの」という意識を育てようとしている。
「貯金」や「寄付」を促す工夫
多くの家庭では、ポケットマネーを「使う」「貯める」「シェアする(寄付する)」の三つのカテゴリーに分けるよう教えている。これは、収入の管理、未来のための貯蓄、他者への思いやりを同時に学ばせる実践的な方法である。
4. デジタル化とお小遣いの変化
キャッシュレス社会への対応
近年、イギリスでは現金よりもキャッシュレス決済が主流となっており、子どもに現金を渡すという習慣も徐々に変化している。特に「GoHenry」や「RoosterMoney」といったアプリ型の金融教育サービスが急速に広がっている。
子ども向けプリペイドカード
GoHenryのようなサービスは、親が設定した予算を子どものカードにチャージし、使い方をアプリでモニターする仕組みだ。子どもは自分のスマホやタブレットから残高を確認できるため、自然とお金の管理を学べるようになっている。
このようなサービスの普及によって、親は「現金を手渡す」という負担から解放され、子どもは「実際の社会と同じ金融環境」の中で成長できるというメリットがある。
5. 日本との比較と文化的考察
金銭教育の開始時期の違い
イギリスでは5歳〜7歳ごろから金銭教育が始まる家庭が多く、早い段階でお金の価値や管理の重要性を体験的に学ばせている。一方、日本では小学校高学年になってようやく「お小遣い帳」をつけるようになる子どもも多く、教育のスタート時期に差が見られる。
お金を「話題にする」ことへの抵抗感
日本では「お金の話ははしたない」「家庭の事情に子どもを巻き込むべきではない」とする考え方が根強いのに対し、イギリスでは「お金も教育の一部」として捉えられ、家庭内でお金について自由に話し合う文化がある。この違いが、金銭感覚の形成や経済的自立のスピードに影響していると考えられる。
6. 今後の展望と課題
子どもとデジタル金融リテラシー
現代の子どもたちは、生まれた時からデジタル環境に囲まれて育っている。ポケットマネーも、現金からデジタルへと移行する中で、子どもたちが正しい金融リテラシーを身につけることの重要性が増している。
今後は、AIやフィンテックがより日常に入り込む中で、単に「お小遣いを渡す」だけではなく、「なぜこの金額なのか」「どう使うとよいか」「何のために貯めるか」といった対話が家庭内でより必要になるだろう。
結論
イギリスにおけるお小遣い(ポケットマネー)は、単なる「お金を与える行為」ではなく、子どもにとっての人生の早い段階における経済教育の第一歩である。金額の大小に関係なく、「どのように使うか」「なぜ必要なのか」を考えさせることが、親と子の間で共有されているのが大きな特徴だ。
日本とイギリスでは文化や制度の違いがあるものの、「子どもが社会で生きていくための準備をする」という本質的な目的は共通している。これからの時代を生きる子どもたちにとって、金銭教育はますます重要なテーマとなっていくだろう。




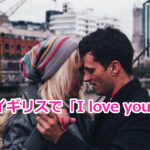





Comments