
はじめに
近年、イギリスのスポーツ界においてアジア系アスリートの活躍が目立つようになってきました。サッカー、クリケット、ボクシング、そしてオリンピック競技においてもアジア系の名前をテレビやニュースで見かける機会が増えています。
しかし、ふと立ち止まって考えてみると、ほんの10年、20年前までは、イギリスのテレビでアジア人アスリートの姿を見ることはほとんどなかったのではないでしょうか?なぜ、これほど多くのアジア系の人々が住むイギリスで、長年スポーツ界に彼らの姿が見えなかったのか。そこには、見えにくいけれど確かに存在した「疎外」の構造があったのかもしれません。
この記事では、イギリスにおけるアジア人アスリートの歴史をたどりながら、なぜその存在がこれほどまでに“見えにくかった”のか、そして今、何が変わりつつあるのかを掘り下げていきます。
アジア系イギリス人とは誰か?
まず前提として押さえておきたいのが、「アジア人」と一口に言っても、イギリスにおいてはその定義がやや異なるという点です。日本やアメリカでは「アジア人」というと東アジア系(中国、日本、韓国など)を想像することが多いですが、イギリスでは「Asian」と言えば、主に南アジア系(インド、パキスタン、バングラデシュなど)を指すことが一般的です。
実際、イギリスのアジア系住民の多くは南アジアにルーツを持ち、特にイングランド中部やロンドン周辺に多くのコミュニティを形成しています。彼らの多くは第二次世界大戦後、旧植民地から移民としてやってきた人々の子孫です。
なぜスポーツ界では「見えなかった」のか?
1. 文化的な期待とプレッシャー
多くのアジア系家庭では、伝統的に「教育」が最も重視されてきました。スポーツに対する価値観は家庭やコミュニティによって大きく異なりますが、少なくとも「プロのアスリートになる」という選択肢は、ごく一部の家庭を除いて現実的なキャリアパスとは見なされていなかったのが実情です。
たとえば、イギリスで育ったパキスタン系の子どもがプロサッカー選手を夢見たとしても、親からは「医者になりなさい」「エンジニアを目指しなさい」と言われることが珍しくありませんでした。これは、移民第一世代が経験してきた差別や経済的困難のなかで、より確実で安定した職を求める傾向が背景にあります。
2. 構造的な障壁
実際、アジア系の子どもが才能を見出されても、それを支える環境が整っていなかったという側面もあります。多くのスポーツクラブやトレーニング機関は白人中心のコミュニティで構成されており、アジア系の子どもや親が心理的に「歓迎されていない」と感じる場面も少なくなかったといいます。
また、コーチやスカウトの側にも無意識の偏見が存在していたとされます。「アジア人はフィジカルが弱い」「リーダーシップに欠ける」などといったステレオタイプが、選手選考の際に不利に働いた可能性は否定できません。
「例外」はいた:過去に光ったアジア系アスリートたち
それでも、歴史のなかでアジア系のアスリートが全くいなかったわけではありません。例えば、イギリス生まれのボクサー、アミール・カーン(Amir Khan)はその代表格です。彼は2004年のアテネオリンピックで銀メダルを獲得し、プロに転向してからも世界王者となりました。
カーンのような存在は、当時まだ稀だった「アジア系でもトップアスリートになれる」実例として、多くの若者に希望を与えました。しかし、あくまで「例外」として扱われていたことも事実です。
なぜ今、変化が起きているのか?
1. 第二世代、第三世代の登場
時代が進むにつれて、アジア系イギリス人も世代交代を迎えています。第二世代、第三世代になると英語を母語とし、地元の学校に通い、地元のフットボールクラブに自然に参加するようになりました。彼らは、親世代に比べてイギリス社会に「内在化」しており、より自由に進路を選べるようになっています。
2. 多様性への意識改革
ブラック・ライブズ・マター運動やDEI(多様性、公平性、包括性)への関心が高まるなかで、イギリスのスポーツ団体も、あらゆる人種や背景を持つ若者たちに門戸を開こうという動きが加速しています。
FA(イングランドサッカー協会)や英国オリンピック協会なども、アジア系を含むマイノリティへのリーチを強化し、スカウトやコーチのトレーニングにおいて「無意識のバイアス」を減らす試みを始めています。
3. 可視化とメディアの役割
SNSやYouTubeなどの発信力によって、マスメディアが取り上げないアスリートの活躍も瞬時に拡散される時代になりました。これにより、アジア系アスリートが地域大会で優勝したり、特別なプレーを見せたりすれば、すぐにコミュニティの誇りとして拡散され、注目されるようになります。
現在注目のアジア系アスリートたち
- ハミザ・チャウダリー(Hamza Choudhury):バングラデシュ系イングランド人のプロサッカー選手。プレミアリーグでプレーする彼は、多くの南アジア系少年たちの憧れです。
- ザイナブ・アリ(Zainab Ali):若手の女子陸上選手で、イスラム教徒としてヒジャブを着用しながら競技を続けている姿が話題に。
- エマ・ラドゥカヌ(Emma Raducanu):中国系とルーマニア系の混血である彼女は、2021年に全米オープンを制し、世界中の注目を浴びました。
「見えなかった歴史」を埋めるために
イギリスのスポーツ史において、アジア人アスリートが「いなかった」わけではなく、「見えなかった」だけだった、という認識は非常に重要です。彼らが表舞台に立てなかった背景には、家庭の価値観、社会の偏見、制度的な障壁など、複合的な要因が絡んでいました。
しかし今、少しずつその壁は崩れつつあります。現代の若者たちは、自分と同じルーツを持つアスリートが国際舞台で活躍する姿を見て、「自分にもできる」と思えるようになってきています。
おわりに:スポーツは誰のものか?
スポーツは本来、誰にでも開かれているべきものです。しかし現実には、文化や人種、経済状況によって“スタートライン”が異なることが多々あります。だからこそ、アジア系アスリートたちがその壁を乗り越えて活躍する姿は、ただの「成功物語」以上の意味を持つのです。
これからの時代、スポーツ界が真に多様性を尊重する空間として機能するためには、過去の「見えなかった歴史」を正しく理解し、そこから学ぶことが不可欠です。
アジア系アスリートの物語は、まさに今、未来へと続く“新しい歴史”を書き始めたばかりなのです。






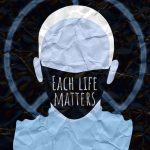



Comments