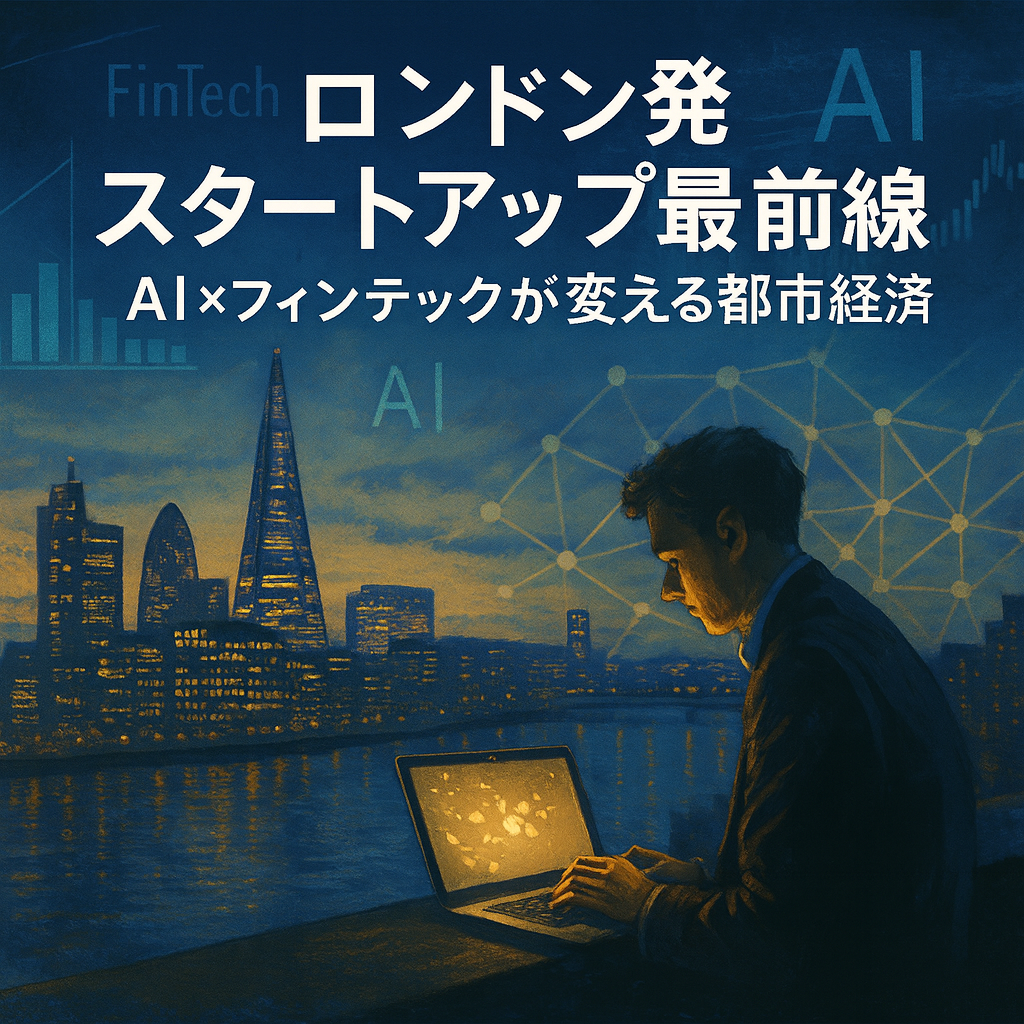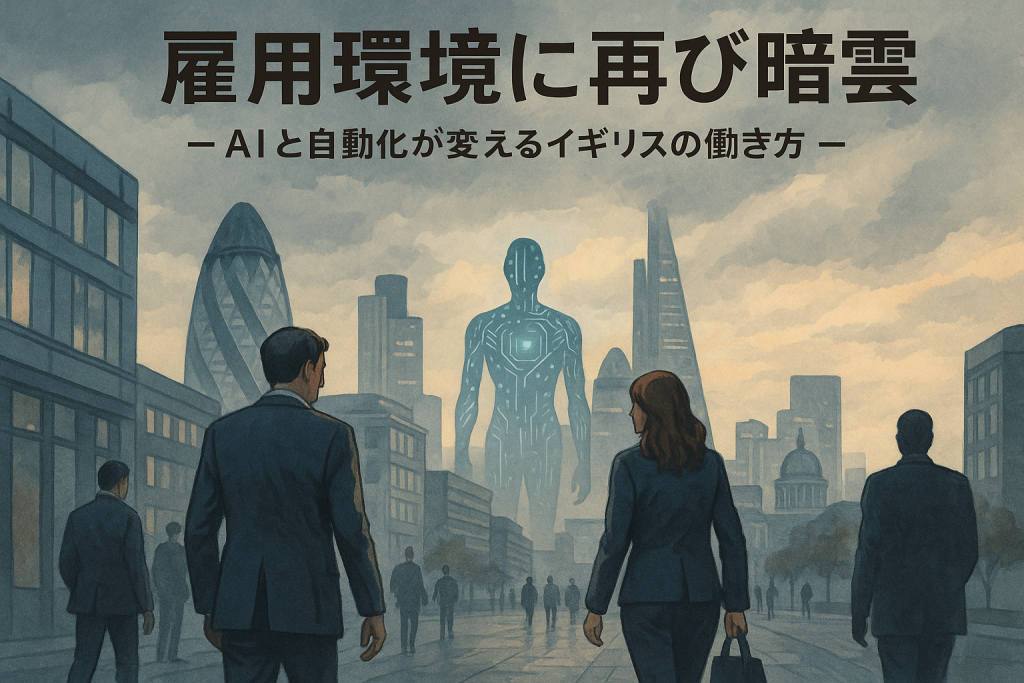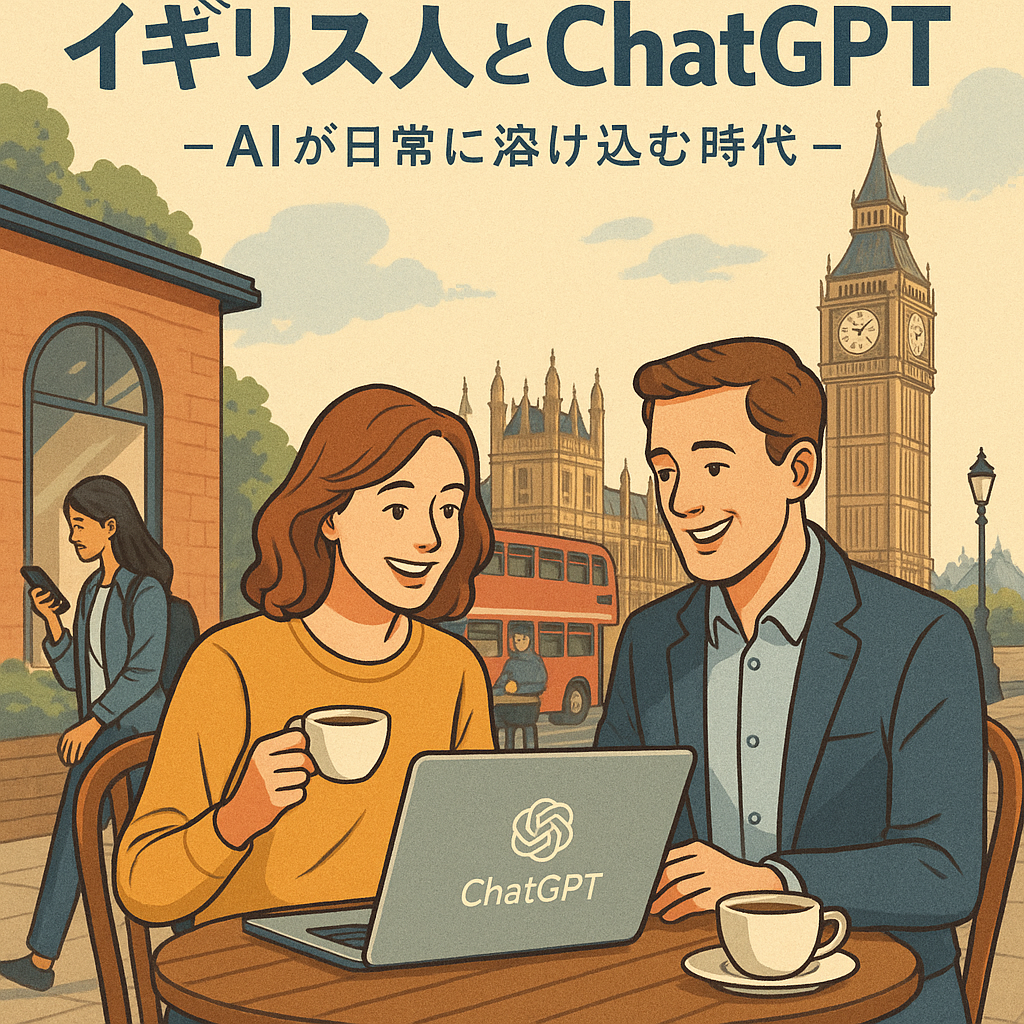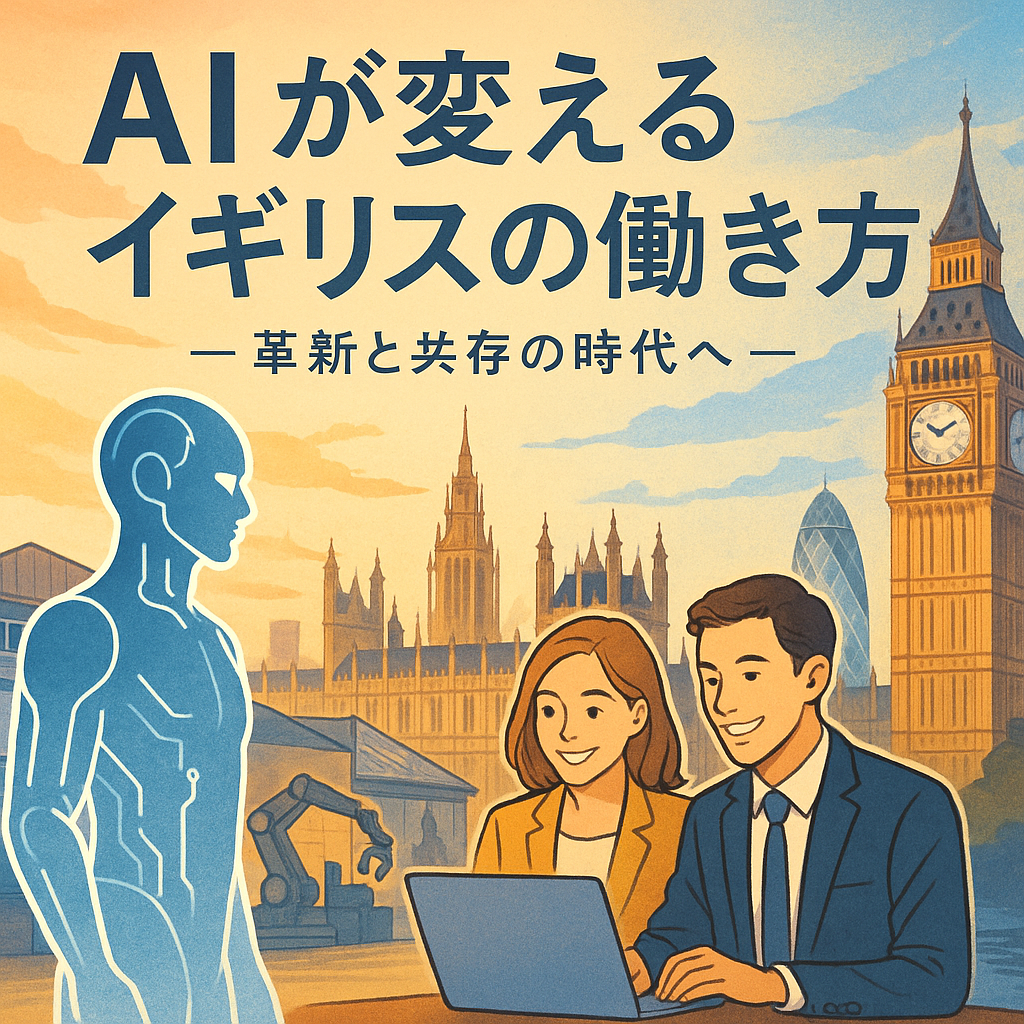…
Author:admin
「中東のシリコンバレー」イスラエル発のテック革命と世界投資の動き
…
ロンドン発スタートアップ最前線|AI×フィンテックで変わる都市経済
…
ロンドンが世界のAIハブへ|ケンブリッジとの連携で進むイノベーション都市構想
…
トランプ米大統領とネタニヤフ首相のスピーチ|米イスラエル関係強化と沈黙する欧州、スターマー首相の存在感薄く
…
BBC報道:ネタニヤフ首相は戦争継続を望む一方、イスラエル国民は停戦を求める
…
雇用環境に再び暗雲 ― イギリスで進むAI導入と人員削減の現実
…
イギリス人とChatGPT|生活に溶け込むAI革命と新しい日常
…
AIが変えるイギリスの働き方|人件費削減と世代間の反発を超えた新しい未来
…
イスラエルとガザ停戦・人質解放に歓喜広がる|イギリスのイスラエル人・ユダヤ人コミュニティの反応
…