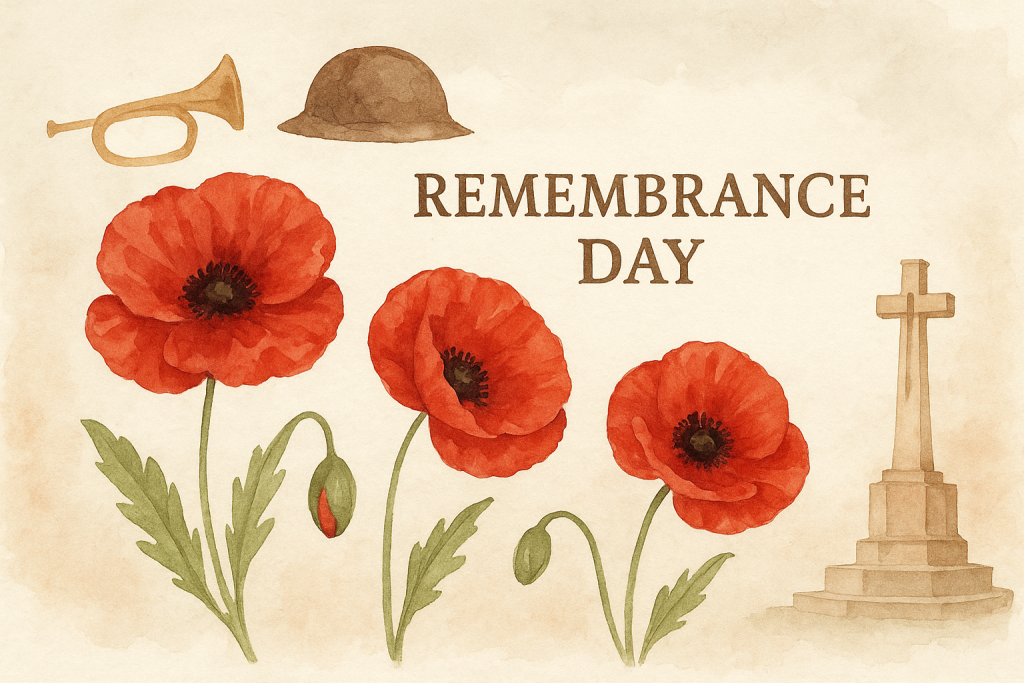…
戦争
Remembrance Day(リメンブランス・デー)とは何か
…
トランプ米大統領とネタニヤフ首相のスピーチ|米イスラエル関係強化と沈黙する欧州、スターマー首相の存在感薄く
…
BBC報道:ネタニヤフ首相は戦争継続を望む一方、イスラエル国民は停戦を求める
…
イスラエルとガザ停戦・人質解放に歓喜広がる|イギリスのイスラエル人・ユダヤ人コミュニティの反応
…
イスラエル・ガザ停戦後、英国に及ぶ経済的負担と移民受け入れへの影響を中立的に整理
…
英国スターマー政権のガザ停戦対応を時系列で整理|声明・人道支援・輸出停止の実績まとめ
…
スターマー英首相、「停戦スピーチは完璧、実行は行方不明」──イスラエルとガザに響かない平和の言葉
…
英国によるパレスチナ国家承認の背景と影響
…
イギリス国内に漂う「トランプ嫌悪」と現実重視のズレ
…