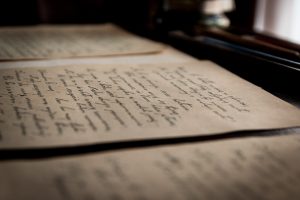
日本の学校教育において「作文」は、子どもたちの思考力や表現力を養う重要な手段のひとつである。夏休みの宿題、学期末の課題、入試の一環としても頻繁に登場し、多くの日本人にとって馴染み深い教育活動だ。一方、英語圏、特にイギリスの学校では、「作文」に相当するような取り組みがあるのだろうか。本記事では、イギリスの初等・中等教育における作文指導の実態や特徴、教育理念の違いについて、日本との比較を交えながら掘り下げていく。
1. 「作文」と「エッセイ」:言葉の壁を越えて
まず、「作文」とは何かを改めて定義する必要がある。日本語における「作文」は、子どもが自己の体験や考えを、一定のテーマに沿って自由に書く文章である。表現の自由度が高く、個人の感じ方や視点が尊重される。
対して、イギリスでは「Essay(エッセイ)」という言葉が一般的に使われる。日本語では「エッセイ」と言うと随筆や軽妙な散文を連想しがちだが、英語の”Essay”はより論理的・構造的な文章を意味する。学校教育の中では、特定のテーマに対し、自分の意見や見解を論理的に展開していく文章として扱われる。
とはいえ、イギリスにも「作文」と呼べるような創作的・表現的な文章指導は確かに存在している。それが”Creative Writing(クリエイティブ・ライティング)”である。
2. 小学校段階における作文教育
イギリスの初等教育(Primary School)は5歳から11歳までを対象とし、国語(English)は主要教科のひとつである。この中で、児童たちは文章を「読む」だけでなく「書く」ことも学ぶ。
小学校では、次のような形で作文に類する活動が行われている:
- ストーリーテリング(Storytelling):自分で物語を創作する。登場人物、舞台、問題、解決といった構成要素を学び、オリジナルの話を書く。
- 日記(Diary Writing):ある出来事を自分の視点で書く。日本の作文に近い。
- 説明文(Explanatory Texts):ある仕組みや手順について説明する文章。
- 意見文(Persuasive Writing):何かを主張する文章。例えば、「校庭に新しい遊具を設置するべきか」など身近なテーマで書かせる。
こうした活動は、”National Curriculum”(全国カリキュラム)に基づいて計画的に行われる。指導要領では、文法やスペリングの正確さ以上に、語彙の選択・構成の明確さ・読者への配慮が重視されている。
3. 中学校・高校での作文指導
中等教育(Secondary School)に進むと、文章指導はより本格化する。特に11歳から16歳までのKey Stage 3およびGCSE(General Certificate of Secondary Education)段階では、以下のような文章が書かれる:
- 分析的エッセイ(Analytical Essays):文学作品や詩を読んだ後、それについて論じる。たとえばシェイクスピアの登場人物の心理について分析するような課題が与えられる。
- 議論文(Argumentative Writing):社会問題などについて意見を述べる。論理的な構成と証拠の提示が求められる。
- ナラティブ・ライティング(Narrative Writing):物語形式での創作文章。
- 実用文(Transactional Writing):手紙、Eメール、記事、レポートなど。
これらの課題は、評価対象として明確に「構成」「文法」「語彙の多様性」「説得力」などの観点でルーブリック化されており、教師は客観的に採点できるよう訓練されている。
また、A-Level(大学進学資格)の段階では、かなり高度なアカデミック・ライティングが求められ、リサーチベースのエッセイや比較論文を書く機会が増える。ここまでくると、日本の大学入試小論文や卒業論文に近い形式になる。
4. クリエイティブ・ライティングの重視
イギリスの教育では、分析的・論理的な文章に加えて、”Creative Writing”(創造的文章)も非常に重要とされている。物語、小説、詩、脚本などを自由に書く力は、自己表現の一環として奨励されている。
たとえば、文学の授業では、生徒が登場人物の視点から物語の続きを書いたり、自作の詩を朗読したりする課題が出される。学校によっては”Writing Club”のような課外活動もあり、才能ある生徒が校内コンテストや地域の文学賞に挑戦することもある。
また、イギリスの教育は「批判的思考(Critical Thinking)」を重視しており、文章を書くことはその訓練の場とされている。型にはまった模範解答を書くことよりも、自分なりの切り口や解釈を提示することが評価されやすい。
5. 日本との比較:評価と目的の違い
日本の作文教育とイギリスのライティング教育には、いくつかの本質的な違いがある。
| 観点 | 日本 | イギリス |
|---|---|---|
| 目的 | 表現力、情緒の成長 | 論理的思考、説得力、創造性 |
| 評価方法 | 感情や体験の深さを重視 | 論理構成、言語運用能力 |
| 文体 | 一人称が多い、主観的 | 客観性や論理性を重視 |
| 使用される形式 | 作文、感想文、小論文 | エッセイ、レポート、創作物語 |
日本の作文は感受性や心情を重んじる傾向があるのに対し、イギリスでは**「書くことは考えること」**という考えのもと、文章を通じた思考訓練として位置づけられている。
6. グローバル社会における作文の価値
グローバルな視点で見ると、「書く力」は英語圏でも日本でも、ますます重要視されている。AIの台頭や情報社会の加速により、単に知識を持っているだけでなく、自分の考えを言語化し、他者に伝える力が求められる時代になった。
イギリスではこの流れに応じて、早期から文章教育に力を入れ、卒業後の進学・就職においてもその能力が重視される。日本でも、これまでの「感想文」中心から「論理的文章」へのシフトが進んでおり、両国とも作文教育の進化が見られる。
おわりに
イギリスの学校にも、日本で言う「作文」に相当する教育は確かに存在する。ただし、その形式や目的は日本とはやや異なり、より論理的・分析的・創造的なアプローチが取られている。
「書くこと」は単なる言語運用ではなく、思考を深め、自己を表現し、他者とつながるための重要なスキルである。その本質は国を問わず共通しており、異なる教育文化から学ぶことで、より豊かな文章教育のあり方が見えてくるに違いない。










Comments