
2025年初頭、ロンドンの地下鉄内でインド人女性が素手でカレーライスを食べていたという出来事が、SNSを中心に大きな話題となった。ある乗客がこの様子を隠し撮りし、コメント付きで投稿したことで、瞬く間に拡散。動画のコメント欄には、「不衛生」「公衆の面前で食事をするなんてあり得ない」「だから移民は…」というような批判が並ぶ一方、「ハンバーガーなら許されるのに?」「手で食べるのは文化だ」「イギリス人のダブルスタンダードだ」と擁護や反論の声も数多く見られた。
本記事では、この一件をきっかけに、イギリスにおける公共の場での「食べる行為」の文化的位置づけ、差別と偏見の構造、そして多文化社会ロンドンのあり方について、様々な視点から深掘りしていく。
1. 公共の場で「食べる」ということ──イギリス文化における暗黙のルール
まず初めに確認しておきたいのは、「ロンドンの地下鉄で食事をすることは違法なのか?」という点である。答えは「ノー」だ。ロンドン交通局(TfL)の公式規定では、明確に「車内での飲食を禁止」としているわけではない。ただし、「匂いが強く、他人の迷惑になる可能性がある食事は控えるように」といった注意喚起はある。
実際、ロンドンの地下鉄内では、多くの人がテイクアウトのコーヒーや軽食を手に持って乗車しており、朝のラッシュ時などにはサンドイッチやペイストリーを片手に通勤する人の姿も日常的に見られる。つまり、「公共の場で食事をする」ことそのものは、イギリス文化の中で決して禁忌とはされていない。
しかし、「何をどう食べるか」については、明確な階層や文化の無意識の基準が存在する。例えば、フォークやナイフ、少なくともプラスチックのスプーンであれば許容されるが、「手で食べる」という行為は、どこか「原始的」「不衛生」「下品」といったニュアンスを含む目で見られる傾向がある。
2. 手で食べる文化は「野蛮」か?:西洋中心主義の罠
では、「手で食べる」ことは本当に不衛生であり、公共の場にふさわしくない行為なのだろうか?
答えは文化によって異なる。インドや中東、アフリカの多くの地域では、手で食事をすることはごく普通のことであり、食事に対する敬意を示す行為ですらある。手で食べることによって料理の温度や質感を感じ取り、五感をフルに活用するという食文化が根付いている。
この視点からすると、「手で食べる=下品・不衛生」という認識は、あくまで西洋的な価値観に基づいたものであり、他の文化を自らの物差しで測る「西洋中心主義」に他ならない。
今回の一件で問題視されたのは、単に「手で食べた」ことではなく、それが「見慣れない」「異質な」文化の行為だったという点である。つまり、問題は衛生の有無やマナーの良し悪しではなく、偏見と無知からくる「文化的差別」に根ざしている。
3. ハンバーガーならOK?:許される食べ方・許されない文化
批判の中には、「カレーを手で食べるなんて」というコメントが多く見られたが、それと同時に、なぜ「ハンバーガーやフィッシュアンドチップスならOKなのか?」という問いも浮かび上がった。
実際、ロンドンの地下鉄では、ファストフードの包装紙を抱えてハンバーガーやチキンを食べている若者も少なくない。彼らに対しては、同じようなレベルの批判はほとんど見受けられない。
ここにあるのは、「見慣れた文化」への寛容と、「異文化」への無意識の排除だ。ハンバーガーやサンドイッチは「西洋的」「現代的」「便利な」食べ物として許容されるが、手でカレーを食べる行為は「異質で原始的で、公共の場にそぐわない」と捉えられてしまう。これは食文化の問題ではなく、「誰がどの文化を体現しているか」によって態度が変わる、という構造的な偏見の現れである。
4. 移民、階級、公共空間──ロンドンという都市の複雑性
ロンドンは、世界でも最も多文化的な都市の一つであり、人口の約40%以上が非白人系住民と言われている。特にインド系移民は、イギリスの歴史的背景からも多く住んでおり、カレーは今や「国民食」として認知されているほどである。
しかし、どれだけ食文化が融合しても、「誰がその文化を体現するか」という要素は、依然として大きな意味を持つ。白人のイギリス人がタンドリーチキンを食べていれば「多文化の享受」として好意的に捉えられるが、インド系女性が手でカレーを食べれば「不衛生」「マナー違反」とされる。
この現象は、単なる文化の違いではなく、移民に対する根強い階級意識や人種的偏見の表出であり、「誰が公共空間にふさわしいか」という無意識の線引きが、いかに差別的であるかを示している。
5. SNS時代の監視と羞恥文化──「晒し」の暴力
この騒動が広がった背景には、もう一つ大きな問題がある。それは、「他人の行為を勝手に撮影し、SNSで晒す」ことへの倫理的な問題だ。
今回のケースでも、撮影者は女性の同意なく動画を撮影し、「見て、これが今のロンドンだ」と皮肉混じりに投稿していた。これに対し、一部のユーザーからは「盗撮ではないか」「プライバシー侵害だ」という批判も出たが、炎上はすぐに「彼女のマナー」へとすり替えられていった。
現代のSNS文化では、「公共の場で目立つ行為をすると晒される」「常に他人の視線がある」という一種の“監視社会”が形成されており、それが羞恥心や自己検閲を過剰に促す構造を作り出している。これは自由と多様性を尊重する都市社会にとって、決して望ましい傾向ではない。
6. 「公共性」とは誰のものか?:これからの多文化共生社会へ
最後に考えるべきは、「公共空間とは誰のものか」という問いである。
公共の場におけるマナーや常識は、時代や文化によって変化し続ける。現代ロンドンのような多文化都市においては、単一の文化や価値観だけでマナーを定義することは、むしろ排他的で不公正になり得る。
今回の騒動を通して浮かび上がったのは、「異文化への無理解」ではなく、「異文化に対する選択的な拒絶」の構造だ。言い換えれば、「文化を受け入れるふりをして、実際は排除している」という偽の寛容性が、我々の社会に根強く残っているということである。
多様性とは、単に様々な文化が「共存する」ことではなく、相互理解とリスペクトを通して「共に在る」ことだ。そして、それを実現するためには、目に見えないバイアスや無意識の偏見に気づくところから始めなければならない。
結びに代えて:問い直すべきは「彼女の行為」ではなく、「私たちの視線」
ロンドン地下鉄の「カレー手食べ騒動」は、単なる日常の一コマが、いかにして社会全体の無意識な構造を映し出す鏡となるかを示してくれた。
公共空間における行為は、その行為それ自体よりも、「誰がそれを行っているか」という文脈によって判断されがちだ。そして、それが文化的・人種的な偏見と結びついた時、マナーや常識は、他者を排除する武器に変わってしまう。
本当に問い直すべきなのは、手でカレーを食べた女性の行為ではなく、それを見た私たちの視線と、そこに潜む無意識の優越感ではないだろうか。









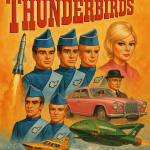
Comments