
「イギリス人はお金に関して無頓着だ」と感じる日本人は少なくない。旅行先や留学、仕事でイギリスに関わった人々からは、「お金の話をタブー視するわけでもないけれど、日本人ほど細かくは気にしていない印象がある」「貯金よりも今を楽しむことを優先しているように見える」といった声が聞かれる。果たしてこれは本当なのか?あるいは単なる文化の違いなのか?本稿では、イギリス人の金銭感覚を多角的に分析しながら、日本人との違いを考察していく。
1. お金に対する基本的な姿勢:貯蓄か消費か
まず注目すべきは、「お金に対する基本的な姿勢」である。
日本人の多くは、将来への不安を見越して「貯金」を重視する傾向がある。子どもの教育費、住宅購入、老後の生活資金、万一の医療費など、あらゆる場面に備えてコツコツと貯める文化が根強い。実際、日本銀行のデータによると、日本の家計貯蓄率は長年にわたり世界的に高い水準にある。
一方で、イギリス人は比較的「消費」を重視する。所得の中からどれだけを楽しみに使えるか、つまり「いまの生活の質」を重視する傾向がある。もちろん、すべてのイギリス人が浪費家というわけではないが、「使うことは悪ではない」という社会的な合意が存在するのは確かだ。
この違いは、単なる個人の性格ではなく、文化的な背景や社会制度にも深く根ざしている。
2. 社会保障制度の影響
イギリスは、ナショナル・ヘルス・サービス(NHS)に代表されるように、国民皆保険、無料医療制度が非常に充実している国である。入院や手術、出産などの医療行為に対して、基本的には無料で受けることができる。これにより、医療費に対する備えをそれほど意識する必要がない。
さらに、年金や失業保険、育児支援といった福祉制度も整っており、「最悪の事態になっても何とかなる」という安心感がある程度ある。結果として、「将来のためにお金を貯めなければ」という強迫観念に駆られにくい。
対して日本では、医療は公的保険で賄われるものの、自己負担もあり、介護や年金に対する不安は根強い。国の制度を完全に信頼できないという意識が、貯蓄行動を後押ししている側面がある。
3. 教育と家族観の違い
日本では、子どもにかける教育費が家計において大きな比重を占める。中学受験や私立進学、大学進学など、教育には多大な費用がかかり、「子どもに投資する」という感覚が強い。
イギリスでも教育費は決して安くないが、18歳以降の大学教育は基本的にローン制度(Student Loan)を利用し、学生本人が将来返済していく仕組みである。親が全額を負担するという考え方は一般的ではなく、「教育は個人の責任」とする文化がある。この点も、親世代の金銭的プレッシャーの違いを生んでいる。
また、家族の経済的な結びつきのあり方も異なる。日本では「親が子を養う」「子が親を支える」といった相互扶助の意識が比較的強いが、イギリスでは「経済的には独立した個人」という価値観が基本にある。
4. お金の話をどう捉えるか:タブーかオープンか
「お金の話は下品だ」という感覚は、日本でもイギリスでも一定程度は共通している。特に職場での給与や昇給の話などは、どちらの国でもあまりオープンにされない。
しかし、その「タブー」の質が異なるのが面白い点だ。日本では、「自分の収入や貯金を話すのは謙虚さに欠ける」「人と比べるようでよくない」という感覚が強い。一方でイギリスでは、「収入や財産はプライベートな情報」という認識であり、「無神経な話題」として避けられることが多い。
一方で、家計管理や投資に関してはイギリスの方がずっとオープンで、学校教育でも「お金の扱い方(Financial Literacy)」が早期から教えられるようになっている。家庭でも「子どもにお金を持たせて管理させる」「家計を一緒に考える」といった習慣が根付いており、日本よりも“教育としてのお金”には熱心とも言える。
5. クレジット文化と「借金」の捉え方
イギリスではクレジットカードやローンを使うことに対する抵抗感があまりない。むしろ、「信用履歴(Credit History)」を作ることが重要視されており、一定の借入と返済を行うことが社会的信用の証とされる。
日本では、「借金=悪」という考え方が根強く、「ローンは最後の手段」という人も少なくない。これは、戦後の経済的困難を背景に「無駄遣いせずコツコツ貯める」ことが美徳とされた歴史が大きく影響している。
この「借金」に対する価値観の違いは、日常の消費行動に如実に表れる。イギリス人は「欲しいから買う」「必要なら借りてでも楽しむ」という思考をしやすく、日本人は「お金が貯まるまで待つ」「無理せず身の丈に合った生活を」という姿勢を取りやすい。
6. 「無頓着」なのではなく、「哲学」が違う
こうして見ると、イギリス人が「お金に無頓着」という印象は、実際には「お金に対する哲学が違う」ということに過ぎないとわかる。イギリス人は「今を楽しむこと」を大事にし、「お金は手段であって目的ではない」というスタンスを取りがちである。
一方で、日本人は「将来に備える」「人との関係に気を使う」「堅実であることを美徳とする」という文化的背景のもと、お金の使い方に慎重になる傾向がある。
どちらが優れている、正しいという問題ではない。むしろ、どちらの価値観も長所と短所があり、状況によってバランスよく活用されるべきだろう。
7. グローバル化による価値観の変容
近年、SNSやインターネットの普及により、国境を越えた価値観の交流が進んでいる。日本でもFIRE(Financial Independence, Retire Early)を目指す人が増え、投資や資産運用に対する関心が高まっている。一方、イギリスでも「エシカル消費」や「サステナブルライフ」の広がりにより、お金の使い方を再考する動きが出てきている。
つまり、「イギリス人はこう」「日本人はこう」と単純に断言できる時代ではなくなってきている。個人の生き方や人生観に応じて、柔軟にお金と向き合うことが求められているのだ。
おわりに:お金は鏡である
お金の使い方、貯め方、考え方――それらは、その人がどんな人生を送りたいのか、どんな価値観を持っているのかを映し出す鏡である。
イギリス人の金銭感覚に「無頓着さ」を見るか、「自由さ」を見るかは、日本人である私たちの視点に左右される。だが、そこには確かに「自分らしく生きるために、お金をどう使うか」という一貫した哲学がある。
日本的な「備えの美徳」もまた尊い。一方で、ときにイギリス人のように「今を楽しむ」視点を持つことで、お金との付き合い方が少し楽になるかもしれない。文化の違いを知ることは、他者を理解するだけでなく、自分自身の価値観を見つめ直す貴重な機会にもなるのである。








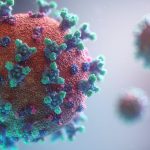

Comments