
介護殺人という、もうひとつの「看取り」
日本では時折、胸が締め付けられるようなニュースが流れてきます。長年家族を介護していた人が、ついに限界を迎え、被介護者である家族を殺してしまう──いわゆる「介護殺人」です。
加害者は高齢者であることも多く、その表情には罪悪感よりも、どこか安堵のようなものすらにじむこともあります。本人にとっては「殺した」のではなく、「救った」のだと感じているのかもしれません。
このような事件は、イギリスでは非常にまれです。もちろんゼロではありませんが、日本ほど頻繁に社会問題として浮上することはありません。
なぜ同じように高齢化が進む先進国であるイギリスと日本で、これほどまでに「介護をめぐる悲劇」の様相が異なるのでしょうか?
この記事では、その背景にある文化、社会制度、家族観の違いを深掘りしながら、介護疲れとその果てにある悲しみ、そしてそこに込められた愛情について考えていきます。
なぜ日本では「介護殺人」が起きるのか?
社会制度の脆弱さと「家族任せ」の文化
日本には介護保険制度が存在し、一定の条件下でプロによる介護サービスを受けることができます。しかし、現実にはその支援は十分とはいえません。
特に、重度の要介護者を抱える家庭では、訪問介護の短時間利用やデイサービスだけではとても足りず、結局、家族がその多くを担うことになります。
「迷惑をかけたくない」「施設には入れたくない」という高齢者自身の価値観、
「親を見捨てたと思われたくない」「家族は家で看取るべき」という社会的圧力──
そうした価値観が、介護を家族の責任とみなす空気を強めてきました。
この「家族任せの介護文化」は、じわじわと介護者の心と体を追い詰めていきます。
介護疲れとは「命を削る共依存」
介護には終わりが見えません。どんなに尽くしても、症状が改善することは基本的にありません。
要介護者の心身は衰え、できたことができなくなり、記憶も会話も失われていきます。
介護者は24時間態勢で起き、排泄の世話をし、食事を作り、何度も呼ばれ、夜中も眠れず、自分の時間をほとんど持てません。
「死んでしまえば楽になるのに」「いっそ自分が死にたい」と思うようになり、やがて「この人を楽にしてあげたい」と思うようになるのです。
その果てに起こるのが、「介護殺人」です。
これは単なる殺人ではありません。
ある意味で、極限状態の中で生まれた「歪んだ愛情の表現」でもあるのです。
イギリスではなぜこのようなことが起こりにくいのか?
「家族が介護するべき」という価値観の希薄さ
イギリスでは、家族が高齢者や障がい者を長期間、24時間体制で介護するという文化は希薄です。
もちろんサポートはしますが、それは「手助け」のレベルであり、基本的には公的サービスに頼るという姿勢が一般的です。
「自分の人生は自分のもの」という個人主義の考えが根底にあり、家族間の依存度が低いため、
「子が親の面倒を見るのは当然」という価値観自体が存在しません。
むしろ、介護の全責任を家族に背負わせることのほうが非倫理的と見なされる傾向にあります。
充実した介護制度と公的支援
イギリスには「NHS(国民保健サービス)」を中心とした包括的な社会福祉制度があります。
介護が必要とされる場合、地域のソーシャルワーカーが介入し、必要な支援を制度的に受けることができます。
とくに在宅介護においては、パーソナルケアワーカーが毎日複数回訪問し、排泄・入浴・服薬・移動の補助を行います。
また、認知症患者には専門ケアを提供するグループホームやデイセンターも多く、家族の負担が最小限に抑えられます。
こうした公的支援により、介護が「命を削るほどの負担」になることが少ないのです。
「施設に入れること」への罪悪感がない
日本では、親を介護施設に入れることに対し、「見捨てたようで後ろめたい」と感じる人が少なくありません。
対してイギリスでは、プロフェッショナルに任せることが「最良の判断」とされることが多いのです。
「施設=悪い場所」という偏見もなく、むしろ本人の尊厳を守る手段として尊重されます。
そのため、家族が無理をする前に「助けを求める」という判断がなされやすく、結果的に介護による悲劇が防がれているのです。
「愛ゆえに殺す」という悲劇
日本の「介護殺人」は、単なる制度の欠陥だけでなく、
「愛情」や「義務感」といった人間関係の濃さゆえに起こっているという側面もあります。
イギリスでは、このような「情の深さ」が希薄である代わりに、「制度の冷静さ」があります。
それは時に「ドライ」とも感じられるかもしれませんが、逆に言えば、感情に任せて命を奪うような事態を回避する合理性があるとも言えるのです。
では、日本のように「愛の深さ」が悲劇を生む社会は、間違っているのでしょうか?
決してそうではありません。
問題は、「愛のあり方」と「社会制度の脆弱さ」がアンバランスであることです。
愛しているからこそ、自分を犠牲にしなければならない。
愛しているからこそ、苦しむ姿を見ていられない。
そんな状態を支える仕組みが、今の日本には足りていないのです。
それでも、誰かを看るということの意味
介護という行為は、ある種の「献身」です。
相手の尊厳を支え、自分の時間と人生の一部を差し出すことでもあります。
それを一人で背負いすぎると、歪んだかたちでしか表現できない愛情になってしまう。
その愛が、本来のかたちを失わないようにするには──
制度の力が必要です。
社会の理解が必要です。
そして、何より「声を上げてもいいんだ」という空気が必要なのです。
おわりに:この国で介護とどう向き合うか
イギリスでは、誰かが限界を迎える前に、周囲が気づき、支援し、仕組みが動きます。
それは文化的な違いであると同時に、国の「設計」の違いでもあります。
日本もまた、急速に高齢化が進むなかで、「自己責任の介護」から「社会全体で支える介護」へと舵を切る必要があります。
介護の末に悲劇が起こる社会では、誰も幸せになれません。
愛するからこそ、無理をしない。
愛するからこそ、手放すという選択肢がある。
そんな社会が当たり前になっていくことを、心から願います。





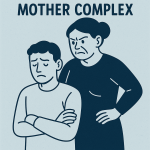




Comments