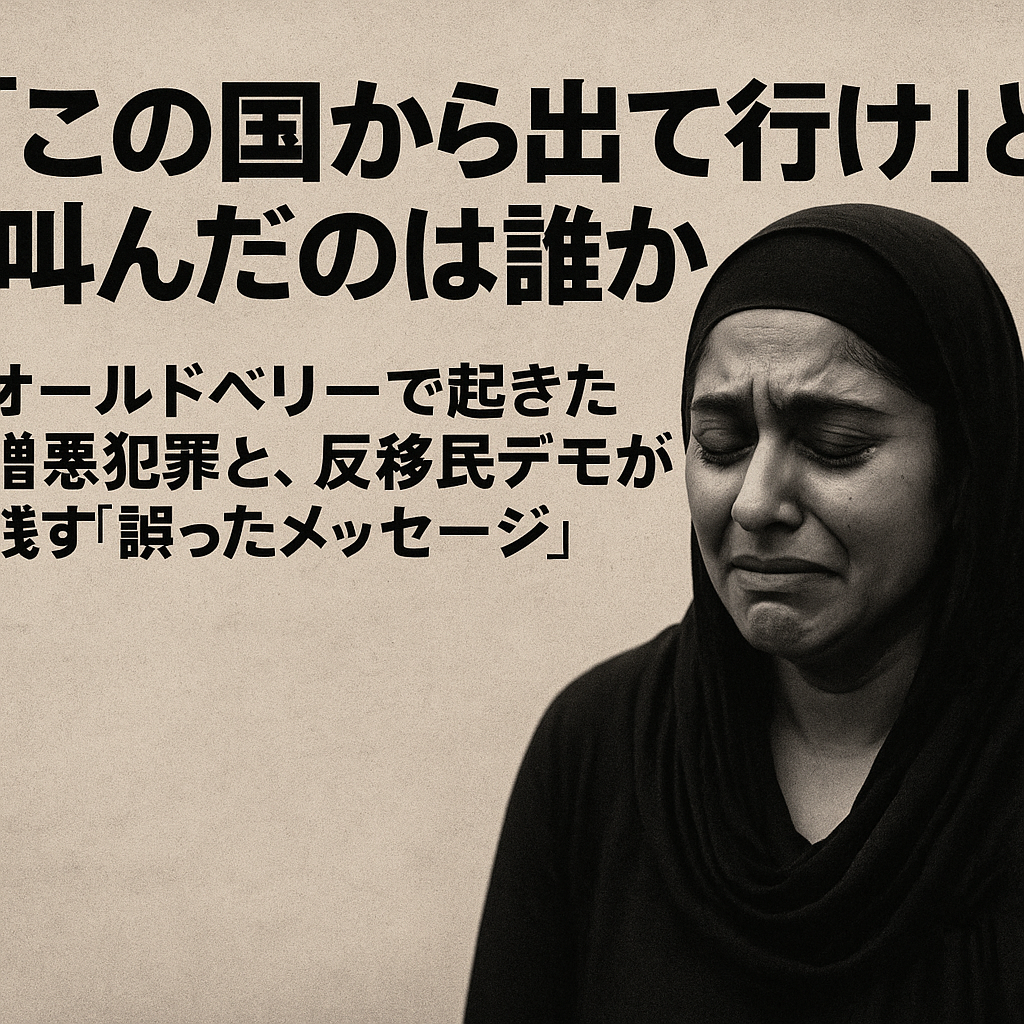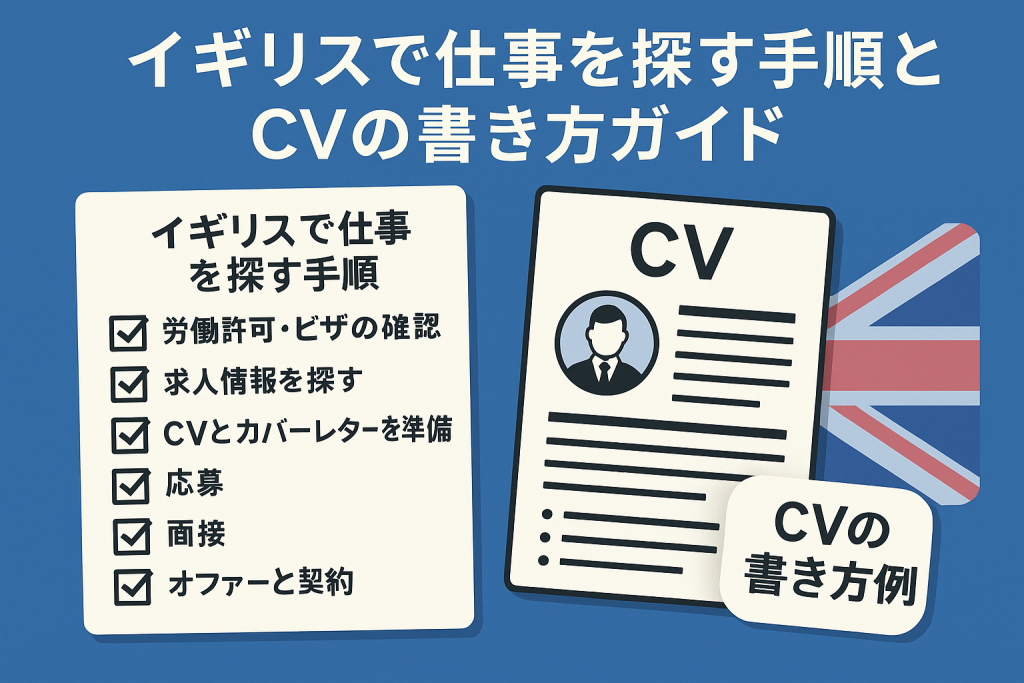…
Author:admin
「イギリス人らしさ」を手放したのは誰か
…
消えゆく大手小売、はびこる床屋とスイーツショップ――イギリス商店街に潜む「闇の経済」
…
ネット発!イギリスから世界に羽ばたいたお宅たちの成功物語
…
ロンドン証券市場の魅力と注目株|場所・見学・証券会社の最新ガイド
…
「この国から出て行け」と叫んだのは誰か――オールドベリーで起きた憎悪犯罪と、反移民デモが残す“誤ったメッセージ”
…
イギリスの「時効なき国」なのに犯罪者はのうのうと?法律と現実のギャップを探る
…
イギリスのインフレ率が高止まりする背景 ― 共存を拒んだ代償
…
イギリスでのプライマリースクールの探し方と申し込み方法
…
イギリスで仕事を探す手順とCVの書き方ガイド
…