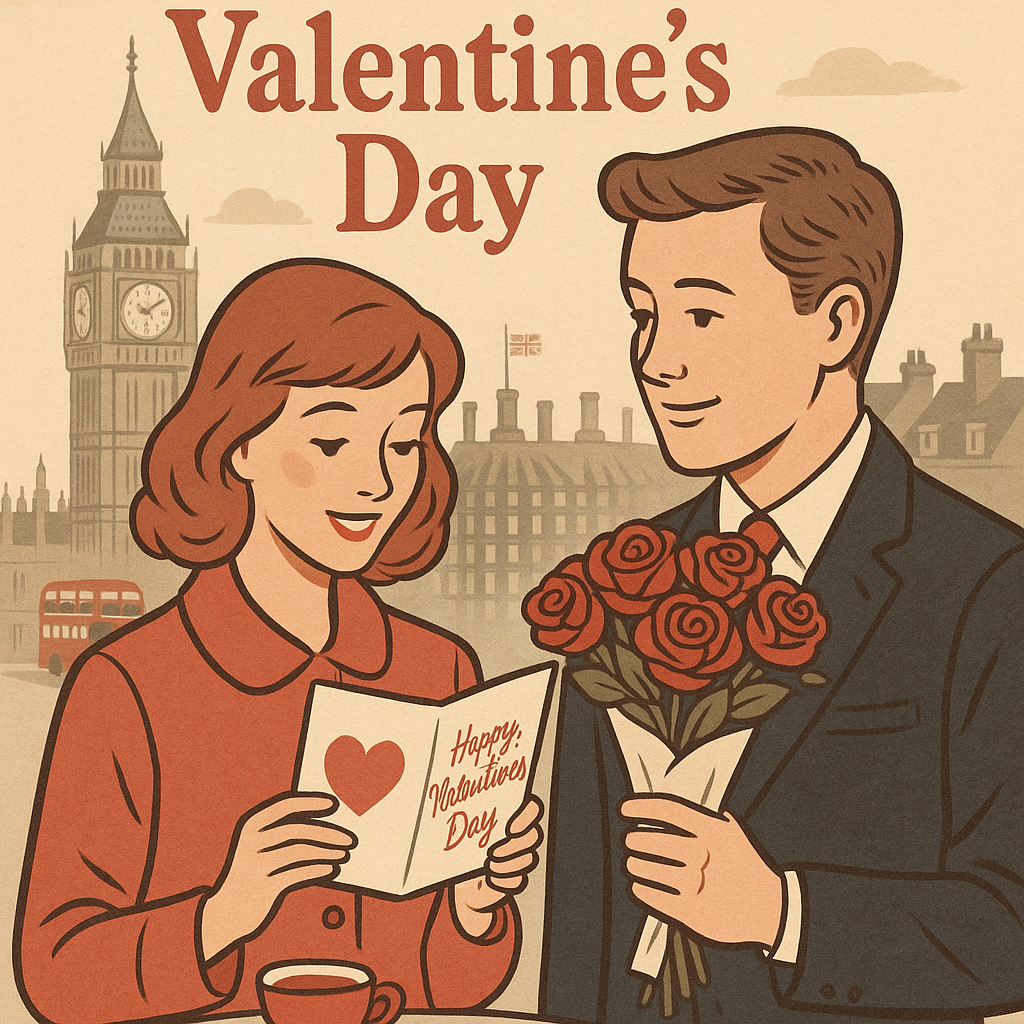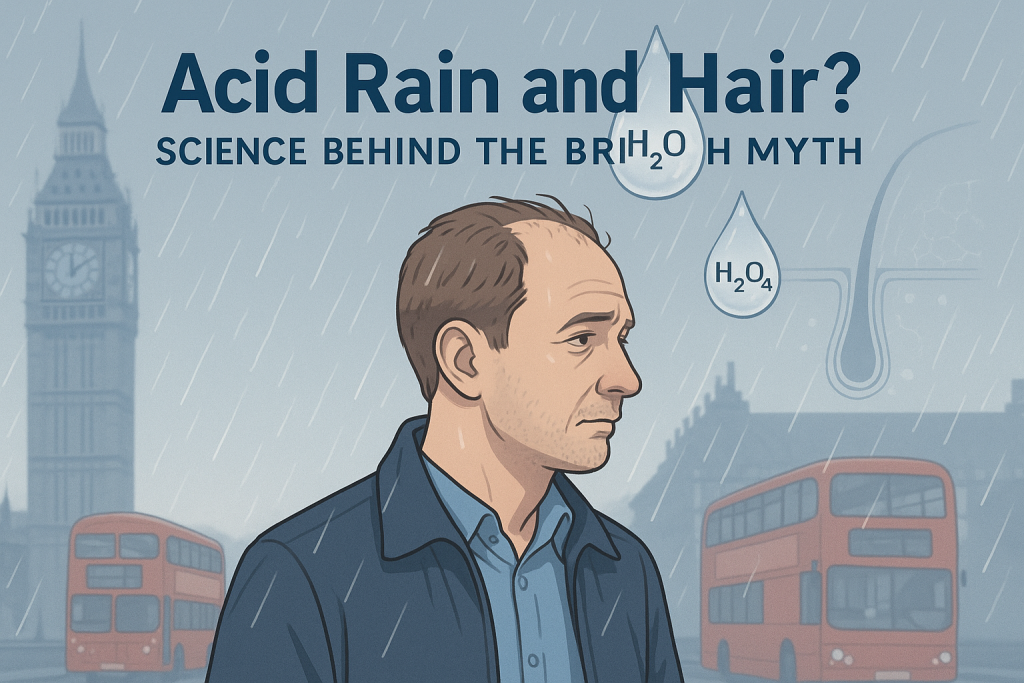…
話題
ロンドンに建設予定の巨大中国大使館
…
イギリスで人種差別的なコメントを耳にすることが増えた理由
…
イギリスのYouTuber文化は衰退するのか
…
過密化するイギリス刑務所の現実――そして生じる「誤った釈放」という危機
…
バレンタインデーについて
…
『Awaab’s Law』ができても、家はまだ安全じゃない――止まらぬ英国のカビ被害
…
イギリスでも巻き起こるSNS論争|英国生活から考えるソーシャルネットワークの存在意義とテレビ離れ
…
イギリスで深まる子どものスマホ論争|SNSと自殺の関係・法改正の行方を徹底解説
…
イギリスの酸性雨で髪が薄くなる?傘をささない英国人の都市伝説を科学的に検証
…