
2025年、世界中がローマ教皇フランシスコの訃報に耳を傾ける中、イギリスではこの国際的ニュースに対する反応が極めて静かであった。宗教的、文化的に長い歴史を持つこの国が、なぜこうも冷静な態度を保ち続けたのか――その背景には、現代イギリス社会における深刻な宗教離れ、そして国民の精神的拠り所の変化がある。
■ 衰退する信仰心――数字に表れる宗教離れ イギリスの信仰人口は、近年急激に減少している。英国国家統計局(ONS)の調査によれば、2020年代初頭にはすでにキリスト教を自認する国民の割合は半数を割り込み、無宗教を選ぶ人々が過半数を超える結果が出ていた。特にZ世代やミレニアル世代では、「自分は宗教を持たない」と答える人の割合が70%を超えることも珍しくない。これは単なる一過性のトレンドではなく、イギリス社会の深層に根付いた価値観の変化である。
こうした傾向は、日曜礼拝の出席率や教会の活動への参加率にも如実に表れている。イングランド国教会の礼拝出席者数は20世紀後半以降、右肩下がりに減少しており、現在では人口のわずか1〜2%程度しか定期的に教会を訪れていない。地方の小さな教会では、維持費用の問題から閉鎖を余儀なくされるケースも増えている。
■ ローマ教皇という「遠い存在」 イギリスにおいて主流であるのはイングランド国教会であり、カトリック教徒は国内の宗教人口において少数派である。フランシスコ教皇の訃報は確かに国際ニュースとして各メディアで取り上げられたものの、多くのイギリス人にとってローマ教皇は日常生活とは無縁の存在だった。
この距離感には歴史的背景もある。16世紀、ヘンリー8世の時代にイングランドはローマ教皇庁から決別し、独自の国教会を設立した。以降、カトリックとプロテスタントの間には長きにわたる宗教的緊張と対立が存在しており、現代においてもその影響は完全には消えていない。
また、近年のイギリス社会においては、宗教指導者の発言がかつてほどの社会的影響力を持たない。政治、教育、家族、ジェンダーといった重要な議論において、宗教的価値観は徐々に背景へと押しやられ、より世俗的かつ個人主義的な価値観が主流になってきている。
■ SNSに映る冷静な反応 今回の教皇死去の報道に対し、イギリス国内のSNS上では限定的な追悼の投稿が見られたものの、大規模な議論や感情的な反応はほとんど確認されなかった。一部の政治家や宗教関係者が哀悼の意を示したほか、公共放送BBCなどが静かなトーンで報道したものの、国全体としての動きは極めて穏やかだった。
このような反応は、もはや宗教的出来事が「自分たちに直接関係のある問題」として受け止められなくなっていることを示している。かつてであれば、王室や政府が主導して追悼の声明を出したり、教会で特別ミサが行われるなど、宗教的な共同体としての振る舞いがあった。しかし現代のイギリスでは、そのような一体感は希薄になっている。
■ 宗教の代わりとなるもの――新たな精神的支柱の模索 宗教離れが進む中で、現代のイギリス人はどのような価値観を精神的支柱としているのか。社会心理学や宗教学の研究によれば、多くの人々は「自然とのつながり」や「マインドフルネス」、「ボランティア活動」などを通じて精神的な安定を得ているという。また、スポーツや音楽、アートといった文化活動も、コミュニティの結びつきを保つ重要な要素として機能している。
このように、宗教に代わる形で人々が「意味」や「絆」を求める動きは広がっており、現代のイギリス社会における新たなアイデンティティ形成のプロセスとも言えるだろう。
■ 教育と宗教――未来世代が選ぶ価値観 若年層における宗教離れの一因として、教育制度の影響も見逃せない。イギリスでは宗教教育が義務付けられてはいるものの、その内容は宗教的教義の伝達ではなく、むしろ多様性理解と価値観の共有に重点が置かれている。こうした環境下で育つ子どもたちは、宗教を絶対的な真理としてではなく、文化や歴史の一部として捉える傾向が強まっている。
■ おわりに――宗教の時代を超えて ローマ教皇の死という世界的出来事に対して、イギリスが静かであった理由。それは単なるニュースへの関心の低さではなく、社会全体が宗教と距離を置き、個々人が新たな精神的価値観を模索している過程の一端である。かつては教会が担っていた社会的、精神的役割が、現代では別の形へと移行しつつある。その静けさの中にこそ、現代イギリス社会の深層が映し出されているのだ。





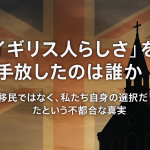

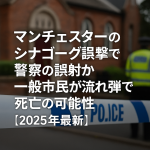


Comments