
建築法違反が「常態化」しているという衝撃
近年、イギリスにおいて建築法に違反したまま建設された集合住宅(いわゆる「フラット」や「マンション」)の数が、政府および独立調査機関の報告により明るみに出てきている。2023年末に公表された英政府の住宅・コミュニティ・地方自治省(DLUHC)の報告では、約1万棟以上の集合住宅が外壁材や断熱材の規定に違反しており、火災時の安全性に重大な懸念があるとされている。
これらの多くは2000年代から2010年代にかけて建設されたもので、一部はそれ以前の改修を経て現在に至る。イギリス全体の集合住宅のうち、約15%が何らかの形で建築基準(Building Regulations)に違反しているとの推計もある。
このような事態がなぜ放置されてきたのか。その背景には、建築資材の価格高騰、施工期間の短縮化、そして何より「利益至上主義」がある。
建築資材価格の高騰が引き金に
建設業界では、建築資材の価格が世界的に上昇している。イギリスも例外ではなく、英国建設製品協会(CPA)の2022年の調査によれば、過去5年間で鉄鋼やアルミニウム、木材、断熱材などの価格が平均で40〜70%も上昇している。
たとえば、火災防止用の耐火被覆材や外壁パネルの価格は、Brexit(英国のEU離脱)後の物流混乱やウクライナ戦争による供給チェーンの制約も相まって急騰した。特に、マンションの外装に使用されるアルミ複合パネル(ACM)は、価格が2015年比で約2倍となっている。
このような状況下で、施工主や開発会社は「いかに安く、早く建てるか」が最大の課題となっており、その結果、品質や安全性が犠牲になることも珍しくない。中には、正規品と偽って安価な建材を使用する事例も存在し、建築現場では見えにくい場所に違法建材が使われるケースもある。
“経費削減”という名の安全軽視
こうしたコストカットの典型例が、火災安全対策の手抜きである。通常、イギリスの建築法では、集合住宅には一定以上の耐火性能を持つ外壁材や断熱材、防煙システムが求められる。しかし、それらの要件を満たす建材は高額で、施工や検査にも時間がかかる。
一部の施工主や開発業者は、「見た目」や「規格には似ているが実際には基準を満たしていない材料」を用いることでコストを削減してきた。検査の目をすり抜けるために、施工後の写真や書類上では正規の建材が使用されているように見せかける不正も横行していたという。
特にグレンフェル・タワー火災以降、こうした「隠れた違法建材」が多数発見されるようになり、政府は大規模な検査と改修プログラムに乗り出すこととなる。
グレンフェル・タワー火災──最悪の結末
2017年6月14日、ロンドン西部ノースケンジントンにあるグレンフェル・タワーで大規模な火災が発生。建物は24階建て、120世帯が暮らす公共住宅だった。火災は深夜1時頃、4階の冷蔵庫が発火源とされているが、その後、火は外壁を伝って急速に上層階へと広がった。
この火災によって、72人が死亡、70人以上が負傷するというイギリス史上でも最悪級の住宅火災となった。
後の政府調査によれば、外壁に使用されていたACMパネルは、建築法で求められる耐火性能を満たしていなかったばかりか、火災時に高温で燃え広がりやすい「可燃性素材」であった。しかも、この建材は2016年の改修工事で取り付けられたもので、設計段階での不備と、施工業者による手抜き、そして行政の検査不足が重なった「人災」であったことが判明している。
「なぜ違法建材が使われたのか」徹底分析
グレンフェル火災を受けて発足した「グレンフェル調査委員会(Grenfell Tower Inquiry)」は、膨大な証拠と証言を集め、なぜ違法建材が使われ、誰がその責任を負うべきかについて詳細な報告をまとめた。
調査によれば、問題の建材は「Reynobond PE」と呼ばれるアルミ複合パネルで、その中心にポリエチレン(可燃性プラスチック)を使用していた。これはドイツやアメリカではすでに高層住宅への使用が制限されていたにもかかわらず、イギリスでは明確な法規制がなかった。
また、設計会社や施工業者、監理会社、ケンジントン&チェルシー区議会などの関係者が、すべて「他人任せ」で安全性を確認しなかったことが、火災拡大を招いたとされる。
報告書では、「利益とコスト削減を優先し、住民の安全は後回しにされた」という指摘がなされている。
法改正とその後の対応
グレンフェル火災以降、イギリス政府は建築基準法の見直しを進め、2022年には「Building Safety Act(建築安全法)」が成立。これにより、住宅の設計・建築・改修において、より厳格な耐火基準が義務化され、建築監理の責任も明確化された。
また、問題のある建材を取り除くための改修助成制度も開始され、2024年時点で2,000棟以上の高層住宅が外壁改修の対象となっている。
しかし、これらの対策は「後手に回った」との批判も多く、いまだに5,000棟近い建物が可燃性建材を使用しており、住民からの不安の声は絶えない。
世界に広がる「隠れた違法建築」の恐怖
グレンフェル火災はイギリスだけの問題ではない。日本、中国、インド、アメリカなどでも、安価な建材を用いた違法建築が多数存在すると言われている。特に都市部では、地価や建設費の高騰が著しく、施工主が利益確保のために安全性を犠牲にする事例は後を絶たない。
建物というのは、一度完成してしまえば、その内部構造や使用資材が外から見えにくくなる。ましてや、事故が30年起きなければ「安全だった」と見なされ、真実が埋もれてしまう構造がある。これは世界共通のリスク構造だと言える。
終わりに──「誰のための建築なのか」を問う
グレンフェル火災は、私たちに改めて「誰のために建物を建てるのか」「安全とは誰が守るべきものなのか」を問い直させた。
建築とは単なる「モノづくり」ではなく、「命を守るための構造物」である。施工主も、設計者も、行政も、そして住民自身も、建物の安全性について主体的に関わる必要がある。
目に見えない建材の一つ一つが、人の命を左右する──そんな事実を、私たちは決して忘れてはならない。








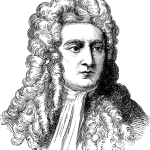

Comments