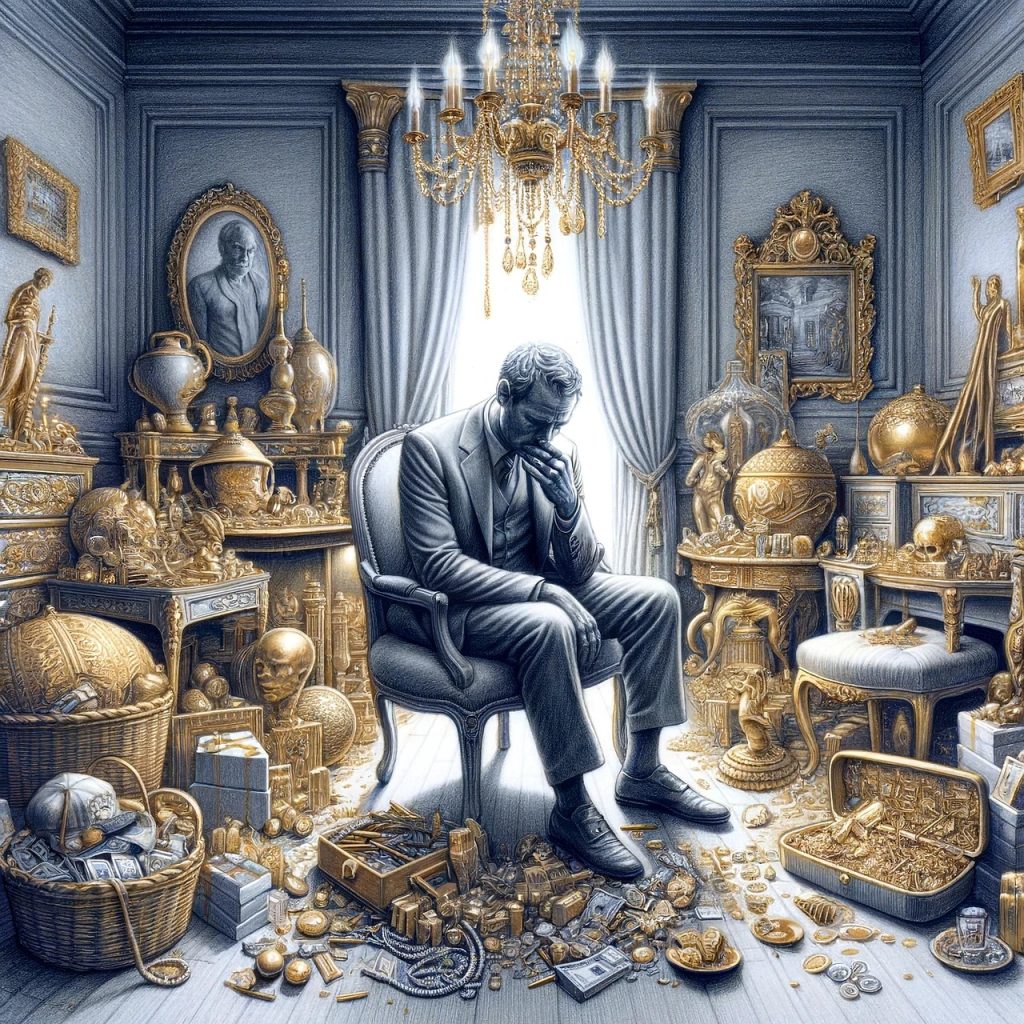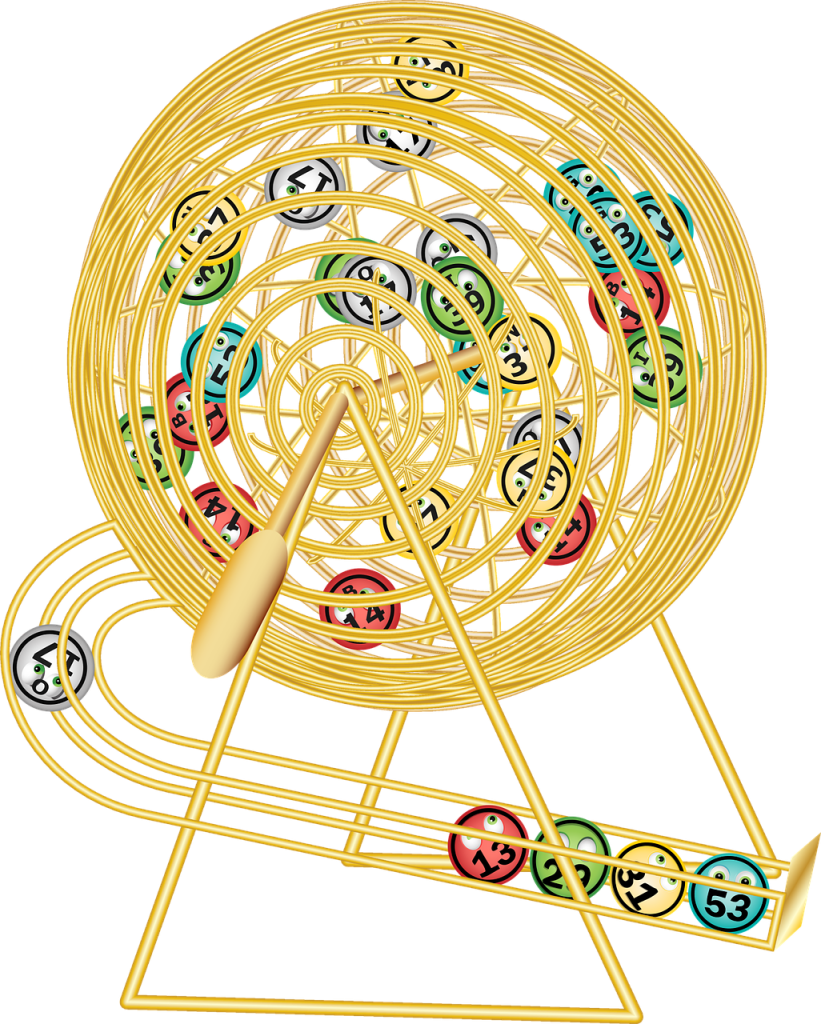…
Month:March 2025
【特集】イギリス人女性が語る「日本人男性との恋愛」:その魅力とギャップのリアル
…
なぜイギリスは酒好きが多いのに飲み放題がないのか?イギリス人が日本の飲み放題に行ったらどうなるのか
…
「日本の桜はイギリスから来た」は本当か?——歴史と科学から徹底検証
…
イギリスのオーガニック野菜:栄養価は高いが「見た目」で損をする理由とは?
…
富豪が逃げ出す国、イギリス:税制が生む「金持ち離れ」の現実
…
イギリス人は実はあまり食べない?——English Breakfastの本当の姿と、和食を求める日本人との共通点
…
宝くじで億万長者?日本とイギリス・欧州のスケール差に愕然
…
イギリスの料理はなぜまずいといわれるのか?
…
【保存版】イギリスの人気デザートランキングTOP10|プディング文化と伝統スイーツまとめ
…