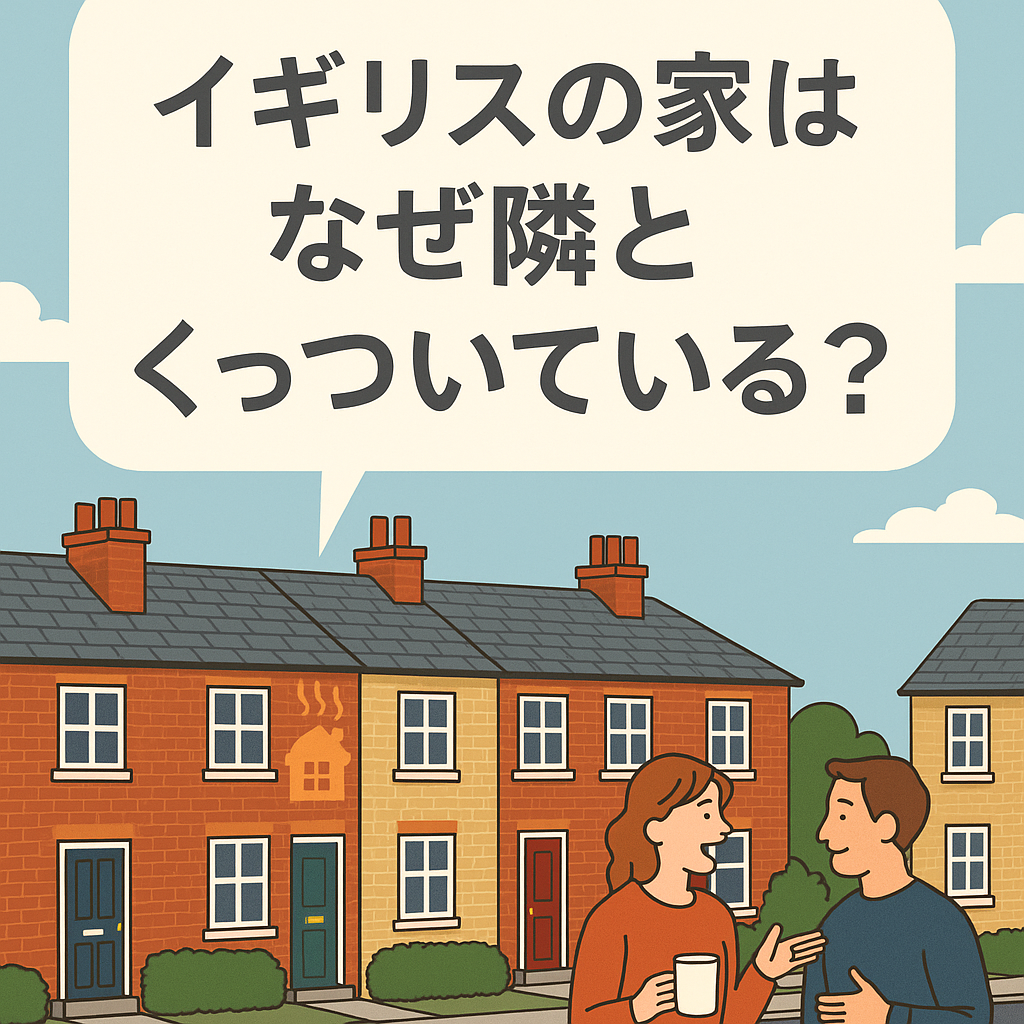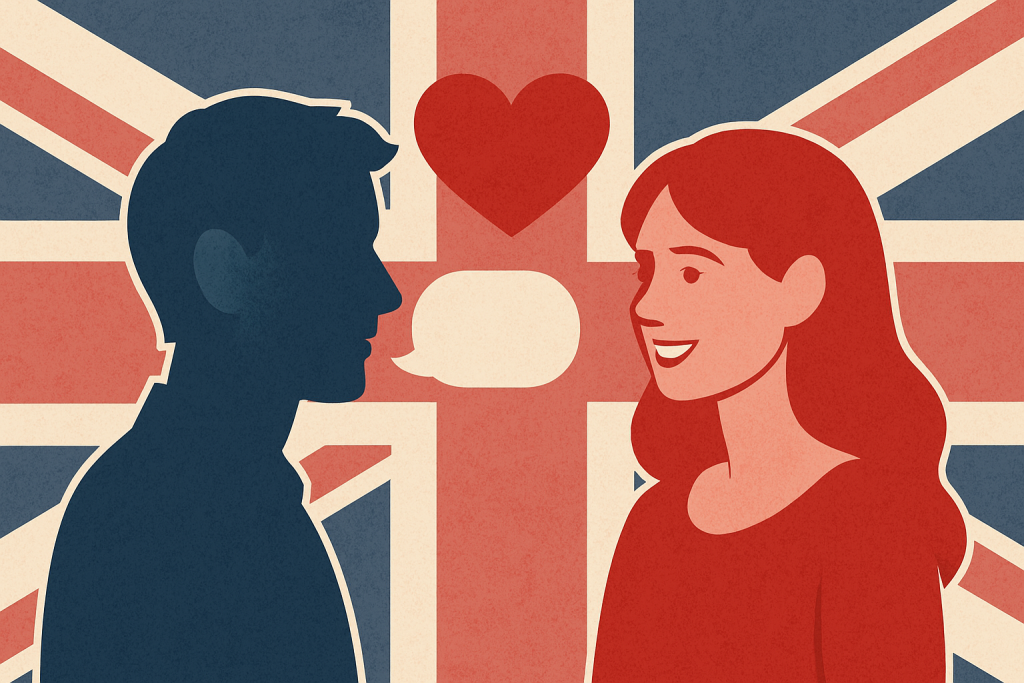…
Author:admin
イギリス人男性との恋愛完全ガイド|文化ギャップを超える秘訣と他では聞けないアドバイス
…
イギリス旅行で役立つ生活の知恵|観光から日常まで安心して楽しむための実践ガイド
…
英国街歩き完全ガイド|ロンドン・オックスフォード・コッツウォルズまで歩いて楽しむ観光と暮らしの魅力
…
英国の割り勘・支払いマナー完全ガイド|イギリスでの食事・デート・パブで失敗しない心得
…
イギリスのマーケット完全攻略ガイド|観光から日常まで楽しむ買い物と歩き方
…
英国パブ文化の楽しみ方完全ガイド|初心者でも安心の注文方法・マナー・おすすめ体験
…
イギリスで極右デモの最中も小型ボート不法入国が加速―先週だけで1,899人【最新データ】
…
イギリス人男性が好きな女性のタイプ3選|恋愛観と文化背景から解説
…
ロンドンの最新生活費2025|家賃・食費・交通・光熱費の完全ガイド
…