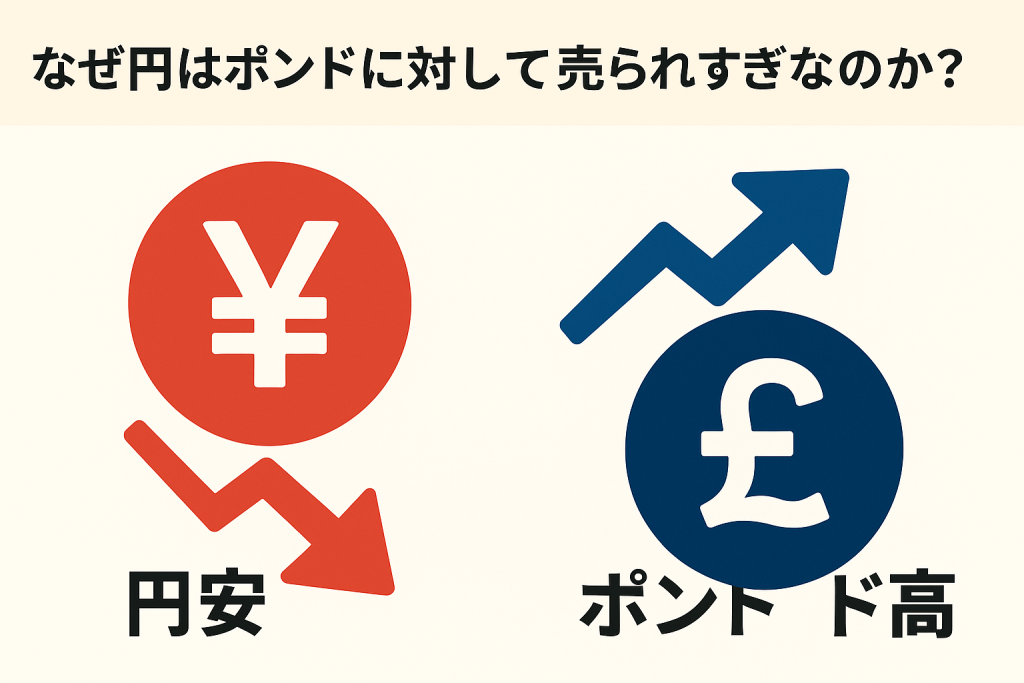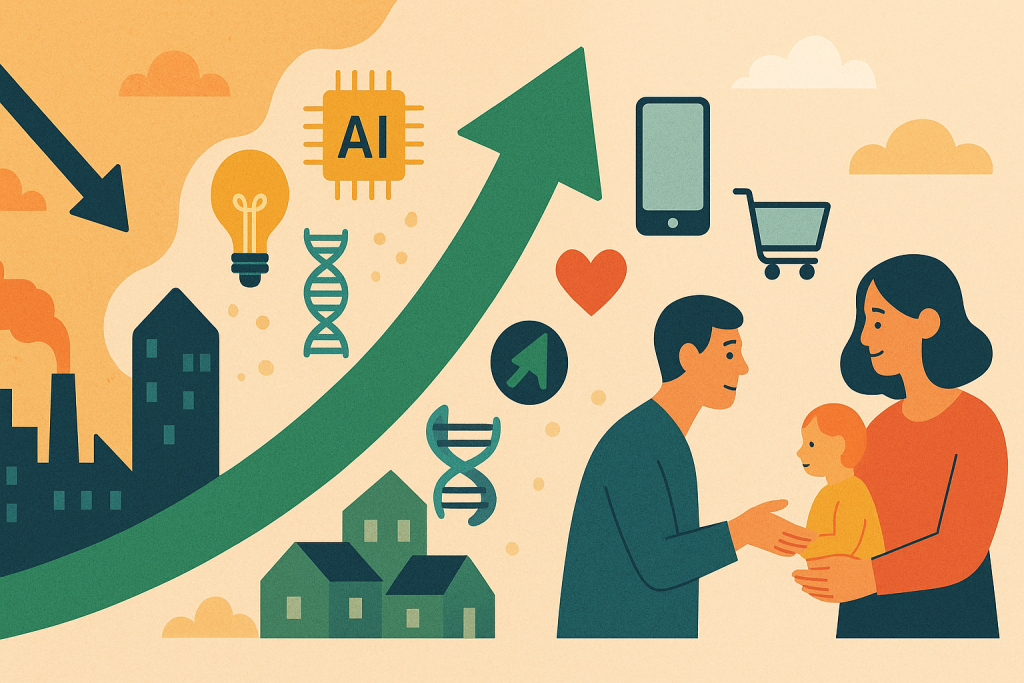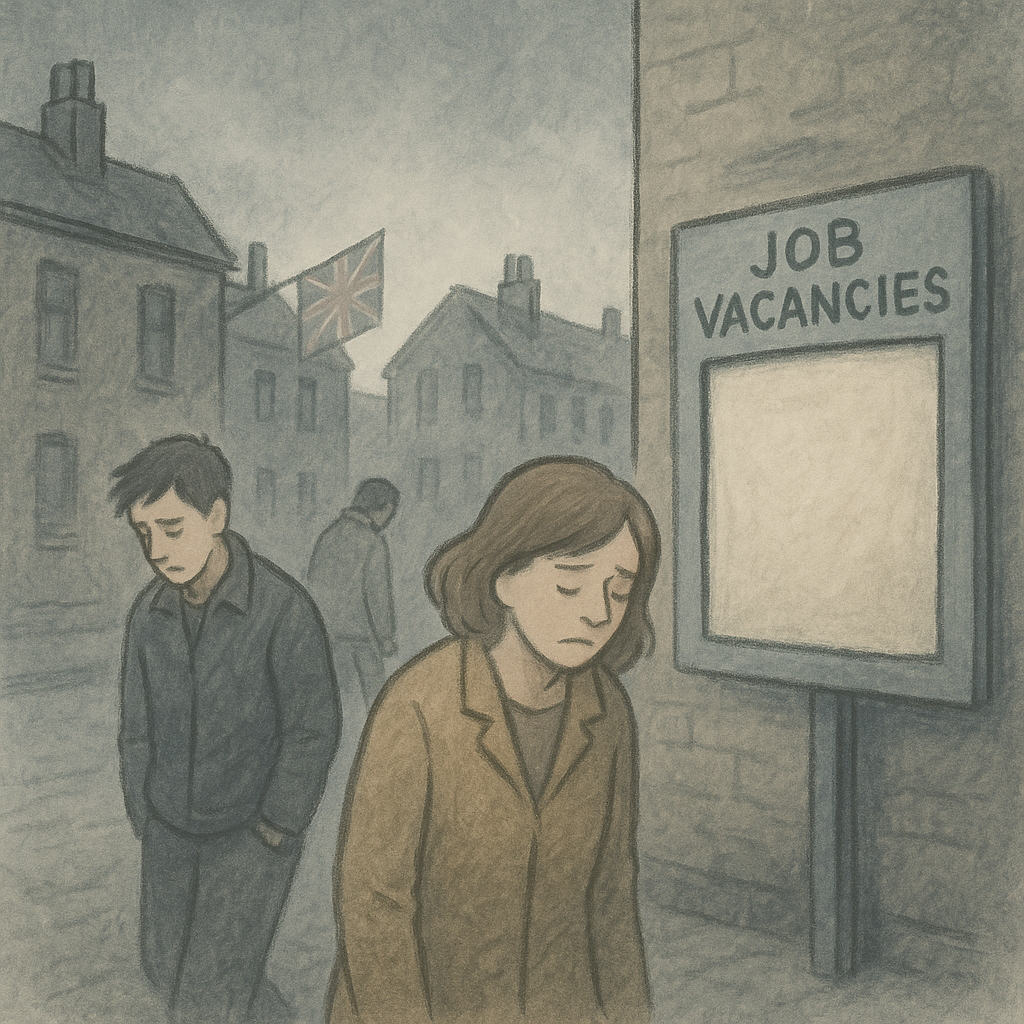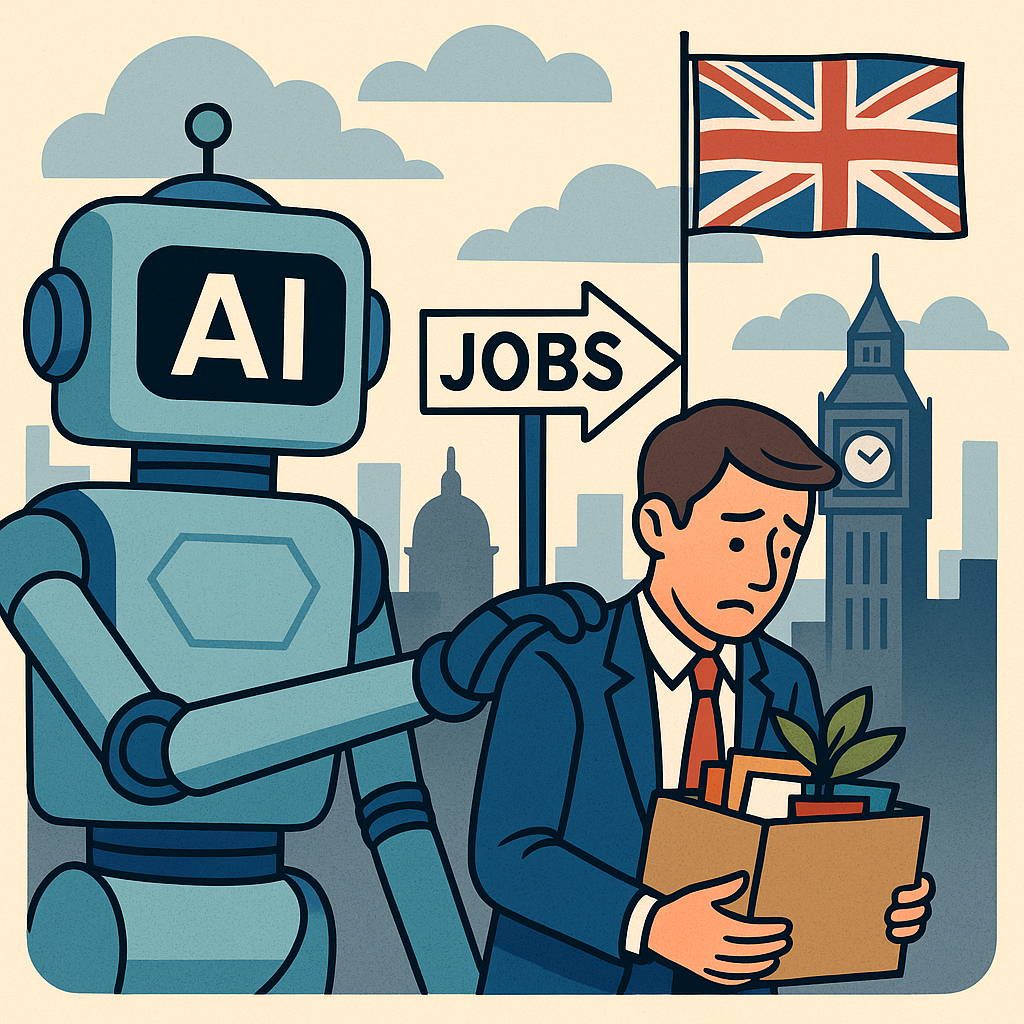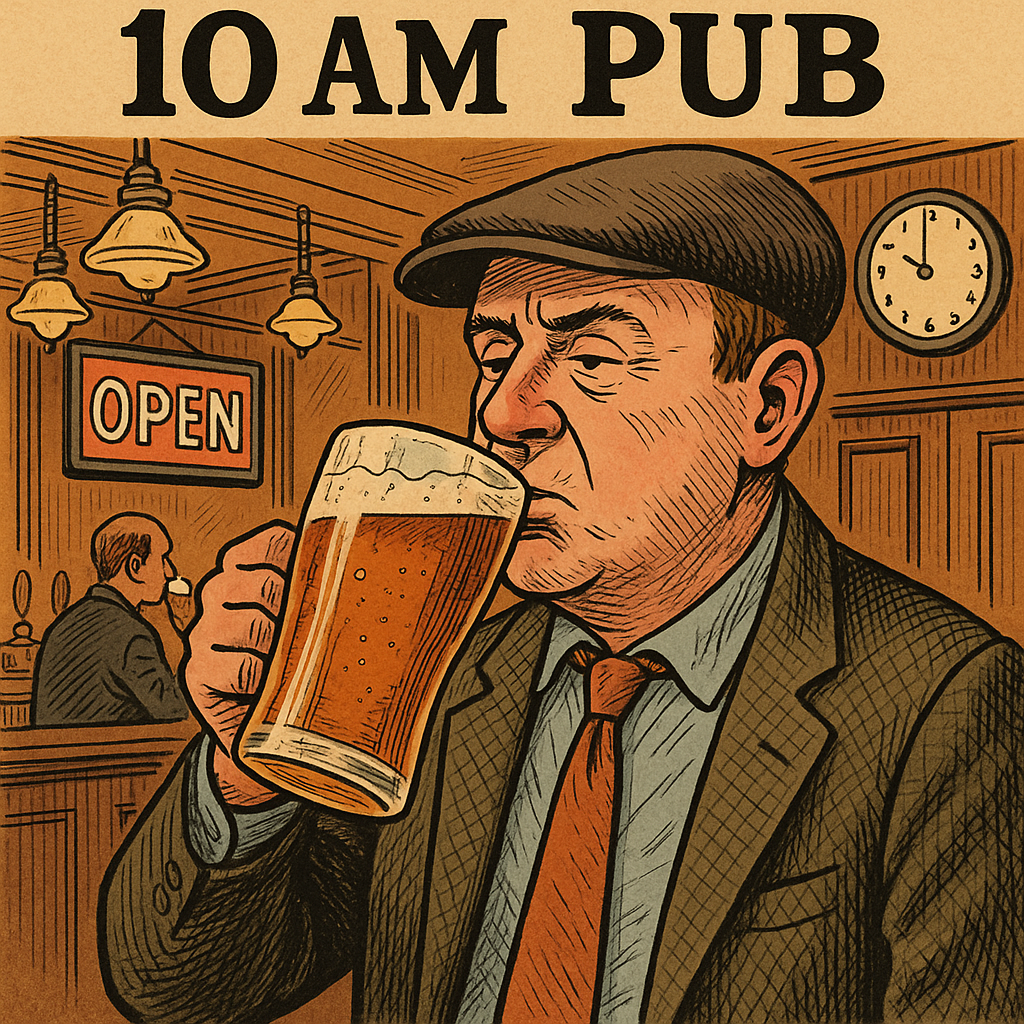…
経済
イギリスは中国にどの程度依存しているのか
…
なぜ円がポンドに対して「売られすぎ」なのか?
…
イギリスが挽回するために必要なこと
…
英国生活サイトが考える経済の成長について
…
イギリスのスーパーで見つけた、この国がかなり悪い方向に向かっているというサイン
…
イギリスで人種差別的なコメントを耳にすることが増えた理由
…
イギリスで深刻化する雇用危機:失業率上昇と相次ぐ人員削減の現実
…
AIが奪うのは単純労働ではない――イギリス労働市場の変化
…
ロンドン賃貸市場に「失速」の兆し
…
なぜロンドン株式市場は地味に見えるのか?|ニューヨーク・東京が活況の中で遅れを取る理由【2025年最新版】
…
朝10時にパイントを──英国という名の液体燃料社会
…