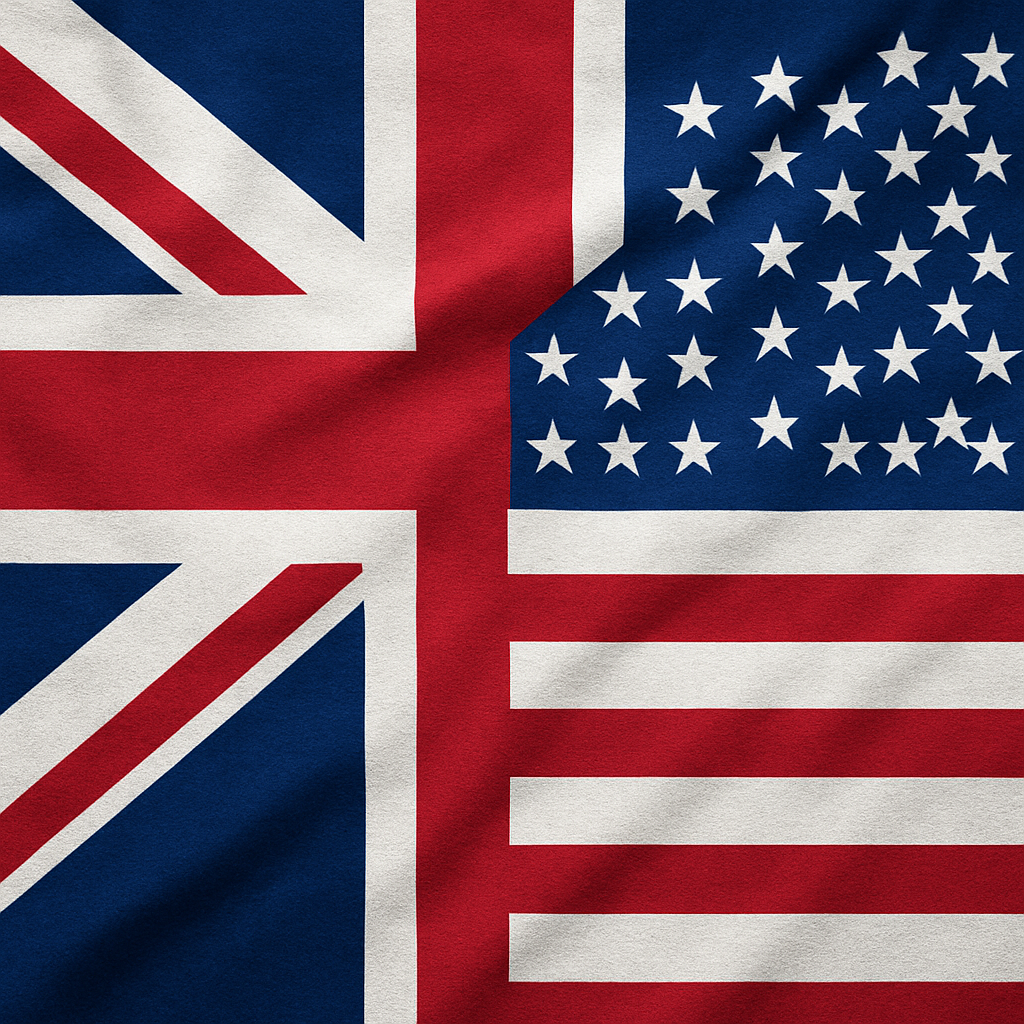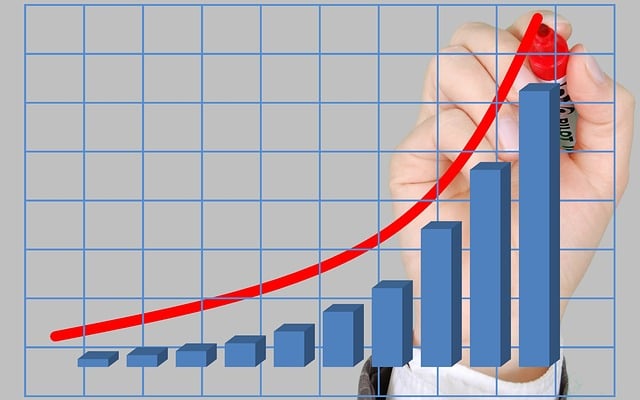…
経済
AI時代における雇用構造の転換:イギリス労働市場の未来を読む
…
英米貿易協定「合意済み」とは何を意味するのか?――舞台裏と今後の展望
…
地下トンネルの英国──格差社会の迷宮を抜け出すために
…
イギリスのスーパーマーケットに潜む「割引表示の罠」― 消費者心理を突いた巧妙な価格戦略の実態 ―
…
イギリスは何を生産しているのか?
…
イギリスに成金が少ない本当の理由――今なお社会に根を張る階級制度の実像
…
イギリス富裕層の資産シフト:仮想通貨と株式への移行、その背景と未来展望
…
「ジュースより安いビール」から見える、ロンドンの物価高騰と生活感覚の揺らぎ
…
「歴史的」米英貿易協定の実態──華やかな発表の裏に潜む英国の課題と展望
…
速報:イギリスここにきてインフレ率上昇
…
イギリスの商店街衰退と郊外型ショッピングモール繁栄の背景と今後の展望
…