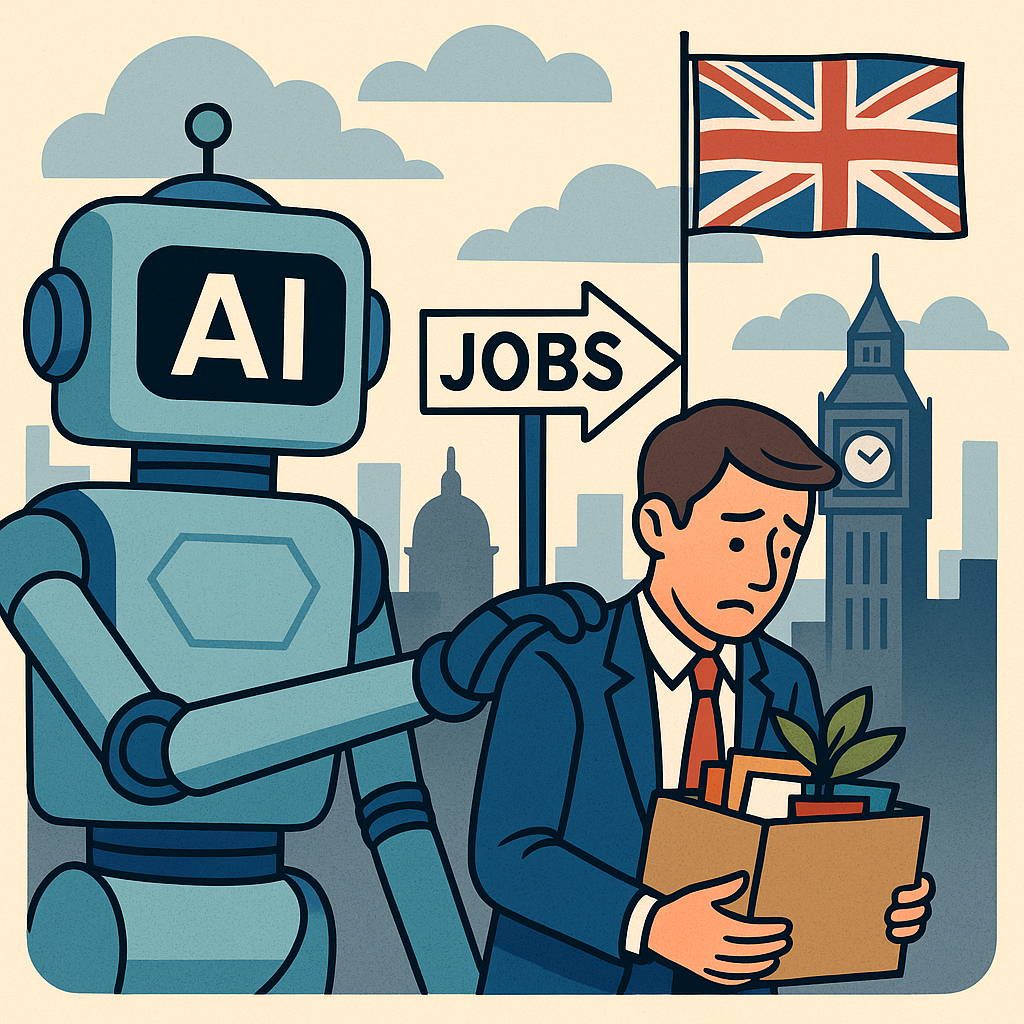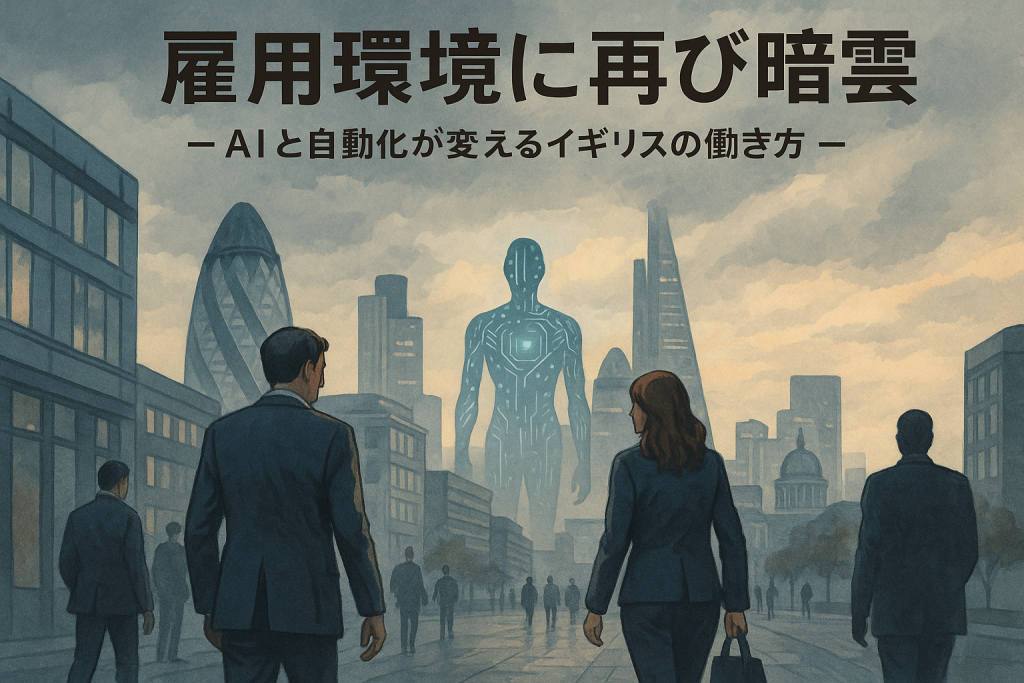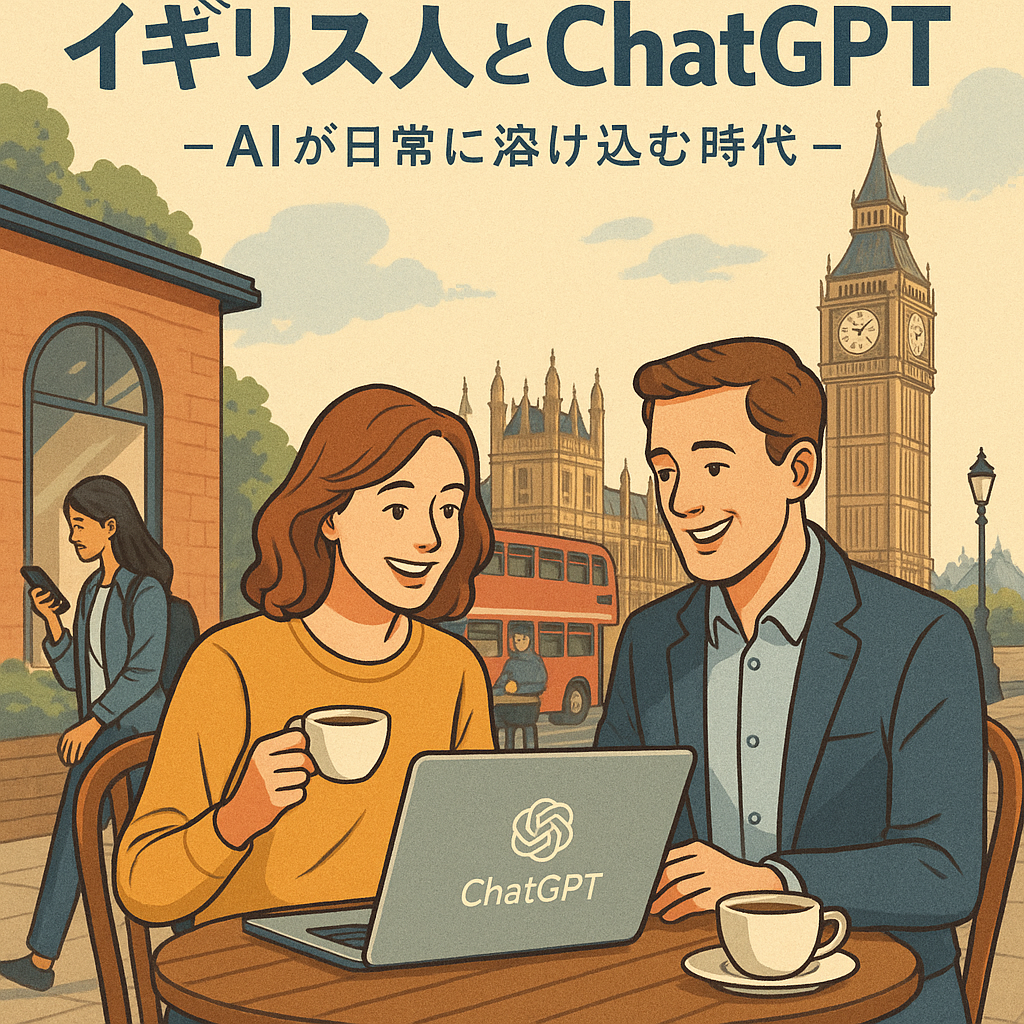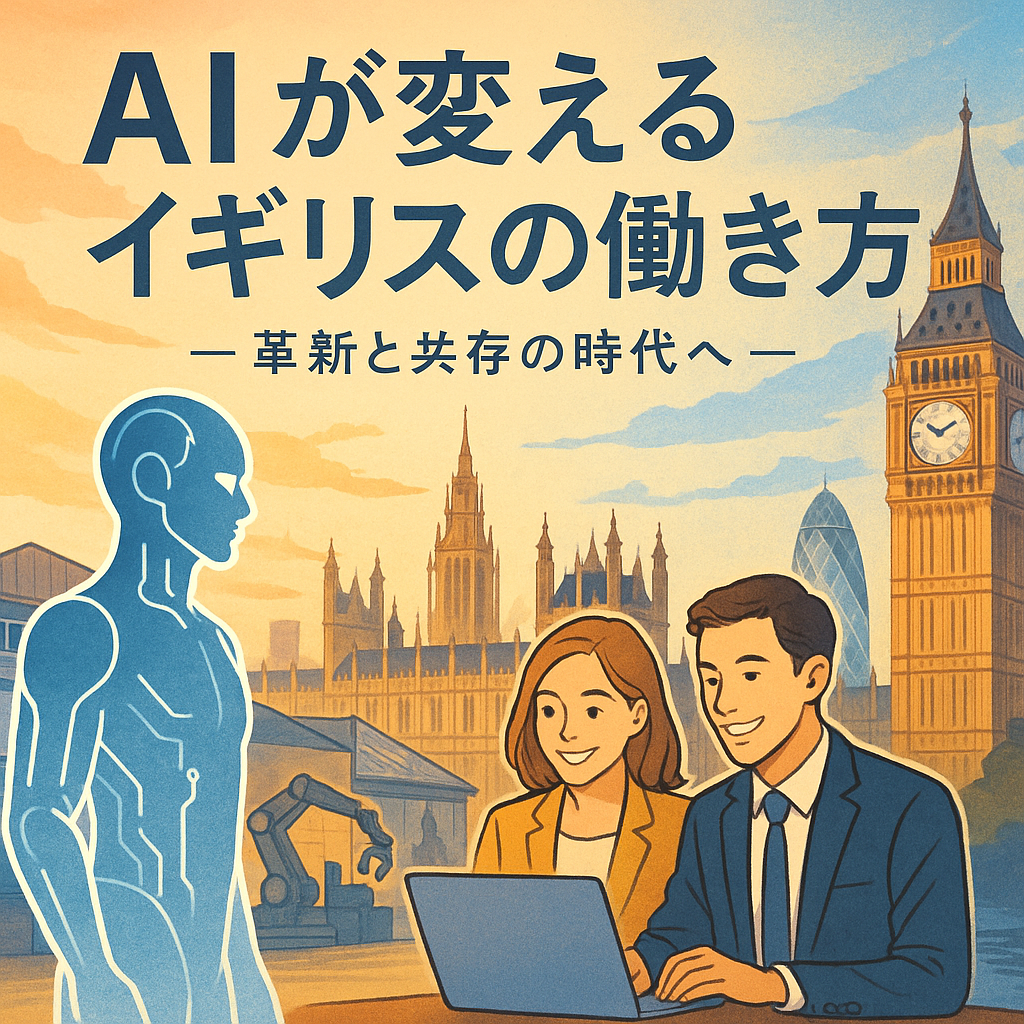…
仕事
イギリスで働くために必要な情報を幅広く紹介しています。現地就職や転職活動のコツ、ワークビザ取得の流れ、職場のマナーやカルチャー、さらにはフリーランス・リモートワークの実情まで。実際に現地で働く日本人の体験談を交えながら、リアルな働き方をわかりやすく発信しています。イギリスでキャリアを築きたい人、挑戦を考えている人のための実践的な仕事ガイドです。
イギリス人は誕生日に仕事を休む?
…
AIが奪うのは単純労働ではない――イギリス労働市場の変化
…
紳士的カオス──イギリス企業という名の「優雅な混沌」
…
雇用環境に再び暗雲 ― イギリスで進むAI導入と人員削減の現実
…
イギリス人とChatGPT|生活に溶け込むAI革命と新しい日常
…
AIが変えるイギリスの働き方|人件費削減と世代間の反発を超えた新しい未来
…
日本とイギリスの働き方を徹底比較|価値観・制度・休暇の違いを解説
…
イギリスの働き方改革とは?ワークライフバランスの本質を徹底解説|制度・文化・日本との違い
…
イギリスの会社では有休をすべて使うのは当たり前|有給休暇制度・文化・日本との違いを徹底解説
…