
「土地は誰のものか?」
この問いは、国家の歴史や文化、そして国民の自由度を浮き彫りにする。そして、世界の中でも特にこの問いに対して「深くて奇妙な答え」を持っている国のひとつが、イギリスである。
イギリスといえば、かつて七つの海を支配した大英帝国。近代議会制民主主義の発祥の地であり、科学や経済、文化の分野でも世界に大きな影響を与えてきた。そんなイギリスが、実は「封建制度の亡霊」にいまだ悩まされていると聞けば、多くの人は驚くだろう。ところが、それが現実なのだ。
今回は、イギリス社会に根付く「土地を所有する」という概念の不思議さと、それにまつわる信じがたいほど非効率な官僚制度、そしてその象徴としての「庭の木一本すら勝手に切れない」制度について、深掘りしていこう。
見た目はモダン、内実は中世
観光地としてのイギリスは美しい。ロンドンの洗練された都市風景、整備された庭園、歴史ある建物。どこを見ても「近代国家」である。だが、生活者としてそこに住むと、次第にその美しい外観の裏にある、古臭い制度と矛盾だらけのルールの数々に気付くようになる。
その一つが、「自分の家の木を勝手に切れない」という、一見信じがたい制度だ。
Tree Preservation Order(TPO)という名の木の特権
イギリスでは「Tree Preservation Order(以下TPO)」という制度がある。これは直訳すれば「樹木保存命令」。一度この命令がかけられた木に対しては、たとえそれが自分の敷地内にあろうとも、切ることはもちろん、枝を払ったり、根をいじることすらできなくなる。
驚くのはその対象範囲の広さと曖昧さだ。古い屋敷の裏庭にある立派な樹木から、ただ伸びすぎた街路樹のような木まで、多くの木がこのTPOの対象になっている可能性がある。そしてこれを判断するのは地元の役所。彼らが「価値あり」と判断した瞬間、その木はあなたのものではなくなる。
あなたがどれだけ「危険だから切りたい」と主張しても、「景観上価値がある」「生態系への影響が大きい」と判断されれば、すぐに却下される。しかも、違反すれば罰金が科される。その額はなんと20,000ポンド(約400万円)にもなるケースもある。
まさに「木のほうが人より偉い」ような世界である。
「所有」ではなく「借りている」というイギリス流土地観
この奇妙な制度の背後には、イギリス独特の土地観がある。日本では家を買えば、そこにある土地も「自分のもの」と考えるのが一般的だ。ところが、イギリスでは話が違う。
イギリスにおける土地の所有形態には、主にFreehold(自由保有権)とLeasehold(借地権)という2つがある。
- Freeholdは比較的日本の所有権に近いが、完全な自由があるわけではない。
- Leaseholdに至っては、実際には王室や教会、地主階級から土地を「借りて」いるという形だ。
このLeaseholdの契約期間は、一般的に99年、125年、場合によっては999年などさまざまで、契約満了後は地主に返還される可能性がある。つまり、あなたが高い金を払って買った家であっても、「期限付きの居候」という立場に過ぎないのだ。
「自分の土地なのに自由がない」という不条理
このように、形式的には自分の土地であっても、イギリスでは「社会全体の合意」や「歴史的背景」によって、その利用が大きく制限される。
特に都市部では「保存地区(Conservation Area)」の指定を受けている場合も多く、その場合は家の外観を変更するのにも許可が必要。窓を変えたければ申請、門を直したければ申請、もちろん庭の木を切るのにも申請…。
まるで「あなたの土地はあくまで貸してあげているだけ。勝手にいじらないでね」という、お上からの無言の圧力である。
官僚主義の極み:「申請すれば何でも通る」とは限らない
さらに厄介なのは、申請をしても通るとは限らないという点だ。自治体や市役所に申請を出したとしても、それが審査され、結果が出るまでに数週間〜数ヶ月かかることも珍しくない。
その間に木が腐って倒れてしまったら? 近所の家に被害を及ぼしたら? それでも「勝手に切ったら罰金」です。
こうなると、市民の間には「だったらもう放っておこう」「なるべく何もしないようにしよう」という心理が働く。これこそが、「やる気を削ぐ社会構造」であり、イギリス特有の「保守的な国民性」を育ててきた一因とも言えるだろう。
土地の自由がなければ、発想も発展もしない
土地や不動産の自由度は、その国の経済的ダイナミズムを大きく左右する。新しいビジネスを始める、街を開発する、新しい家を建てるといった活動は、基本的に「所有の自由」あってこそ成り立つ。
ところがイギリスでは、ちょっとした増築や庭の手入れすらも「申請」と「許可」が必要となる。このような制度が、結果的に創造性を阻み、経済の停滞を助長していると感じるのは筆者だけではないだろう。
「官僚主義」と「階級意識」の残滓
この制度の根底にあるのは、イギリス社会に今なお残る階級意識である。土地の大半はいまだに、貴族や王室、教会といった“伝統的な権力者”によって保有されている。
そして、庶民がその土地にアクセスするには、「借りる」という形を取らざるを得ない。役所や地方自治体は、その管理人に過ぎないが、時にはその判断が庶民の生活を大きく左右する。
要するに、イギリスではいまだに「庶民が自由に土地を使う」ことは、完全には認められていないのだ。
まとめ:進んでいるようで、どこか止まっている国
イギリスは、見た目は近代国家でありながら、制度の中身はどこか中世のまま。美しく整った街並みの裏には、時代錯誤の制度と、自由を奪われた生活が存在する。
もちろん、自然や景観を守るという理念そのものは否定しない。しかし、それを守るために人間の暮らしが不便になり、萎縮し、発展が妨げられるのであれば、本末転倒ではないだろうか。
庭の一本の木を切るためにお伺いを立てねばならない。そんな社会に、果たして「個人の自由」や「自立した市民」は根付くのだろうか?
イギリスの不思議な土地制度は、そうした問いを現代の私たちに突きつけてくる。
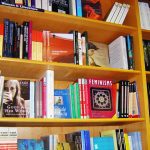









Comments