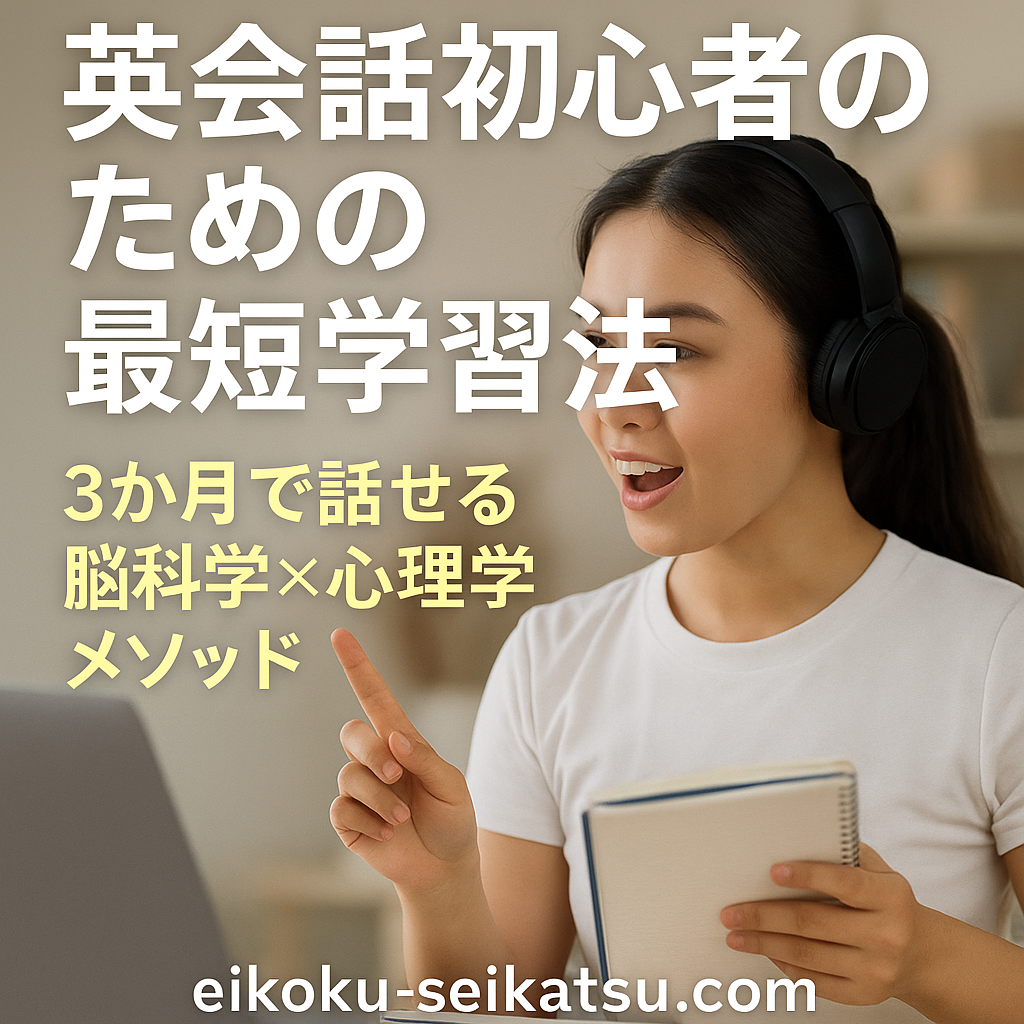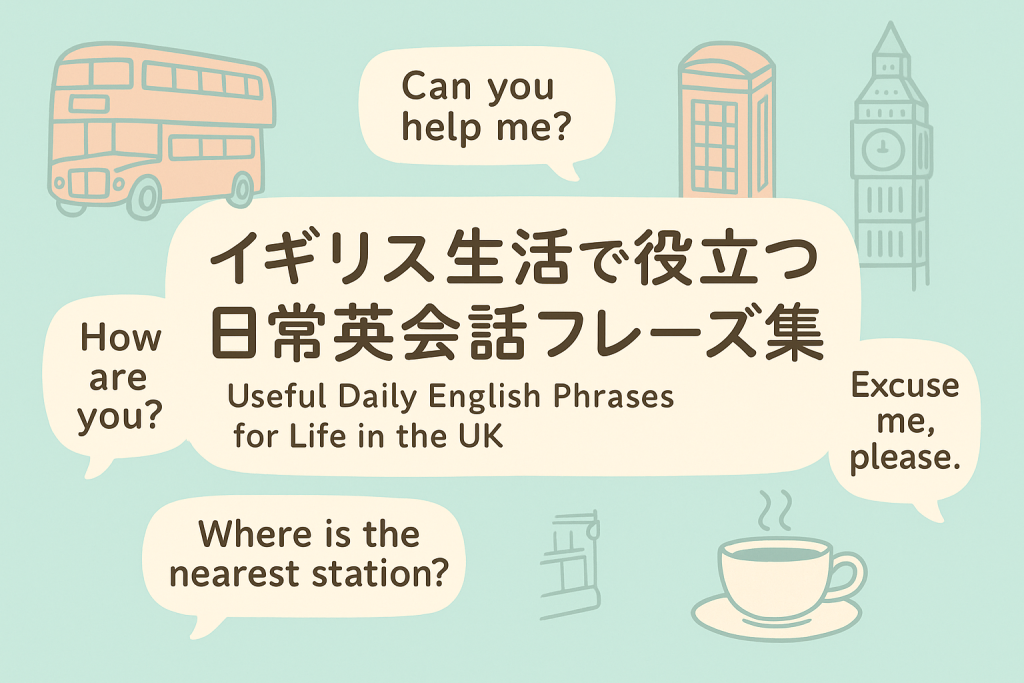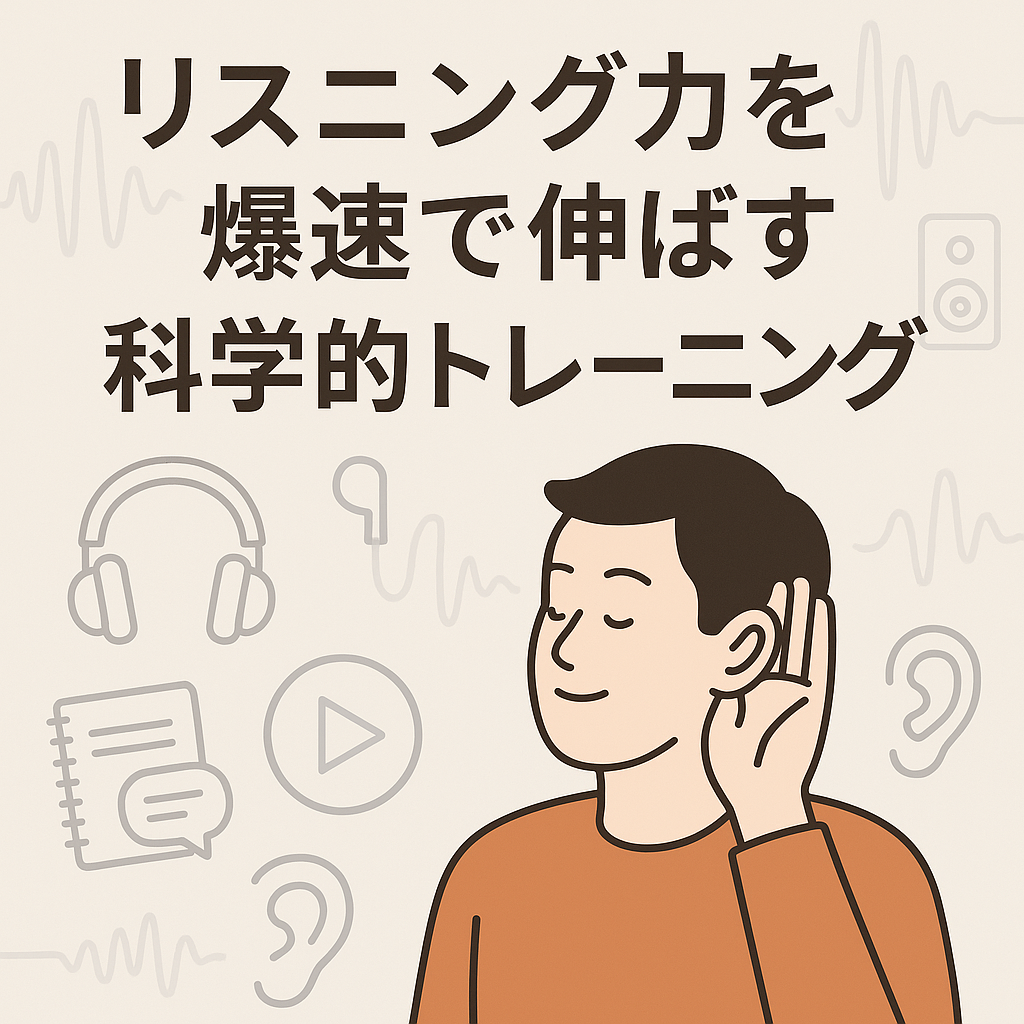…
Author:admin
英語が話せなくてもイギリス人の彼氏・彼女を作る方法|心理学×科学で長続きする恋愛術
…
英会話初心者のための最短学習法|3か月で話せる脳科学×心理学メソッド
…
イギリスと日本の文化ギャップを乗り越える方法|心理学×文化人類学で学ぶ相互理解のコツ
…
遠距離恋愛で絆を深めるコミュニケーション術|心理学×科学が教える長続きの秘訣
…
イギリス生活で役立つ日常英会話フレーズ集|現地で通じるリアル英語と文化マナー
…
リスニング力を爆速で伸ばす科学的トレーニング法|脳科学×心理学で英語が聞こえる耳を作る
…
イギリス生活で役立つ文化マナーと日常英会話|現地で信頼される話し方とリアルフレーズ集
…
イスラエル野党党首がAI・半導体への国家投資を宣言|英国経済にも波及、ロンドン・ケンブリッジで進むテック連携
…
英国AI戦略とスタートアップ支援の現状|スターマー政権が描くテック国家の未来
…