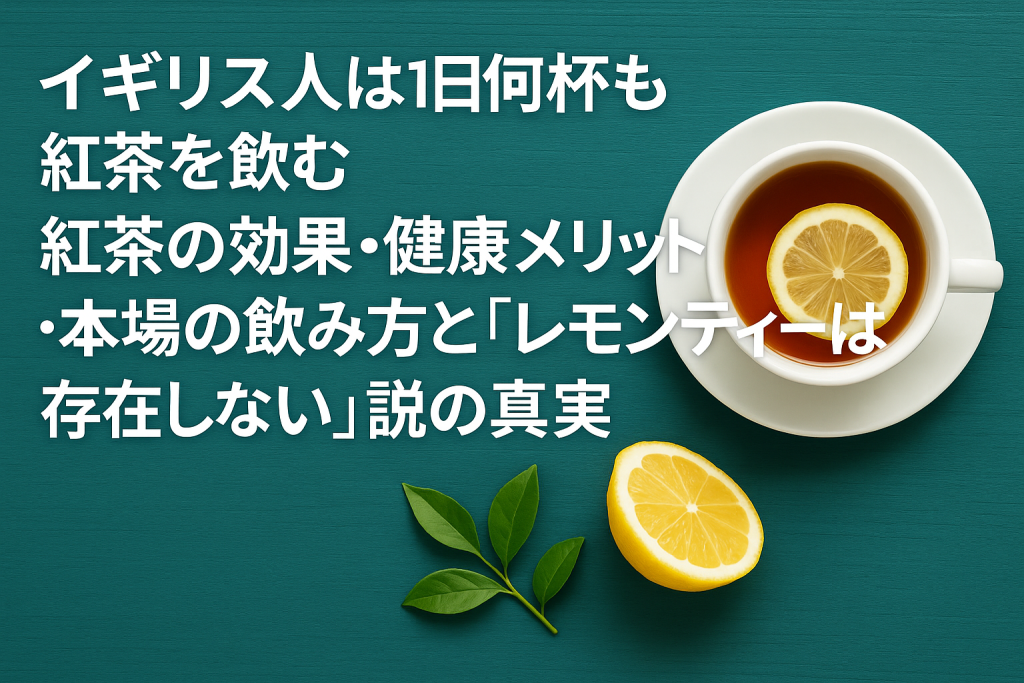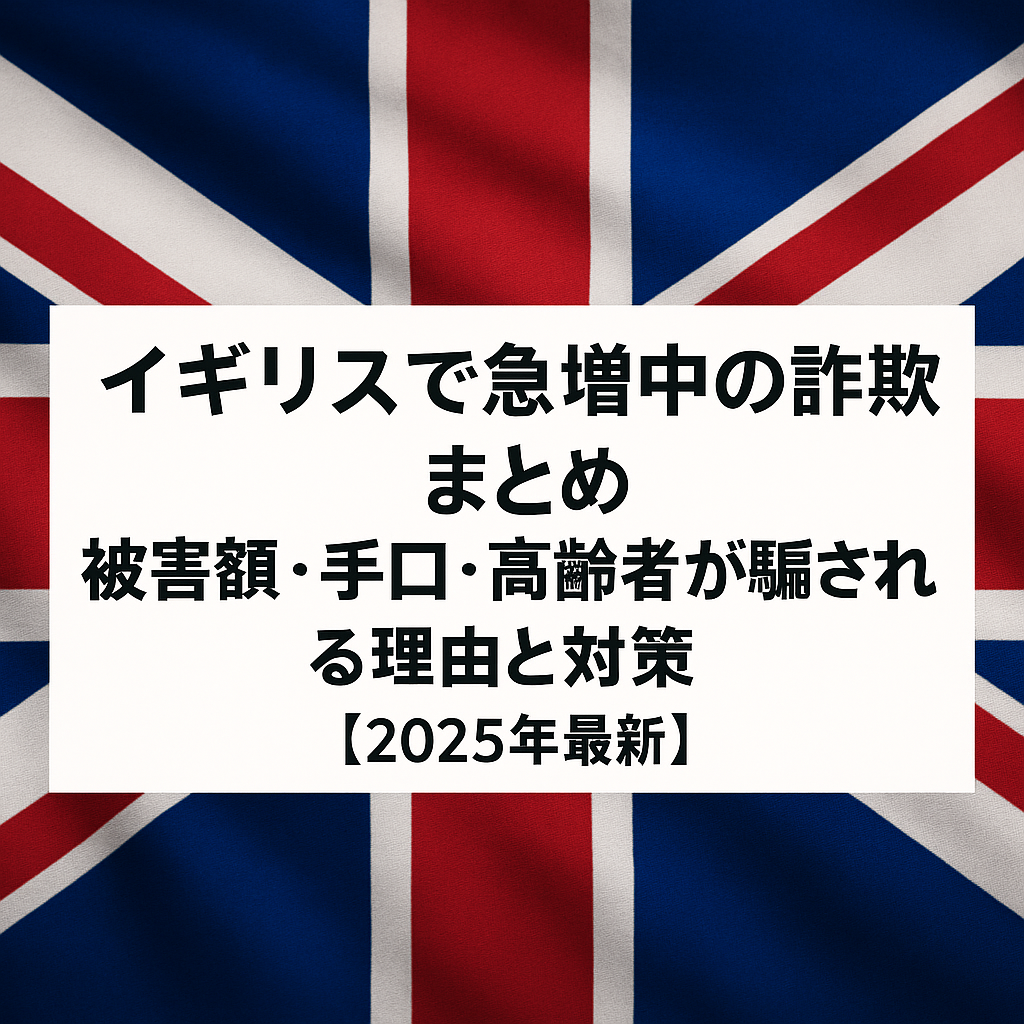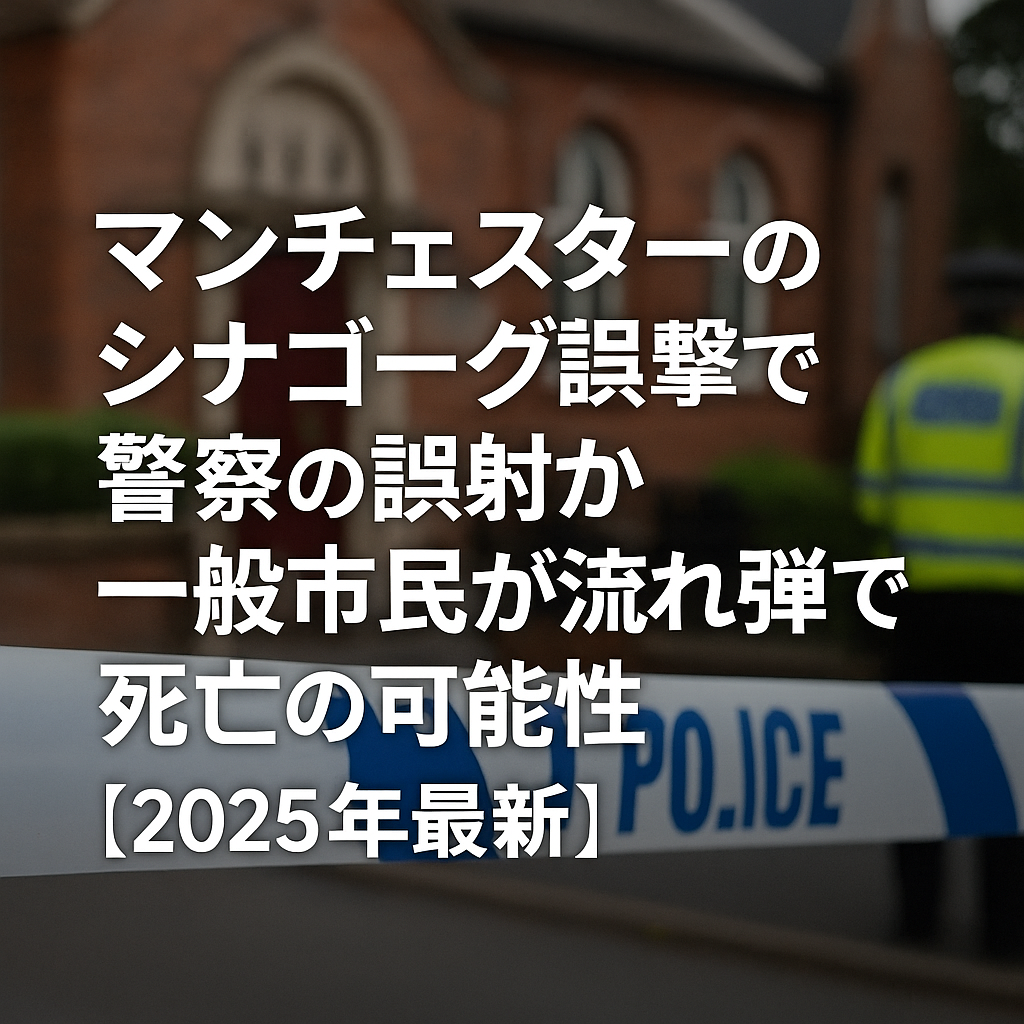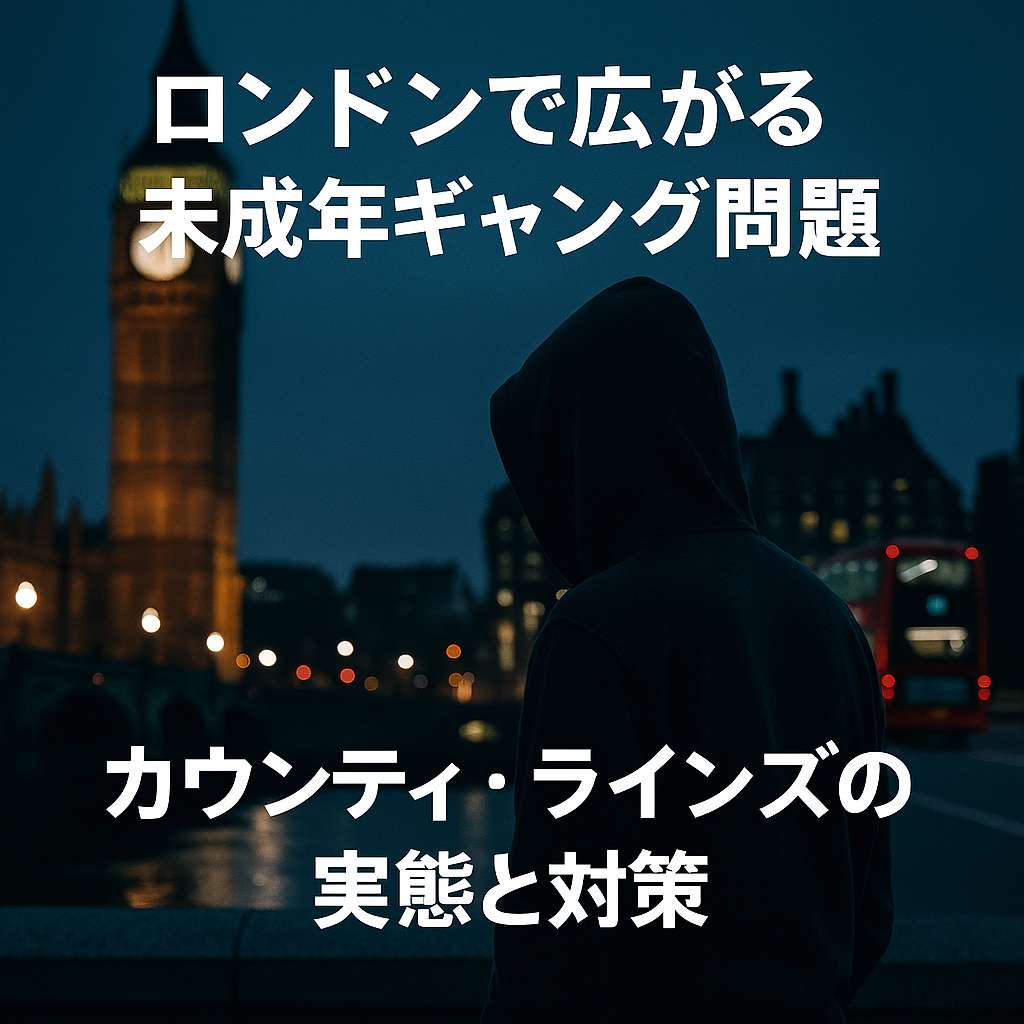…
Author:admin
イギリスで急増中の詐欺まとめ|被害額・手口・高齢者が騙される理由と対策【2025年最新】
…
マンチェスターのシナゴーグ襲撃で警察の誤射か 一般市民が流れ弾で死亡の可能性【2025年最新】
…
イギリスで宗教や人種差別による攻撃から外国人が身を守る方法【ヘイトクライム対策ガイド】
…
イギリスの避難民受け入れ:年間の人数・国家予算・一人当たりコストの実態
…
【2025年最新版】英国ビザの主な変更点まとめ|スキルドワーカー・家族・学生・訪問・医療従事者
…
イギリス人が怒る英語表現7選|絶対に言ってはいけないフレーズと文化的背景
…
イギリスのエール種類一覧|ビター・IPA・スタウトまで魅力を徹底解説
…
ロンドンで広がる未成年ギャング問題|カウンティ・ラインズの実態と対策
…
イギリスの人気タバコ銘柄一覧|ニコチン・タール量と健康被害の実態【2025年最新】
…