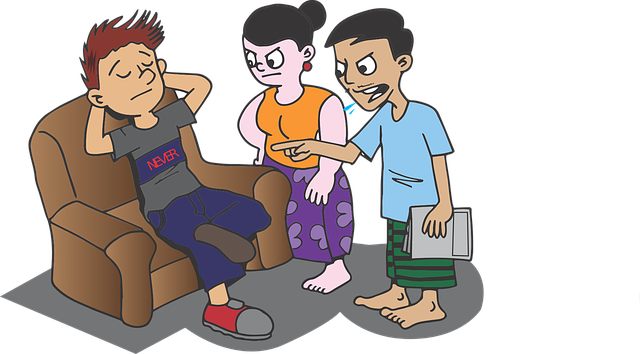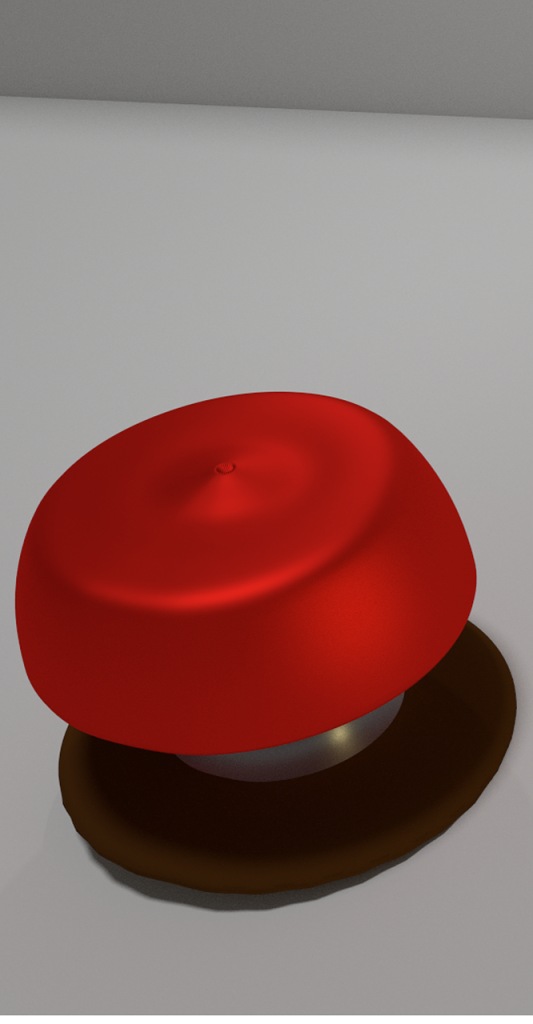…
話題
イギリス人の「政治離れ」:政権交代しても生活は変わらないという現実
…
イギリスにおける「中年の不機嫌」──魅力を失った大人たちが不愛想になる理由
…
「人は見られたように育つ」——イギリスで学んだ、評価と行動の不思議な関係
…
世界を終わらせるスイッチ:イギリスに潜む黙示の噂
…
「食洗器がない家には住みたくない」──イギリスのインド人コミュニティにおける家事観の変容と矛盾
…
イギリスの売春は合法か違法か?地域別に見る法律・規制・現状まとめ
…
「搾取していたのは同胞だった」:ユニバーサルクレジットの現実とイギリス社会の誤解
…
イギリスの配送業者が本当にどうしようもない理由:苦情を言っても無駄、AI応答だけ、改善ゼロの実態
…
イギリスにおけるコロナ後の在宅ワーク状況:2年以上経った今を考える
…