
はじめに
2024年に行われたイギリスの政権交代は、経済政策の大きな転換点となった。その後わずか1年で、企業倒産件数は急増し、経済全体に深刻な影響を及ぼしている。特に、2025年1月のデータでは、イングランドとウェールズにおける企業倒産件数が前年同月比で11%増加し、1,971件に達した。これは過去5年間で最も高い水準であり、英国経済が抱える構造的課題の顕在化ともいえる。本稿では、この倒産急増の背景にある要因、業界別の影響、政策との関連性、さらには将来への見通しについて多角的に考察する。
1. 統計から読み解く現状:倒産件数の推移
英国破産管理庁(The Insolvency Service)の発表によれば、2025年1月に倒産した企業数は1,971件。これは2024年同月から11%の増加であり、2020年のパンデミックによる一時的な企業救済策終了後を除けば、異例の数字である。
特に注目すべきは、この倒産件数の増加が一過性ではなく、2024年中期以降、持続的な上昇トレンドを描いている点である。企業の破産申請の多くが自主清算(Creditors’ Voluntary Liquidations)であることからも、経営者自らが「もはや持ちこたえられない」と判断している現実が浮き彫りになる。
2. 政策が引き起こした労働コストの上昇
新政権の掲げる「公平な労働市場の実現」という理念のもと、2025年4月から最低賃金が引き上げられ、同時に雇用主の国民保険拠出金(National Insurance Contributions)も増額された。この措置は労働者保護の観点から評価される一方で、企業、とりわけ中小企業にとっては深刻な打撃となった。
たとえば、ロンドンを拠点とする飲食チェーンの経営者は「売上は横ばいなのに、人件費だけが上がる。利益率がゼロに近づいている」と述べている。業界団体の調査によると、従業員10人以下の企業のうち42%が「人件費の増加によって、事業継続に深刻な不安を抱えている」と回答している。
3. 金利上昇と借入コストの増大
もう一つの大きな要因は、中央銀行による金利の継続的な引き上げである。イングランド銀行(Bank of England)は、2023年からのインフレ抑制のために段階的に政策金利を引き上げてきたが、その副作用として、企業の借入コストが急騰している。
特に、過去に低金利を前提として事業拡大を進めてきた企業にとっては、利払い負担が増大し、キャッシュフローに深刻な影響を及ぼしている。建設業界では、プロジェクトのための資金調達が困難になり、着工延期や中止が相次いでいる。
4. 消費者心理の冷え込みと売上の減退
インフレ率が高止まりし、生活費が増加するなか、消費者の購買意欲は著しく低下している。GfK消費者信頼感指数によれば、2025年初頭の時点で英国の消費者信頼感はマイナス27と、依然としてネガティブ領域に留まっている。
これは特に小売業、外食産業、レジャー業界などの「消費者依存型」業種にとっては致命的だ。売上が前年比で二桁減少した企業も多く、体力のない中小企業から順に市場から姿を消している。
5. エネルギー価格の高騰と産業構造への影響
ロシア・ウクライナ戦争以降、エネルギー価格の不安定さは世界中に波及しているが、英国では特に産業用エネルギー価格の上昇が深刻である。製造業、建設業、農業など、エネルギー集約型の産業では、運営コストの増大が収益を圧迫している。
たとえば、英国内のある金属加工業者は「光熱費が前年比で1.8倍になった。原材料費も上がり、価格転嫁も限界。利益が出る構造ではない」と語っている。政府のエネルギー補助政策も縮小されたことで、企業にとってのリスクは一層高まっている。
6. 小売業の危機と雇用への影響
特に注目すべきは、小売業界での倒産とそれに伴う雇用喪失の急増である。2024年には、小売業界だけで約17万人の労働者が職を失っており、前年から42%も増加している。これはリストラや倒産が相次いだ結果であり、業界にとっては未曾有の危機と言える。
たとえば、大手ホームセンターの「ホームベース」や自然派化粧品ブランド「ザ・ボディショップ」の破綻は、大規模な店舗閉鎖と人員整理を招いた。こうしたブランドは長年にわたってイギリス国内で根を張っていたため、地域経済やサプライチェーンにも波及効果が及んでいる。
7. 業界別に見る倒産の傾向
倒産件数が最も多い業種は、建設業と小売業である。建設業では、資材価格の上昇と資金調達の困難さ、さらに人手不足も加わり、プロジェクトの採算性が低下している。また、規制や安全基準の強化も、追加コストとして重くのしかかっている。
小売業に次いで深刻なのはホスピタリティ業界だ。外食産業では、原材料費の高騰、エネルギーコスト、人手不足と三重苦が続いており、特に地方都市では小規模レストランの廃業が相次いでいる。
8. 政策対応の限界と経済回復への課題
新政権は労働者保護や環境政策を優先課題に掲げているが、企業側からは「現場を無視した理想主義的な政策」との批判もある。政府は一部の中小企業に対して融資保証制度や税制優遇を実施しているが、対象や条件に制限があり、実効性には疑問の声も多い。
経済回復には、単なる支援策ではなく、以下のような構造的改革が必要とされている:
- 企業向け金融制度の柔軟化と再設計
- エネルギー価格安定化のための国家的戦略
- 中小企業支援の簡素化と即効性ある補助金制度
- 労働市場改革とスキル教育への投資強化
9. 専門家の見解と今後の展望
経済学者のマーティン・カーニー氏(元イングランド銀行総裁)は、「イギリス経済は構造転換の最中にある。倒産はその“痛み”の表れであり、今後数年間はこうしたトレンドが続くだろう」と述べている。
一方、民間調査機関のレポートでは、「2025年下半期からは金利の安定や消費の持ち直しにより、倒産件数は徐々に減少に転じる可能性がある」との予測もある。ただし、これはエネルギー価格や国際情勢の安定が前提であり、不透明感は依然として強い。
おわりに:企業・政府・市民それぞれの対応が問われる時代
現在の英国における企業倒産の急増は、単なる経済循環ではなく、政権交代、国際情勢、エネルギー問題、消費構造の変化といった複合的要因が絡んだ「構造的な変化」の表れである。企業は持続可能なビジネスモデルへの転換を求められ、政府には的確で迅速な政策対応が必要だ。
そして、消費者としての我々もまた、経済への影響力を持つ主体であることを忘れてはならない。景気の波を越えるために、国全体での連携と知恵が、今ほど必要とされている時代はない。


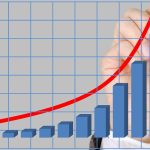


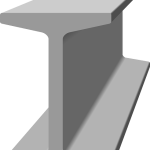




Comments