
はじめに:見えない社会の亀裂
イギリスでは近年、若者の「親離れ」が遅れ、結婚率が歴史的な低水準にまで落ち込んでいる。この現象は単なる文化の変化ではなく、深刻な経済的背景と密接に結びついており、多くの専門家が「このままでは社会の基盤そのものが揺らぐ」と警鐘を鳴らしている。
家賃の高騰、物価の上昇、そして伸び悩む賃金。この三重苦が若者たちの自立と人生設計を阻み、社会の活力を削いでいる。そしてその影響は、個人や家族の問題にとどまらず、出生率の低下、消費の停滞、地域コミュニティの空洞化など、国家全体に波及している。
この記事では、現在のイギリスが直面している「若者の孤立」と「社会構造の変化」の実態を経済的・社会的観点から検証し、私たちがこの問題にどう向き合うべきかを考察する。
第1章:結婚率の歴史的低下
イギリス国家統計局(ONS)のデータによれば、2020年のイギリスにおける結婚率は1,000人あたり3.4件と、記録史上最低の水準となった。特に20代から30代前半の結婚件数の減少が顕著であり、若年層にとって結婚が「現実的な選択肢」ではなくなっていることが伺える。
一方で、同棲カップルの割合は増加しているが、これも住宅事情や経済的な理由から、結婚という「制度」に踏み出せない層が増えていることを示唆している。結婚式や住宅購入といったライフイベントの高額化も、若者の結婚に対するハードルを引き上げている。
第2章:親元から離れられない若者たち
同じくONSの調査によると、2023年時点でイングランドおよびウェールズにおける20〜34歳の若者のうち、約34%が親と同居している。この割合は過去30年間で最も高く、特にロンドンやマンチェスターなど都市部ではその傾向が顕著だ。
家を出たくても出られない若者たちの最大の障壁は、やはり家賃の高さである。ロンドンではワンルームアパートの平均家賃が月£1,500(約28万円)を超えており、フルタイムで働いても生活が成り立たない「ワーキングプア」の状態に陥る若者も多い。
第3章:物価の高騰と停滞する賃金
2022年から続くインフレにより、イギリスではエネルギー価格や食料品の価格が急騰した。ガス代や電気代は2倍近くになり、牛乳やパン、卵といった日用品も軒並み値上げされている。
一方、実質賃金(インフレ調整後)はほとんど上昇しておらず、むしろ2008年の金融危機以降、長期的な停滞が続いている。結果として、若者が自立し、家庭を築くための「経済的基盤」が失われているのだ。
特に非正規雇用やギグワーカーとして働く若者たちは、生活の安定を得ることが難しく、将来に希望を見出せずにいる。
第4章:壊れゆく「中流」幻想
かつてイギリス社会を支えていた「中産階級」の存在が、今や幻想となりつつある。教育を受け、正社員として働き、家を買い、家庭を持つ──そうした人生のモデルケースが、今の若者には「非現実的」なものとなっている。
住宅価格の高騰とローンの規制強化により、持ち家率は低下傾向にあり、特に初めて家を購入する「ファーストタイム・バイヤー」にとっては、頭金だけで年収の数倍を要求される状況となっている。
このような社会構造の変化により、「努力すれば報われる」という信念自体が揺らぎつつある。
第5章:個人化する社会と孤立する若者
経済的な困難だけでなく、社会的なつながりの希薄化も、若者の自立と結婚への意欲を削いでいる。SNSによる「つながり」は増えた一方で、リアルなコミュニティや人間関係は分断され、孤独感を抱える若者が増えている。
NHS(国民保健サービス)の調査では、18〜34歳の若者のうち約4割が「深刻な孤独」を感じていると答えており、これは高齢者層を上回る数字である。
社会的・経済的に「接続の断絶」が起きており、その影響は精神的健康の悪化や自殺率の増加という形でも現れている。
第6章:破滅へと向かうのか?
では、イギリス社会はこのまま破滅へと向かっているのだろうか。悲観的な見方もあるが、変革の兆しも存在する。
たとえば、いくつかの自治体では「ユース・ハウジング支援」や「ベーシック・インカムの試験導入」といった政策が模索されている。また、企業側もテレワークや柔軟な雇用形態を導入し、若者の生活に寄り添う取り組みを始めている。
しかし、根本的な問題──すなわち「労働の価値に見合った対価の回復」「住宅市場の正常化」「社会的つながりの再構築」──が解決されない限り、若者たちは将来に希望を持てないままである。
第7章:必要なのは「構造改革」か、それとも「価値観の転換」か
この状況を打破するには、単なる経済対策や住宅政策にとどまらず、社会全体の「価値観の転換」が必要とされている。家を持つこと、結婚すること、子どもを持つこと──これらを義務や責任としてではなく、「選択肢」として社会が支え、祝福する空気が求められている。
同時に、国や企業、地域社会が「若者は自己責任でなんとかすべきだ」というスタンスを改め、共助の精神を取り戻す必要がある。
おわりに:未来は選べるか
若者が親元を離れ、自立し、人生を築くことが困難な社会は、長期的に見て持続不可能である。出生率は下がり、経済は停滞し、社会は分断されていく。その兆しは、すでにイギリスのあらゆる場所に表れている。
だが、未来は選べる。希望を捨てるのではなく、現実を直視し、制度を問い直し、つながりを再構築すること。破滅ではなく「再生」へと向かうために、今、社会全体が変わる時が来ている。

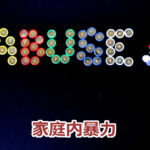








Comments